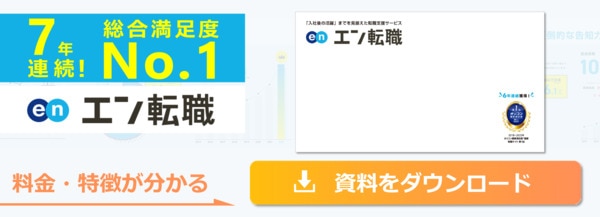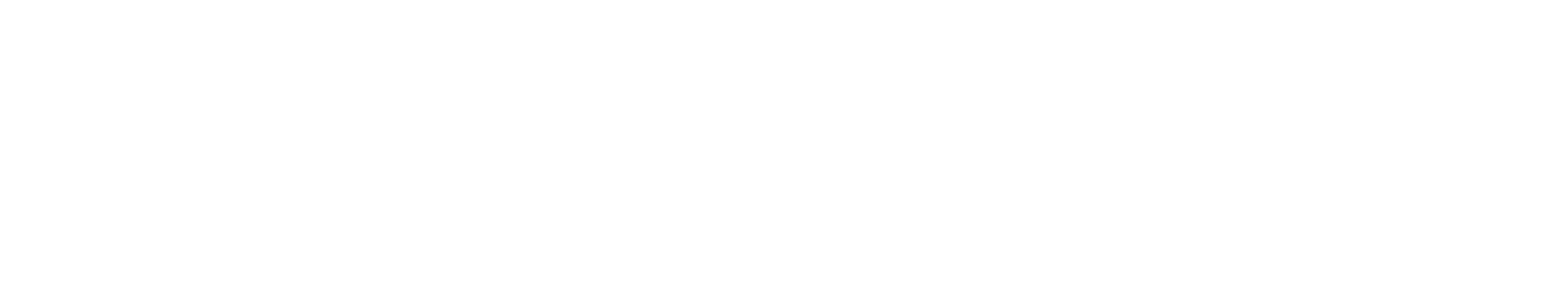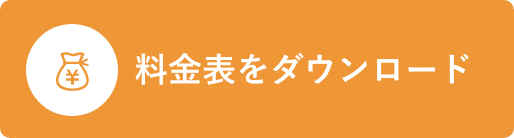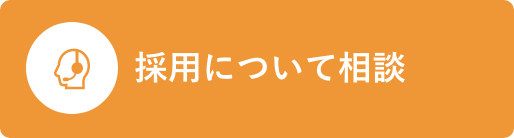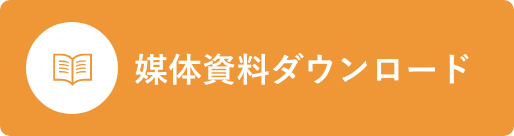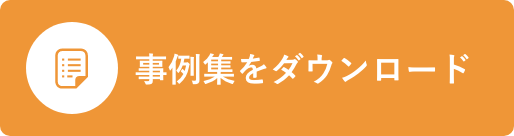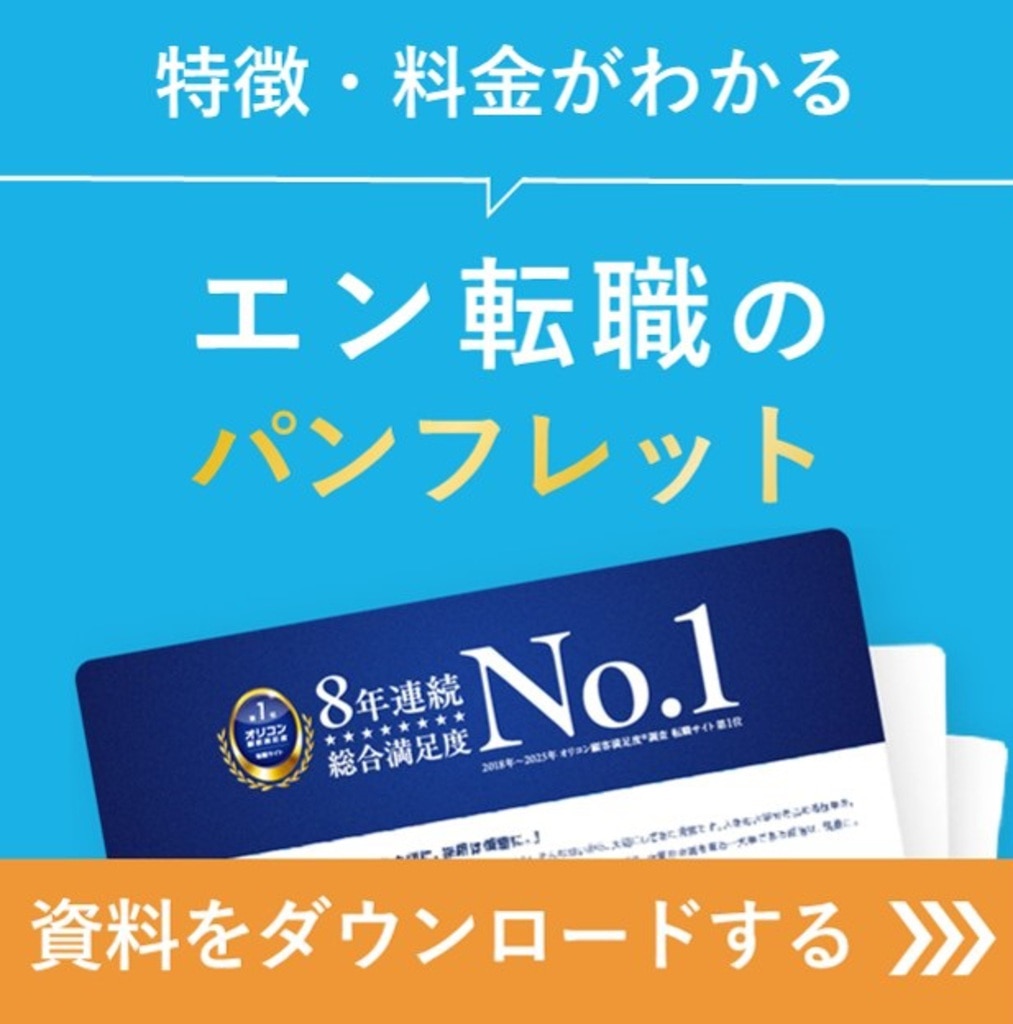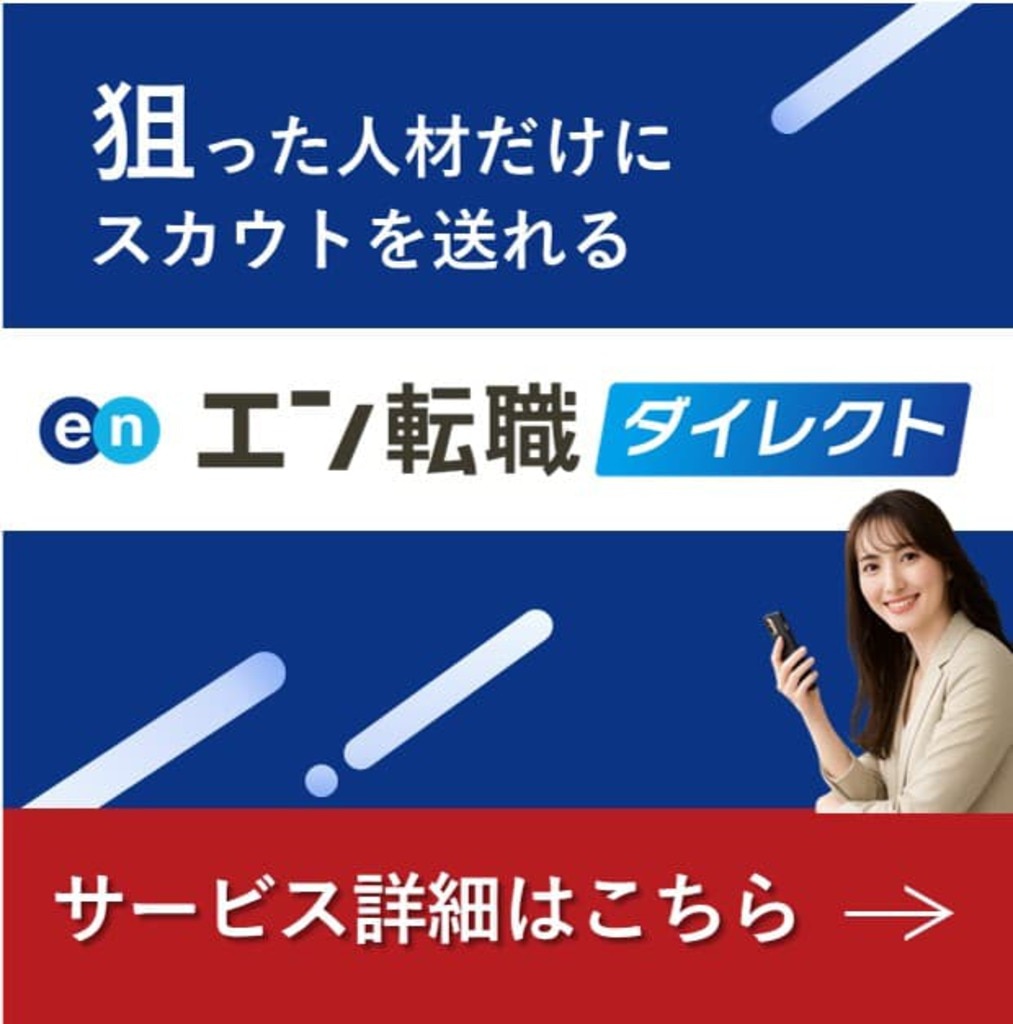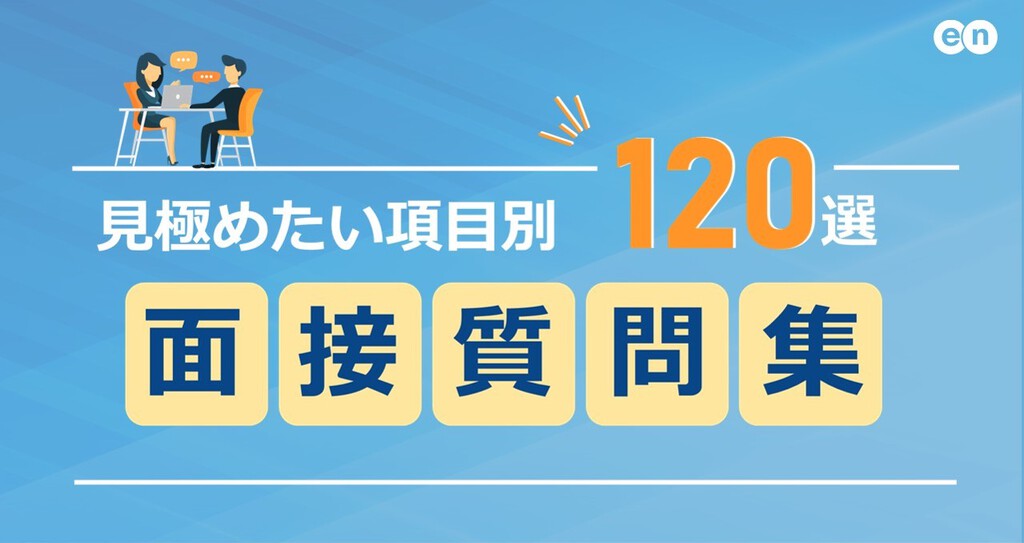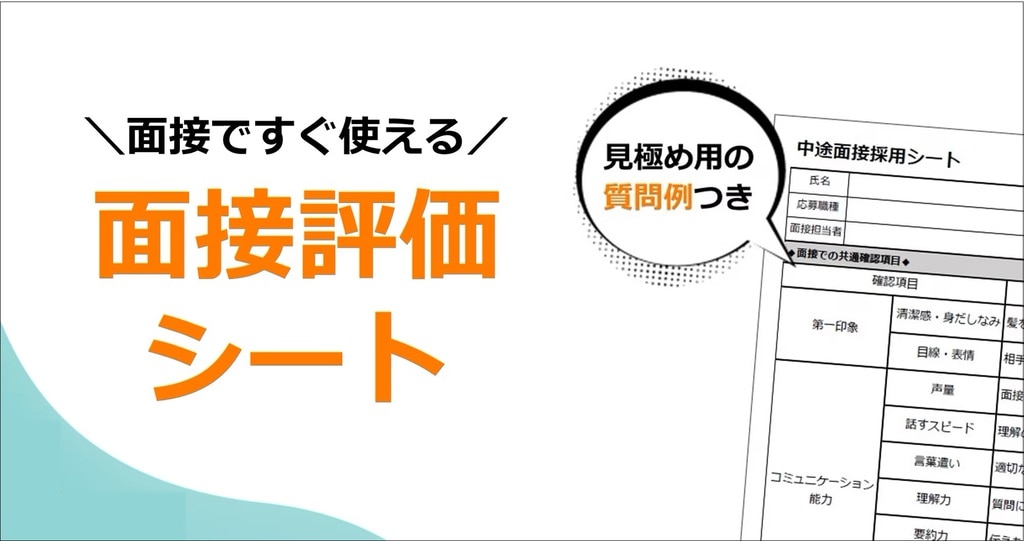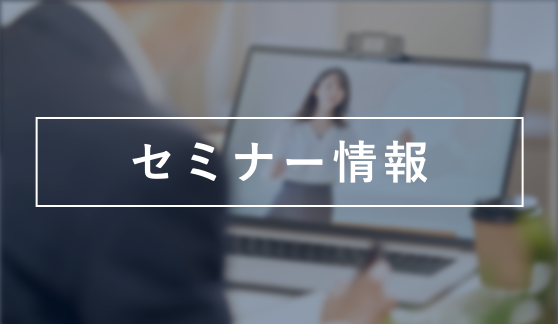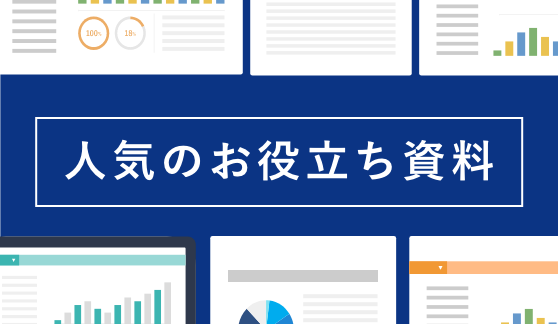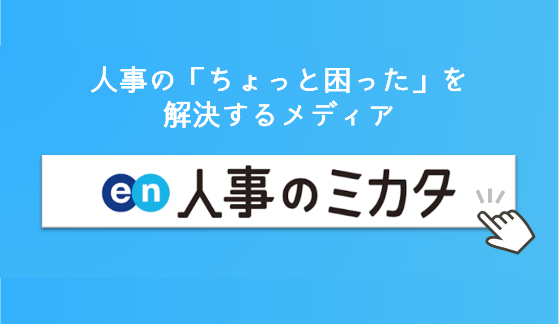中途採用の給料を決める5つの方法|流れやよくあるトラブル、防止策も解説

中途採用を実施するとき、どのような方法で給料を決めるべきか悩む人事・採用担当者は多いものです。自社の給料が競合他社の水準とかけ離れていると、求人に応募が集まりにくくなってしまうため、待遇は慎重に決定する必要があります。
本記事では、中途採用の給料の決め方をわかりやすく解説します。中途採用でよくある給料トラブルと、その防止対策も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.中途採用の給料を決める際の基本的な考え方
- 2.中途採用の給料を決める5つの方法
- 2.1.前職の給料をもとに決める
- 2.2.前職の業績をもとに決める
- 2.3.試用期間に能力を見て決める
- 2.4.競合他社の給料水準と比較して決める
- 2.5.自社の給料相場に合わせて決める
- 3.【5ステップ】中途採用の給料を決める流れ
- 3.1.求人票や求人広告に記載する条件を決める
- 3.2.採用選考で応募者の能力や経験を見極める
- 3.3.選考過程で応募者と条件のすり合わせを行なう
- 3.4.内定時に書類を交付して給料を明記する
- 3.5.応募者から交渉があった場合は適宜対応する
- 4.中途採用でよくある給料トラブルの例
- 5.中途採用で給料トラブルを防止する対策とポイント
- 5.1.求人の内容や選考方法を見直してミスマッチを防ぐ
- 5.2.求人票の待遇に関する項目を詳細に記載する
- 5.3.就業規則を適宜改定して既存社員の反発を防ぐ
- 5.4.募集職種の一般的な給料相場を把握しておく
- 5.5.選考時に希望額や前職の給料を確認する
- 5.6.希望額を聞くときは根拠もあわせて確認する
- 5.7.給料の決め方や基準を明確に定めて説明する
- 5.8.評価制度や昇給基準を明確に定めて説明する
- 5.9.内定時に交付する書類に給料を明記しておく
- 6.まとめ
中途採用の給料を決める際の基本的な考え方
求人を募集する際、給料と給与の違いがわからず混乱するケースがあります。一般的には「給料=基本給」「給与=基本給+各種手当(残業手当・通勤手当など)」とされているため、混同しないよう注意しましょう。
また、中途採用の給料を決めるときは、厚生労働省が推奨する「同一労働・同一賃金」の原則を守りつつ、「自社の賃金テーブル」「応募者の前職での収入や実績」などにも総合的に配慮することが大切です。
どれかひとつの条件だけにこだわると、自社の給料が競合他社の水準とかけ離れてしまい、求人に応募が集まりにくくなります。広い視野で情報収集して給料を決定し、その決め方や人材への評価基準などを応募者に開示することで、待遇に対する納得感を高められるでしょう。
中途採用の給料を決める5つの方法
中途採用の給料を決める方法は、主に5つに分けられます。ここからは、代表的な給料の決め方をケース別に解説します。
前職の給料をもとに決める
中途採用の市場には、「前職よりも待遇の良い会社に転職したい」と考えて転職活動を行なっている求職者が多くいます。求職者の前職よりも、自社の待遇が低い場合、選考辞退や内定辞退につながる可能性が高いでしょう。
待遇を理由とした辞退を防止するためには、求職者が前職で受け取っていた給料をヒアリングしたうえで、自社の給料を決める必要があります。
「面談や面接でヒアリングする」「前職の給料明細の提示を求める」などの方法で前職の給料を聞き出し、自社の賃金テーブルとバランスを取りながら決めるとよいでしょう。
前職の業績をもとに決める
前職の業績を参考にする場合は、求職者に過去の成果がわかる資料の提出を求め、確認したうえで給料を決定します。ただし、求職者が社会人経験はあるものの業界未経験だった場合、提出できる資料がないため、相場よりも給料が低くなってしまうでしょう。
求職者が未経験ゆえに給料が低くなることに対して、不満を感じないようにするためには、「入社後の成果次第で昇給の可能性がある」と伝えるのがおすすめです。自社の賃金テーブルと人事評価制度を明確に設定し、入社後もモチベーションを保てるよう配慮しましょう。
なお、業務内容や成果に応じて賃金を決定する給与制度は「職務給制度」と呼ばれています。職務給制度については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
▼職務給制度とは? 職能給・基本給との違いやメリット、移行手順も解説
試用期間に能力を見て決める
3ヶ月~6ヶ月程度の試用期間を設け、求職者の働きぶりや能力を実際に見てから、給料を決める方法もあります。試用期間を設ける方法は、採用選考で正式な給料を決めるのが困難な場合に有効です。
ただし、労働条件通知書や内定通知書などの書類に「記載の待遇は仮であり、正式な賃金は試用期間中の働きに応じて決定する」のような記載が必要となります。あやふやな情報で求職者を混乱させないよう注意しましょう。
競合他社の給料水準と比較して決める
競合他社や同業・同職種の給料水準を参考にする方法もあります。転職サイトに掲載された情報をチェックするなど、競合調査の手間はかかりますが、水準を揃えることで選考辞退や内定辞退を防止しやすくなるでしょう。
自社の給料を競合他社や同業・同職種の水準と合わせる方法には、以下のようなやり方が挙げられます。
- 転職サイトで競合他社の待遇をチェックする
- 求職者に他社でどのような待遇を提示されたかヒアリングする
- 厚生労働省が公表する賃金構造基本統計調査などの資料を参考にする
自社の給料相場に合わせて決める
給与体系に年功序列が反映されている企業では、自社の相場に合わせて、中途入社者の給料を決めるケースもあります。給与体系が年功序列である場合、年齢や勤続年数に応じて、明確に賃金テーブルが定められていることが多いためです。
自社の相場に合わせる方法は、中途入社者の給料を決めやすい点がメリットです。しかし近年では、成果主義的な考え方で給与体系を定める企業が増えているほか、年功序列だと前職の実績が反映されないため、求職者が不満を感じる可能性もあります。
ある程度は、前職の実績や同業他社の水準なども考慮したうえで、自社の賃金テーブルとバランスを取って、待遇を決めたほうがよいでしょう。
なお、年功序列が反映されている給与制度には「職能給制度」が挙げられます。職能給制度については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
▼職能給とは? 職務給との違いやメリット・デメリットを解説
【5ステップ】中途採用の給料を決める流れ
続いて、中途採用の給料を決める流れを解説します。中途採用では、以下の5ステップで給料を決めるのが一般的です。
- 求人票や求人広告に記載する条件を決める
- 採用選考で応募者の能力や経験を見極める
- 選考過程で応募者と条件のすり合わせを行なう
- 内定時に書類を交付して給料を明記する
- 応募者から交渉があった場合は適宜対応する
各ステップについて、詳しいやり方を見ていきましょう。
求人票や求人広告に記載する条件を決める
中途採用を実施するには、まず求人票や求人広告などを何かしらの媒体に掲載し、求人募集する必要があります。求人募集のため、求職者に開示する労働条件を決めましょう。
一般的に、求人票や求人広告には、以下のような条件を記載します。
- 賃金
- 社会保険の有無
- 試用期間の有無
- 時間外労働の有無
- 業務内容・雇用期間
- 就業場所・終業時間
- 休憩時間・休日休暇 など
「試用期間後に正式な給料を決める」「選考時に前職の収入や実績をヒアリングして給料を決める」などの場合は、その旨も求人票に記載しておくとよいでしょう。
なお、求人票については、以下の記事で詳しく解説しています。記載項目や書き方などをより詳細に知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
▼求人票とは? 役割や記載すべき項目、求職者が重視する内容などを解説
採用選考で応募者の能力や経験を見極める
求人票や求人広告を作成・掲載したら、採用選考を行ない、応募者の能力や経験を見極めましょう。一般的には、書類選考や適性検査、面接選考などを実施しますが、応募者とリラックスして話す場を設けたいときは、選考過程にカジュアル面談を取り入れてもよいでしょう。
なお、書類選考や面接選考で応募者をどのように見極めるべきか、ポイントを知りたいという方には、以下の記事がおすすめです。具体的な評価基準や質問例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
▼書類選考の通過ラインを決める5つの基準。判断のポイントと事前準備
▼中途採用の面接で使える質問例75選|人材を見極めるポイントも解説
選考過程で応募者と条件のすり合わせを行なう
面接などの選考過程で、応募者と条件のすり合わせを行ないましょう。企業側と応募者側で条件を採用前に話し合い、認識をすり合わせておくことにより、入社後のトラブルを防止できます。
たとえば前職の給料を参考にして、自社の待遇を決める場合は、「面談や面接で前職の給料をヒアリングする」「選考過程のどこかで前職の給料明細を提示してもらう」などの方法で応募者と条件のすり合わせを行なう必要があります。
条件のすり合わせをするときは、なるべく具体的な数字で給料を提示し、お互いに認識の相違が生じないよう注意しましょう。
内定時に書類を交付して給料を明記する
選考過程で条件をすり合わせし、合意が取れて内定となった場合は、改めて応募者に書類を交付して詳しい待遇を伝えます。
内定時に応募者へ交付する書類には、「内定通知書」や「労働条件通知書」があります。一般的には、労働条件通知書に賃金を明記するケースが多いですが、内定通知書に記載しても構いません。
なお、内定通知書については、以下の記事で詳しく解説しています。一般的に記載する内容や、文例テンプレートを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
▼内定通知書とは? 記載内容やテンプレート、法的効力などを紹介
応募者から交渉があった場合は適宜対応する
内定通知書や労働条件通知書を交付したあとに、応募者から条件の交渉があった場合は、ないがしろにせず誠実に対応しましょう。企業側と応募者側の双方が、納得したうえで入社とならなければ、のちに給料トラブルへと発展してしまいます。
企業としては、自社の給与体系や人事評価制度、昇給に関する評価基準などを明確に説明できるようにしておくことが重要です。応募者側の話を傾聴したうえで、自社の状況についてもきちんと説明し、お互いの納得度を高められるようにしましょう。
中途採用でよくある給料トラブルの例
続いて、中途採用でよくある給料トラブルの例を3つ紹介します。
- 内定後または入社後にミスマッチが発覚した
- 企業側と応募者側で認識に齟齬があり内定辞退された
- 中途入社者の給料が高く既存社員から反発が起こった
応募者にあいまいな情報を与えたり、既存社員の待遇とのバランスを配慮せずに給料を決めたりすると、上記のようなトラブルが生じやすくなります。各トラブルについて、詳しく見ていきましょう。
内定後または入社後にミスマッチが発覚した
中途採用では、入社後に「予想していたよりスキル不足だった」「中途入社者が期待通りに活躍してくれない」などのミスマッチが発覚するケースが多々あります。しかし、ミスマッチが発覚したとしても、スキル不足を理由に、一方的な減給をすることはできません。
企業が減給できるのは、以下のようなケースに該当する場合かつ、減給に関する事由が就業規則に明記されている場合のみと定められています。
▼企業が減給できるケースの例 |
|
企業が一方的な理由で減給すると、労働契約法違反として罰則の対象になる恐れがあります。基本的に、内定後または入社後に減給するのは難しいといえるでしょう。中途入社者の給料は、選考の段階で慎重に決定する必要があります。
企業側と応募者側で認識に齟齬があり内定辞退された
「求人広告における待遇の記載があいまいだった」などの理由で、企業側と応募者側の認識に齟齬が生じ、トラブルになるケースがあります。
待遇は応募者の生活に直結する重要事項であるため、認識に齟齬があると内定辞退や早期離職につながります。たとえば、以下のような状況では、双方の認識に齟齬が生じやすくなるため注意しましょう。
▼企業と応募者の認識に齟齬が生じやすくなる例 |
|
求人に記載された情報があいまいで、わかりづらい表記である場合、「求人票の詐称」とみなされる可能性があります。企業の信用を損ねる恐れがあるだけでなく、応募者と訴訟トラブルに発展するリスクもあるので、十分注意しましょう。
中途入社者の給料が高く既存社員から反発が起こった
優秀な人材を確保するため、応募者との待遇交渉で、給料額を相場より高く提示することがあります。会社としては高い給料を提示する代わりに、優秀な人材を採用できるため、良好な結果と言えるかもしれません。
しかし、中途入社者の給料が自社の相場より高すぎるあまりに、既存社員が不満を抱き、反発が起こる可能性もあります。場合によっては、不満を抱いた既存社員が、連鎖的に退職してしまうケースもあるでしょう。
中途入社者に対して、相場より高額な給料を設定するときは、既存社員が納得できる根拠を示すことが重要です。中途採用における給料の決め方や、評価方法などを社員全体に開示し、待遇の公平性・透明性を保つようにしましょう。
中途採用で給料トラブルを防止する対策とポイント
ここからは、中途採用で給料トラブルを防止する対策とポイントを9つ紹介します。前述の給料トラブルが自社で発生しないよう、対策を把握しておきましょう。
求人の内容や選考方法を見直してミスマッチを防ぐ
「中途入社者が予想していたよりスキル不足・経験不足だった」などのミスマッチが生じると、業務生産性に悪影響が出てしまいます。ミスマッチを防止するため、求人の記載内容や採用の選考方法を見直しましょう。
採用のミスマッチが生じる要因には、以下のようなものがあります。
- 企業側が提供する求人情報が偏っている
- 企業側が提供する求人情報があいまいでわかりづらい
- 採用担当者が応募者の資格や経歴だけで能力を評価している
採用のミスマッチを防止するには、上記の要因を改善する必要があります。改善策としては、以下のような取り組みが挙げられるでしょう。
- 求人情報をわかりやすく記載する
- 応募者の評価基準を明確に設定する
- 採用担当者の見極めスキルを育成する
なお、採用のミスマッチに関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。「ミスマッチが起こる理由や対策をもっと知りたい」という方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
▼採用ミスマッチの理由とは? 早期離職を防ぐための4つの対策
求人票の待遇に関する項目を詳細に記載する
求人票や求人広告の待遇に関する項目は、なるべく詳細かつ具体的に記載しましょう。求職者に自社の待遇条件をはっきり開示すると、認識の齟齬によるトラブルを防止できます。
また、求人情報に記載した条件と、面接で直接伝えた条件に差異があると、不信感につながります。人事・採用担当者の間で共通認識を持ち、求職者へ伝える情報に差異が生じないよう注意しましょう。
なお、求人の書き方については、以下の記事でも解説しています。求職者が入社後の様子を具体的にイメージできるような求人を作成するため、ぜひ参考にしてください。
▼応募したくなる求人広告の作り方|コピーライターが具体例つきで解説
就業規則を適宜改定して既存社員の反発を防ぐ
中途入社者の給料を既存社員よりも良くする場合は、不公平感をなくすことが大切です。既存社員が納得できる状況をつくらないと、「自分よりも社歴の浅い人が良い給料をもらっている」と内部から反発が生じる可能性があります。
社員同士の不公平感をなくすには、就業規則の待遇に関する項目を適宜改定し、新たなルールを既存社員と中途入社者の両方に適用する方法が効果的です。
中途入社者の給料を特例として高くするのではなく、「就業規則に従って決定した」という状況をつくることにより、社内の不公平感を軽減させられます。
ただし、就業規則を改定するときは、過半数労働組合と協議のうえ、意見書と就業規則変更届を作成し、労働基準監督署に届出する必要があります。就業規則の変更は、労働基準法や労働契約法など複数の法令にかかわる業務となるため、専門家に相談しましょう。
募集職種の一般的な給料相場を把握しておく
中途採用の待遇を決めるときは、募集職種の一般的な給料相場を把握しておくことも大切です。実際のところは、「自社の賃金テーブル」「前職の待遇」などをもとに給料を決めるケースが多いですが、相場を把握しておけば、応募者と待遇の交渉をする際に役立ちます。
たとえば、応募者が前職の待遇を理由に高額な給料を希望してきた場合、同業・同職種の賃金相場がわかっていれば「一般的な相場は30万円程度なので、自社もその水準を参考にしている」と根拠を示しながら交渉できるでしょう。
募集職種の一般的な給料相場を知りたい場合は、転職サイトに掲載されている競合他社の求人情報や、厚生労働省が公表する「賃金構造基本統計調査」「中途採用者採用時賃金情報」などの資料が参考になります。
選考時に希望額や前職の給料を確認する
選考時に応募者の「希望の給料額」「前職の給料」などを確認し、自社の賃金テーブルとバランスを取りながら給料を決定すると、待遇に関するトラブルを防止しやすくなります。面談や面接の場で、条件のすり合わせを行ない、企業側と応募者側で共通認識を形成できるようにしましょう。
基本的に、中途採用では「前職よりも待遇の良い企業で働きたい」と考えている応募者が多いものです。選考の段階で応募者の考えを傾聴しつつ、自社の賃金水準や評価制度に関する情報も伝えて意見をすり合わせ、双方が納得できる給料を設定しましょう。
希望額を聞くときは根拠もあわせて確認する
応募者に希望の給料額をヒアリングするときは、金額の根拠もあわせて確認しましょう。応募者によっては、根拠がないにもかかわらず、「とりあえず高めの金額を要望してみよう」と考えているケースがあります。
特に、前職の給料と希望額の差が大きい場合は、なぜその金額を希望しているのか、よく確認したほうがよいでしょう。根拠を確認する方法には、「直近2ヶ月~3ヶ月程度の給与明細を見せてもらう」「前職の源泉徴収票を提示してもらう」などが挙げられます。
応募者の過去の実績や、スキルレベルに適した給料を設定できるよう、不明瞭な部分は選考時にしっかり確認しておきましょう。
給料の決め方や基準を明確に定めて説明する
給料の決め方や決定基準は、なるべく明確に定め、わかりやすく説明できるようにしておきましょう。「何を根拠に給料を決めるのか」を明確にし、基準を公表することにより、既存社員と中途入社者の双方から納得を得やすくなります。
本記事の冒頭で述べたように、中途採用の給料の決め方は、主に以下の5つに分けられます。
- 前職の給料をもとに決める
- 前職の業績をもとに決める
- 試用期間に能力を見て決める
- 競合他社の水準と比較して決める
- 自社の給料相場に合わせて決める
「自社がどのような方法で給料を決めているのか」「なぜその方法を選択したのか」などの情報も含めて公表し、透明性・公平性の高い採用活動ができるようにしましょう。
評価制度や昇給基準を明確に定めて説明する
中途採用で未経験者を採用するとき、相場よりも給料を少し低く設定するケースがあります。応募者が待遇に不満を感じないよう「入社後の成果に応じて昇給できる」と説得する場合に備えて、自社の人事評価制度や昇給基準は明確に定めておきましょう。
自社の人事評価制度や昇給基準が、明確に定められており、きちんと説明することができれば、応募者に「社員の頑張りが評価される会社」という安心感を与えられます。入社意欲の向上やモチベーションアップにもつながるでしょう。
内定時に交付する書類に給料を明記しておく
給料などの待遇条件は、口頭で伝えるだけでは「言った/言わない」という水掛け論になる可能性が高いため、必ず書類に明記しましょう。
内定を出すときは、「内定通知書」や「労働条件通知書」などの書類を企業から応募者へ交付します。賃金・雇用形態・就労場所・勤務時間・福利厚生などの条件を漏れなく記載し、企業側と応募者側が共通の認識を持てるようにしましょう。
まとめ
中途採用における給料の決め方や、よくある給料トラブル、その防止対策などを解説しました。中途採用の代表的な給料の決め方は、主に以下の5つです。
- 前職の給料をもとに決める
- 前職の業績をもとに決める
- 試用期間に能力を見て決める
- 競合他社の水準と比較して決める
- 自社の給料相場に合わせて決める
中途採用の給料を決めるときは、厚生労働省が推奨する「同一労働・同一賃金」の原則を守りながら、「自社の賃金テーブル」や「応募者の前職での給料・実績」などにも総合的に配慮するとよいでしょう。
また、「求人にあいまいな情報を記載してしまう」などの不備があると、応募者と給料トラブルになる可能性があります。求人情報はなるべく詳細に記載し、企業側と応募者側の認識に齟齬が生じないようにしましょう。
詳細かつ魅力的な求人情報を掲載するなら、『エン転職』がおすすめです。エン転職は1,100万人以上の会員を保有する、日本最大級の中途採用向け求人サイトです。
エン転職には、取材専門のディレクターと、求人作成専門のコピーライターが所属しています。プロがわかりやすい求人を作成するため、企業の情報を正しく、魅力的に求職者へ伝えられるでしょう。
また、エン転職はどの料金プランを選んでも、求人に掲載できる情報量が「一律最大」です。A4用紙4枚分の求人原稿に加えて、写真3点、動画1点といった多くの情報を掲載できるため、企業の強みや仕事の魅力を存分にアピールできます。
中途採用でお悩みの方は、以下のエン転職お問い合わせ窓口より、ぜひお気軽にご相談ください。
▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。
ほかにもエン転職には採用を成功に導くさまざまな特徴があります。エン転職の料金表・パンフレットのダウンロードやサービスの詳細については、こちらからご確認ください。
▼エン転職のサービス紹介ページ