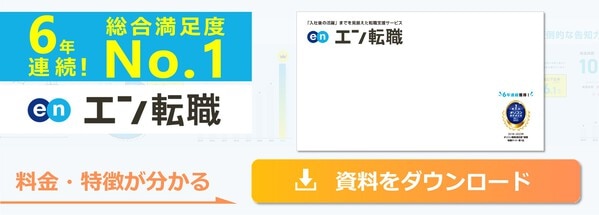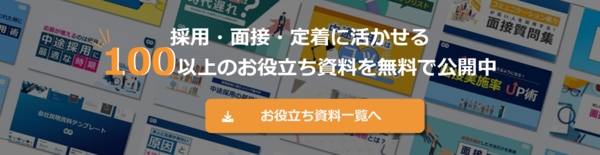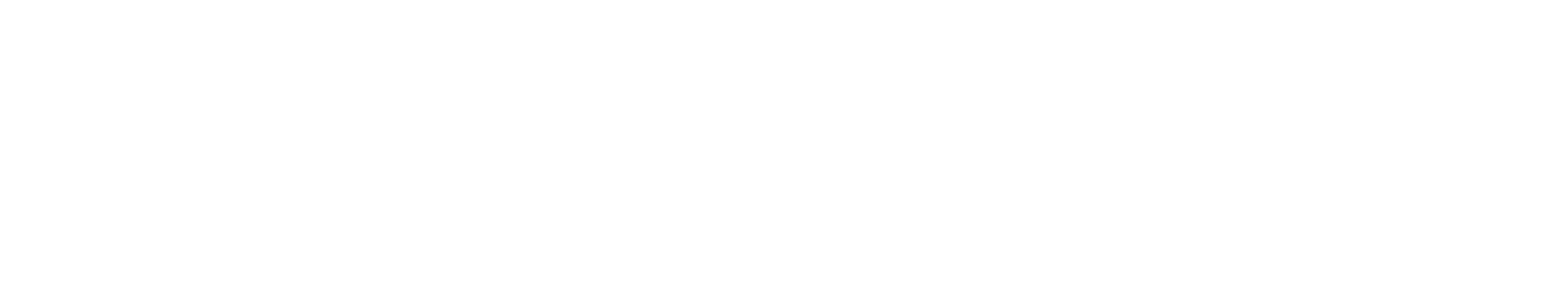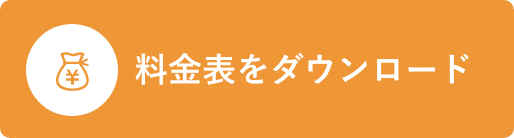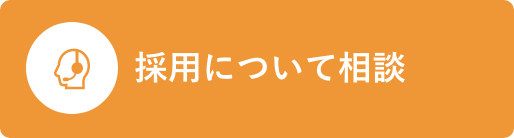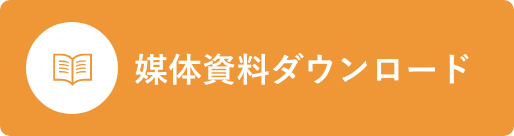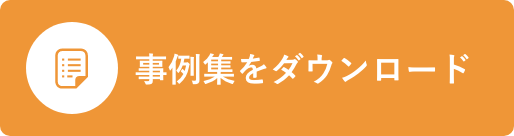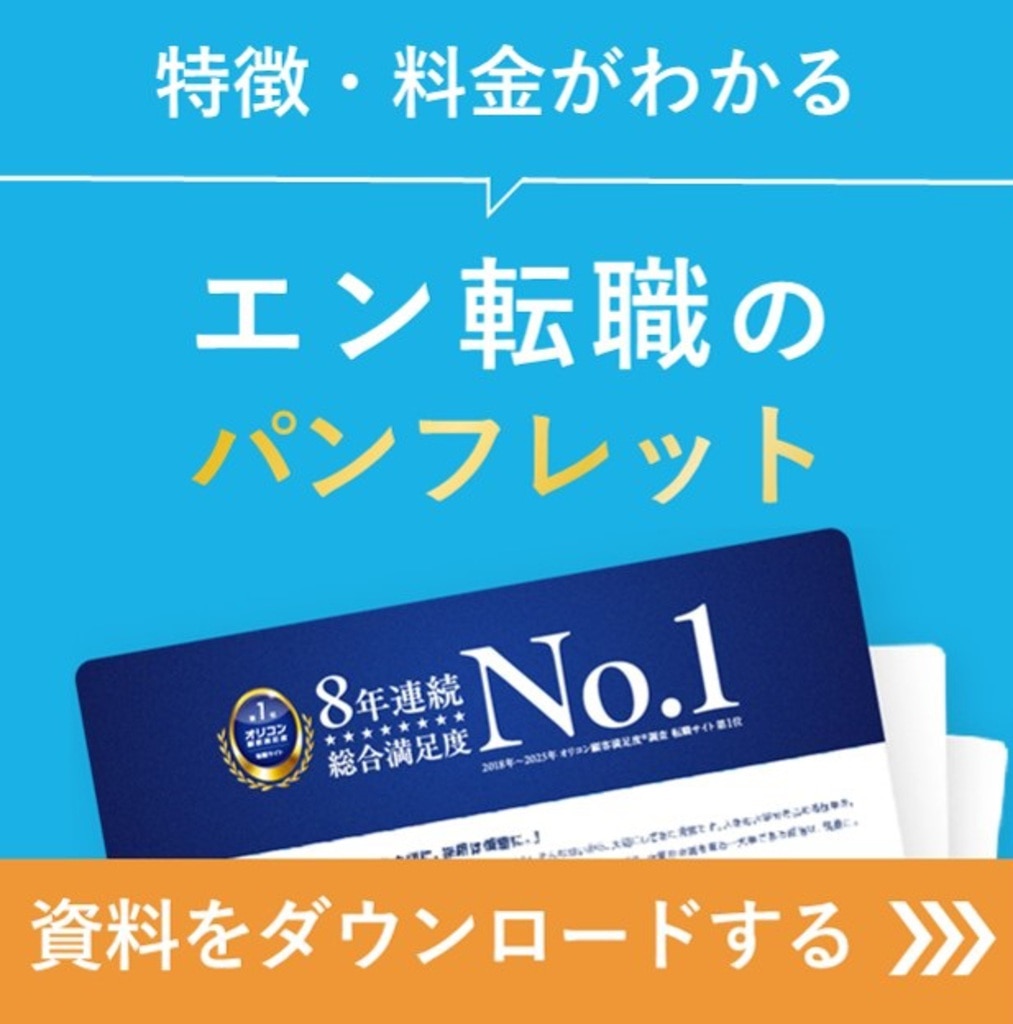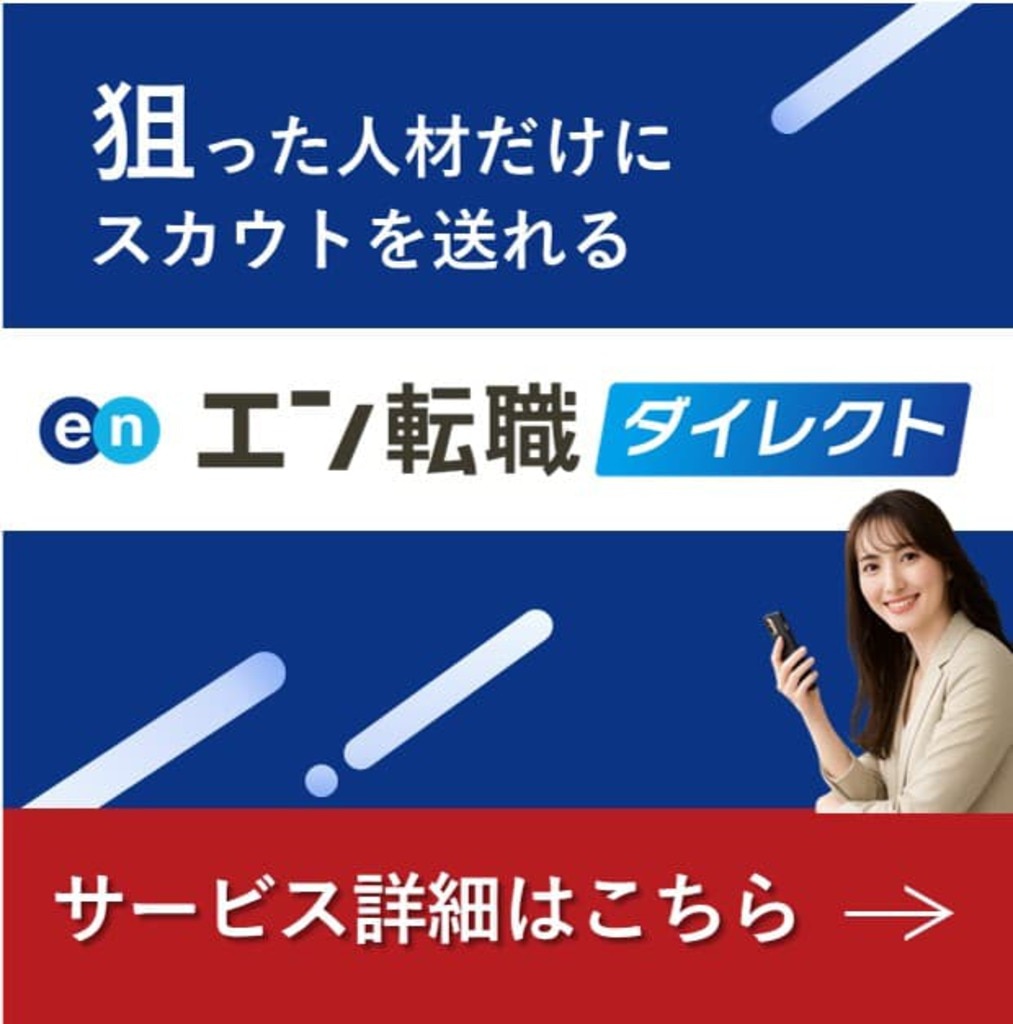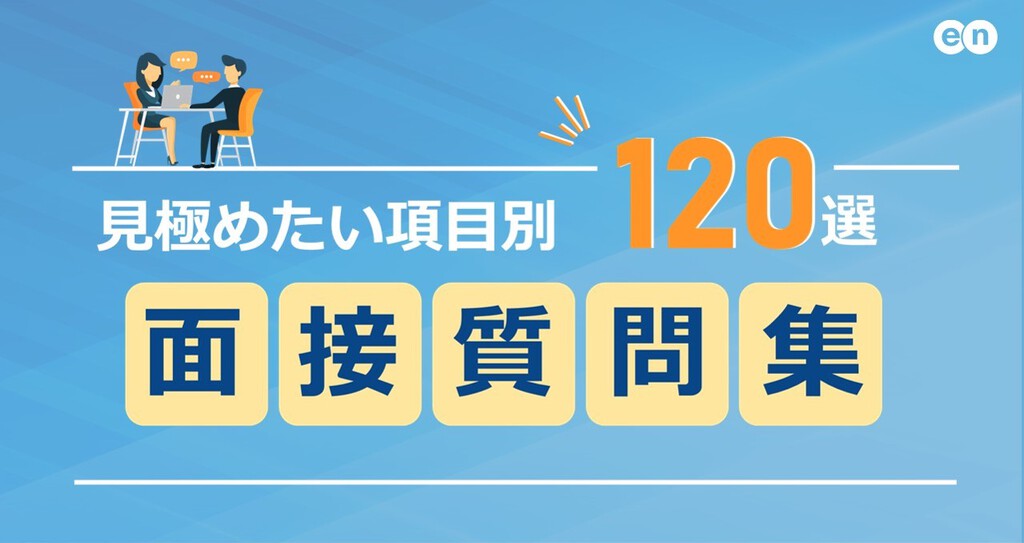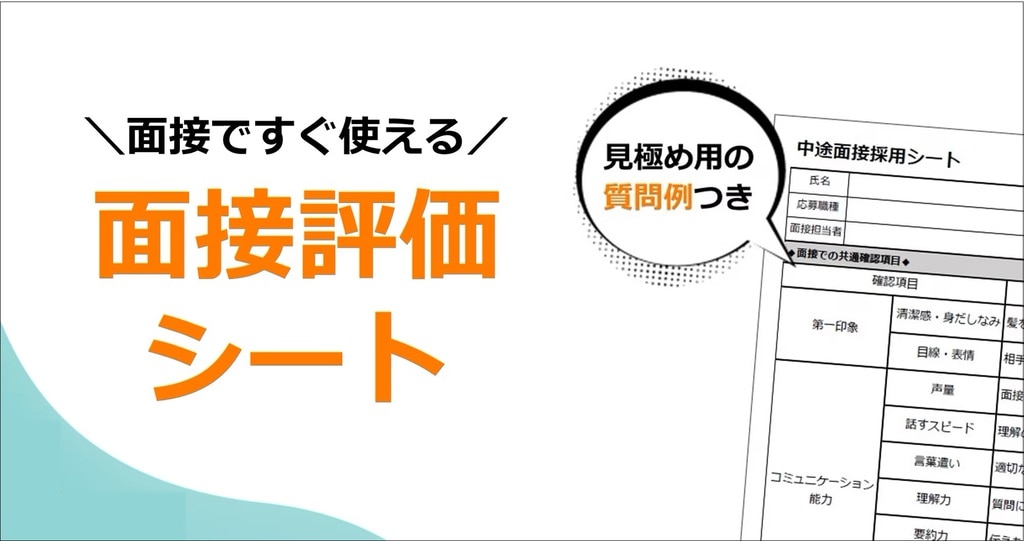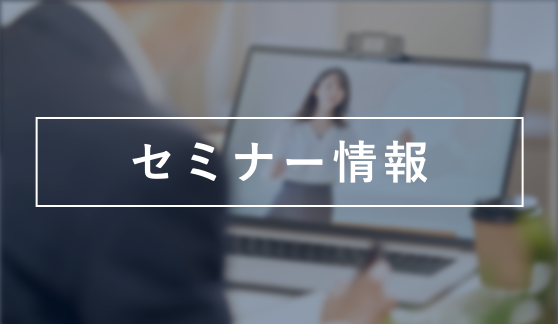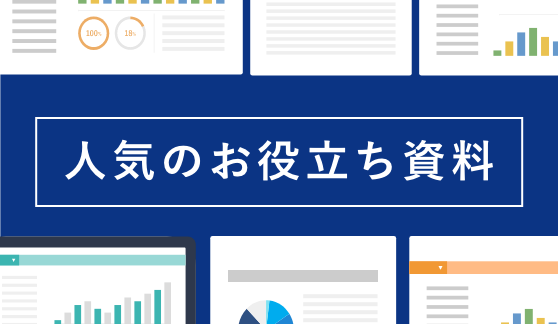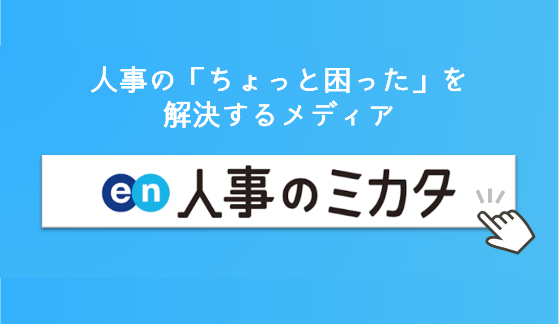新卒の採用単価はいくら? 計算式と平均値、削減する方法やポイントも解説

「新卒採用の平均的な採用単価って、どのくらいなの?」
「新卒採用の採用単価を削減したいけど、何をすればよいかわからない…」
新卒採用を行なうにあたり、上記のようにお悩みの企業は多いでしょう。
近年は労働人口の減少によって、企業間の採用競争が激化しています。ある程度はしっかりコストをかけなければ、必要な人材を確保することが難しくなっているため、「新卒採用の費用と成果」を天秤にかけ、悩む企業が増えているようです。
そこで本記事では、新卒採用の採用単価について、平均値や動向、削減方法などを解説します。新卒採用の採用単価を削減するポイントや、おすすめの求人サービスも紹介しますので、「新卒採用の費用を見直したい」とお悩みの方は、ぜひご覧ください。
目次[非表示]
- 1.採用単価と採用コストの違い
- 2.新卒の採用単価の計算方法
- 3.新卒の採用単価の平均値
- 4.新卒採用におけるコストの動向
- 5.新卒の採用単価を削減する7つの方法
- 5.1.無料の求人媒体を活用する
- 5.2.費用対効果の高い求人媒体を活用する
- 5.3.リファラル採用を行なう
- 5.4.ダイレクトリクルーティングを行なう
- 5.5.ソーシャルリクルーティングを行なう
- 5.6.オウンドメディアリクルーティングを行なう
- 5.7.大学や専門学校の掲示板に求人情報を貼り出す
- 6.新卒の採用単価を削減する4つのポイント
- 6.1.自社の採用要件を明確化する
- 6.2.採用のミスマッチを防止する
- 6.3.新卒採用の工程を見直す
- 6.4.内定者フォローを実施する
- 7.採用単価を抑え、若手採用を成功させるなら『エン転職』
- 7.1.会員数が業界最大級!
- 7.2.会員の若手比率が高い
- 7.3.採用ミスマッチを防止しやすい
- 7.4.プランにかかわらず求人の情報量が多い
- 7.5.プランにかかわらず求人の露出量が多い
- 8.まとめ
採用単価と採用コストの違い
採用活動の費用を表す用語には、「採用単価」と「採用コスト」があります。まずは、採用単価と採用コストの違いを解説します。
採用単価
採用単価とは、採用1人あたりに発生した費用のことです。たとえば、新卒採用を実施し、200万円かけて5人の新入社員を採用したとします。この時、新卒採用の採用単価は「200万円÷5人=40万円」となります。
採用単価は、企業が採用で使った求人媒体(就職サイトや人材紹介サービスなど)の費用対効果を測る指標として活用されています。新卒採用の採用単価を計算すれば、「自社が新卒採用で使った求人媒体の費用対効果」が明確化されるでしょう。
採用コスト
採用コストとは、企業の採用活動にかかったコスト全般を指す言葉です。採用コストには、「内部コスト」「外部コスト」という2つの考え方があり、それぞれのコストを足した合計が「採用コスト」と呼ばれています。
内部コストは、主に採用担当者の人件費や交通費などの「社内で発生したコスト」を指します。内部コストには、社内で発生した金銭的コストに加えて、採用担当者の時間的コストなども含まれます。
外部コストは、求人の掲載費や採用管理システムの利用料、合同企業説明会へのブース出展料といった「社外で発生したコスト」を指します。採用活動における内部コストと外部コストの例を下記にまとめましたので、参考にご覧ください。
内部コストの例 |
外部コストの例 |
|
|
新卒の採用単価の計算方法
新卒採用の採用単価は、以下の計算方法で算出することが可能です。
|
新卒採用にかかった費用の総額÷採用人数=新卒採用の採用単価 |
たとえば、300万円の費用をかけて10人の新入社員を採用した場合は、「300万円÷10人=30万円」となるため、新卒採用の採用単価は30万円です。
新卒の採用単価の平均値
株式会社マイナビが実施した調査「2024年卒 企業新卒内定状況調査」によると、2024年の新卒採用における採用単価の平均値は56.8万円でした。
上記のアンケート調査に回答した企業のうち、上場企業の新卒採用単価の平均値は49.0万円。非上場企業の新卒採用単価の平均値は57.5万円でした。
▼新卒入社予定者1人あたりの採用費の平均値 | |
回答全体 |
56.8万円 |
上場企業 |
49.0万円 |
非上場企業 |
57.5万円 |
出典:株式会社マイナビ「2024年卒 企業新卒内定状況調査」
新卒採用におけるコストの動向
近年は、少子高齢化により労働人口が減少しているため、企業間の採用競争が激化しています。労働人口が減少しているなかで、新卒採用を実施すると、「1人の学生を複数の企業で取り合う」という状況が発生しやすくなります。
このような状況下では、「有料の求人サービスを複数併用する」など工夫し、しっかりとコストをかけて新卒採用に取り組まなければ、必要な人材を確保するのが難しいでしょう。そのため、新卒採用に必要なコストは上昇する傾向があります。
従業員数が多い企業ほど、新卒採用のコストが高い傾向
就職みらい研究所の資料「就職白書2023」によると、2024年卒採用の見通しについて、採用活動にかける費用が「増える」と回答した企業は31.3%、「前年と同じ」と回答した企業は62.1%、「減る」と回答した企業は6.6%でした。
以下の表は、アンケート調査に集まった企業からの回答を、従業員数別にまとめたものです。従業員数にかかわらず、「減る」と回答した企業は圧倒的に少ないため、「ある程度はきちんとコストをかけて新卒採用を実施しなければ、成果につながらない」と考えている企業が多い様子がうかがえます。
増える |
同じ |
減る |
|
回答全体 |
31.3% |
62.1% |
6.6% |
従業員数300人未満 |
27.6% |
64.9% |
7.5% |
従業員数300~999人 |
30.1% |
63.2% |
6.7% |
従業員数1000~4999人 |
36.5% |
59.2% |
4.3% |
従業員数5000人以上 |
34.0% |
54.6% |
11.3% |
新卒採用のコストに課題を感じる企業が増えている傾向
前述したアンケート調査の「2023年卒採用の振り返り」において、新卒採用の課題点に「採用にかかわるコスト」を挙げている企業が27.6%ありました。
前年の調査では、同項目の数値が26.3%だったため、上昇傾向にある新卒採用のコストに課題を感じる企業が増えている様子がわかります。
社会の少子高齢化が深刻化するにつれて、労働人口は徐々に減少します。今後も新卒採用のコストは、上昇傾向が続くと考えられるでしょう。
▼新卒採用の課題点に「採用にかかわるコスト」を上げた企業の割合 | |
2022年調査 |
26.3% |
2023年調査 |
27.6% |
新卒の採用単価を削減する7つの方法
前章で述べた通り、新卒採用のコストは上昇傾向となっています。しかし、企業が新卒採用にかけられる予算には限りがあるため、必要な部分にはしっかり費用をかけつつ、ムダな費用は削減しなくてはなりません。
ここからは、新卒採用にかかる費用を削減し、採用単価を抑える方法を7つ紹介します。新卒採用の費用を「自社にとっての適正ライン」に抑えられるよう、ぜひご覧ください。
無料の求人媒体を活用する
求人を掲載する媒体のなかには、無料で使えるものがあります。たとえば、下記のような無料の求人媒体を活用し、求人の掲載費用を削減するとよいでしょう。
- ハローワーク
- エンゲージ
- Indeed(インディード)
- Googleしごと検索
- 求人ボックス
- スタンバイ
無料の求人サービスについては、以下の記事で詳しく解説しています。「求人を無料掲載できるサービスを探している」という方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
▼無料で求人掲載できるサービス17選!向いている企業や活用のコツも解説
費用対効果の高い求人媒体を活用する
新卒採用の採用単価を削減するためには、自社が利用した求人媒体の採用成果を洗い出し、費用対効果を分析することも大切です。有料の求人媒体のなかで「自社にとって費用対効果が高かった媒体」を明確化し、新卒採用で重点的に活用するようにしましょう。
費用対効果が低かった媒体の利用を停止し、費用対効果が高かった媒体のみ重点的に活用することで、ムダな費用を削減しながら、効果的な新卒採用を行なえるようになります。
リファラル採用を行なう
リファラルは「紹介」や「推薦」といった意味を持つ単語です。リファラル採用とは、自社の既存社員から友人や知人を紹介してもらい、選考を行なったうえで採用する手法を指します。
リファラル採用には、就職サイトや新卒採用向け人材紹介サービスなどの求人媒体を介すことなく、新入社員を確保できるメリットがあります。
友人や知人を紹介してくれた既存社員に対し、インセンティブ(紹介報酬)を支払うケースもありますが、基本的には外部媒体を利用するよりも安価で済む場合がほとんどです。
リファラル採用に関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。成功させるためのプロセスや注意点などを紹介していますので、ぜひ併せてご覧ください。
▼リファラル採用とは? メリットやデメリット、費用、成功ポイントを紹介
ダイレクトリクルーティングを行なう
ダイレクトリクルーティングとは、企業の人事・採用担当者が、自社の採用要件を満たす学生に、スカウトメールなどを用いて直接アプローチする手法のことです。
新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービスは多数存在しますが、サービスの提供会社が保有する人材データベースに、サービスを利用する企業が直接アクセスし、登録されている人材のプロフィールなどを確認してスカウトする手法が一般的です。
ダイレクトリクルーティングには、企業がデータベースに登録された人材の学歴や保有資格などの情報を確認したうえで、直接アプローチできるメリットがあります。以下の記事で詳細なメリットや費用相場、サービスの選び方などを解説していますので、ぜひご覧ください。
▼ダイレクトリクルーティングとは?従来の採用方法との比較・サービスの選び方
ソーシャルリクルーティングを行なう
ソーシャルリクルーティングとは、SNSを活用して人材を確保する採用手法のことです。SNSは無料で活用できるものが多いため、企業が欲しい人材を探してアプローチするための費用を削減できます。
消費者庁の調査資料「令和4年版 消費者白書」によると、10代~30代の若年層におけるSNS利用率は、9割を超えていることがわかっています。
新卒採用では10代~20代の人材を採用するケースが多いため、「自社の採用ターゲットが利用していそうなSNS」に照準を絞って活用するのもよいでしょう。
ソーシャルリクルーティングについては、以下の記事で詳しく解説しています。実施する際のポイントなどを知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
▼ソーシャルリクルーティングのメリットは? 注意点や運用のポイントを解説
オウンドメディアリクルーティングを行なう
オウンドメディアとは、企業が自社で保有・運営するメディアのことです。つまり、オウンドメディアリクルーティングとは、企業が自社メディアを使って求人情報や企業情報を発信し、人材採用に活かす手法を指します。
オウンドメディアリクルーティングで自社の情報を継続的に発信すると、学生が自社への理解を深めやすくなります。自社の事業内容や社風を理解したうえで、求人に応募してくれる学生が多くなるため、採用ミスマッチを防止できるでしょう。
オウンドメディアリクルーティングについては、以下の記事で詳しく解説しています。メディア運用に必要なコンテンツや、導入フローなどを知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
▼オウンドメディアリクルーティング|特徴・コンテンツ例・手順などを解説
大学や専門学校の掲示板に求人情報を貼り出す
会社の近くに高校や大学、専門学校などの教育機関がある場合は、新卒向けの求人情報を校内の掲示板に貼り出すことは可能か確認してみるとよいでしょう。
学校によっては、求人情報の貼り出しを許可してくれるケースがあります。学校に求人情報を貼り出す場合は、原則無料なので、求人掲載費の削減につながります。
新卒の採用単価を削減する4つのポイント
続いて、新卒採用の採用単価を削減するポイントを4つ紹介します。下記4点を意識して新卒採用に取り組むと、費用削減につながるでしょう。
自社の採用要件を明確化する
採用要件とは、企業が採用活動で人材の合格/不合格を決めるための評価基準のことです。たとえば、新卒採用の採用要件には「コミュニケーション能力の高さ」「就業意欲の高さ」「主体性の有無」などが挙げられます。
新卒採用を開始する前に、自社の採用要件を明確にしておきましょう。一定の評価基準を設けておくことにより、学生を適切に評価しやすくなります。
適切な評価が行なえる環境を構築すれば、「採用活動の長期化」や「自社とのミスマッチ」を防止できるため、新卒採用のコスト削減につながります。
採用のミスマッチを防止する
採用のミスマッチとは、企業と学生(求職者)の間で、業務や社風などの認識にズレが生じたまま採用に至ってしまうことをいいます。採用のミスマッチは、新入社員の早期離職につながりやすいものです。
新入社員が早期離職してしまうと、企業側は再びコストをかけて採用活動を実施しなくてはならなくなります。余計な費用が増えてしまうため、採用のミスマッチが生じないよう、対策を講じる必要があるといえるでしょう。
採用のミスマッチを防ぐには、下記のような対策が有効です。
- 新卒採用を行なう各部署の採用要件を明確にする
- 求人を正確に作成・掲載する(誇張表現を控える)
- 適性検査や性格検査などを実施し、自社とのマッチ度を測る
- 学生を深掘りできる面接を実施し、自社とのマッチ度を測る
採用のミスマッチを防止すれば、新卒採用の無駄なコストを削減できるでしょう。
新卒採用の工程を見直す
新卒採用の工程を見直すことも、コスト削減につながります。たとえば、「企業説明会の開催回数を見直す」「一次面接をオンラインに変更する」などの見直しを行なうと、会場設営費や交通費の削減が可能となります。
既存の採用工程が適切であるか改めて見直し、必要以上にコストがかさんでいる部分を改善しましょう。採用工程の見直しにより、金銭的コストを削減できるだけでなく、採用担当者の労力や時間的コストも削減できるようになります。業務負担の軽減にもつながるでしょう。
内定者フォローを実施する
新卒採用の採用単価を抑えるには、内定者に対するフォロー施策を行ない、内定辞退や早期離職を防ぐことも重要です。内定辞退や早期離職を防ぎ、新入社員の定着率を向上させれば、採用活動を実施する機会が減るためコスト削減につながります。
内定者フォローの代表的な施策には、下記のようなものが挙げられます。新卒採用で内定者が決まった際に、実施してみるとよいでしょう。
- 内定者面談
- 内定者懇親会
- 社内報の送付
- 社内見学・職場体験
- オンライン研修・eラーニング
なお、内定者へのフォロー施策については、以下の記事でより詳しく解説しています。内定者フォローによくあるイベントなどを紹介していますので、ぜひご覧ください。
▼内定者フォローの内容とイベント例、内定辞退を防ぐポイントも解説
採用単価を抑え、若手採用を成功させるなら『エン転職』
最後に、若手人材の採用におすすめの求人サービスを紹介します。費用対効果が高い求人サービスを利用し、若手採用のコストを削減したいとお考えの方には、『エン転職』がおすすめです。
エン転職は、総合人材サービスを展開するエン・ジャパン株式会社が運営しており、業界最大級の会員数を誇る求人サイトです。主な特徴や強みをまとめましたので、求人サービスを選定する際の参考にご覧ください。
会員数が業界最大級!
エン転職は、1,100万人以上の会員数を誇る、日本最大級の求人サイトです。エン転職の会員数は、1ヶ月に約7万人のペースで増加中。「およそ1分間に1人」という驚異的なペースで、新規会員が増えています。
会員の若手比率が高い
エン転職には、若手会員の比率が高いという特徴があります。1,100万人以上いる会員のうち、約7割が35歳以下の若手人材です。
主要な求人サイトのなかでも、若手会員の比率が特に高いため、「会社の次世代を担う若手人材を積極採用したい」とお考えの方にぴったりな求人サービスといえます。
エン転職の会員データについては、以下の記事でより詳しく解説しています。会員の年齢構成比や男女比、学歴比などを詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。
▼【最新版】エン転職の会員数・会員データはコチラ!<2025年7月更新>公式サイトが徹底解説
採用ミスマッチを防止しやすい
エン転職の求人広告には、「仕事の厳しさ」「向いていない人」という項目があります。一見、ネガティブな情報を掲載しているように思えるかもしれません。
しかし、求人にあえて「仕事の厳しさ」「向いていない人」という項目を設けることにより、入社前後のイメージギャップを防止しやすくなるメリットがあります。
自社の業務内容や社風、職場環境とマッチする人材からの応募を集めやすくなるため、採用ミスマッチの防止に役立ちます。
プランにかかわらず求人の情報量が多い
エン転職には、「SS・S・A・B・C」という5種類の基本企画(基本プラン)があります。上位企画ほど機能性は充実しますが、実は求人広告の情報量に関しては、プランによる違いが特にありません。
エン転職は利用するプランにかかわらず、「A4用紙4枚分相当」の情報を掲載することが可能です。テキストだけでなく、写真3枚・動画1点も掲載できるため、企業の魅力を十分アピールできます。
プランにかかわらず求人の露出量が多い
一般的な求人サイトは、上位プランほど求人のサイト内表示順位が高くなります。つまり採用予算が高く、上位プランを利用できる企業でなければ、求人情報の閲覧数や応募数を増やすことが難しいのです。
しかし、エン転職は「プラン×人材とのマッチ度」という独自ロジックで、求人のサイト内表示順位を決定しています。会員が絞り込んだ検索条件と求人のマッチ度が高ければ、どのプランでも上位表示のチャンスがあるため、求人の閲覧数・応募数アップが期待できるでしょう。
エン転職ならば、採用にかかるコストを抑えながら、若手人材を確保できる可能性が高くなります。以下のページより、エン転職のサービス資料を無料ダウンロードしていただけますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
▼エン転職のサービス資料を無料ダウンロードする
まとめ
新卒採用の採用単価について、平均値や動向、削減方法などを紹介しました。新卒採用の費用相場は、上昇傾向となっています。昨今は、少子高齢化による労働人口の減少で、企業間の人材獲得競争が激化しているため、今後も上昇傾向が続くでしょう。
「新卒採用だけでなく、第二新卒の採用も実施したい」
「20代~30代の若手人材を確保したい」
このようにお考えの場合は、ぜひ『エン転職』をご活用ください。
エン転職は企業と求職者、双方からの利便性を追求し、オリコンヒットチャートでお馴染み「オリコン顧客満足度調査」の「転職サイト部門」において、8年連続 総合満足度第1位を獲得(2025年時点)しています。
いま1番ユーザーから選ばれている求人サイトだからこそ、若手人材の採用にもおすすめです。採用活動にお悩みの方は、以下のエン転職お問い合わせ窓口より、ぜひお気軽にご相談ください。
▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。
他にもエン転職には採用を成功に導く様々な特徴があります。エン転職の料金表・パンフレットのダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますので合わせてご覧ください。
▼エン転職のサービス紹介サイト