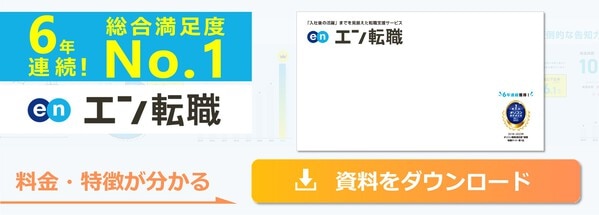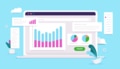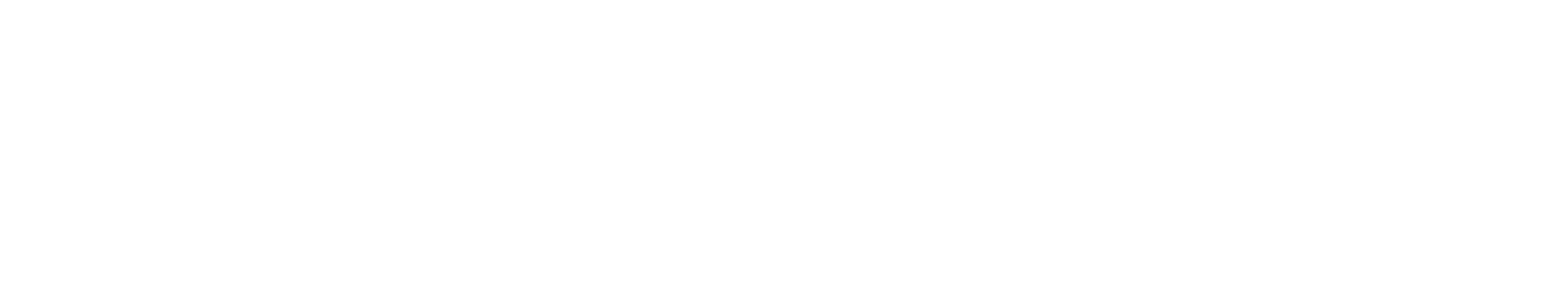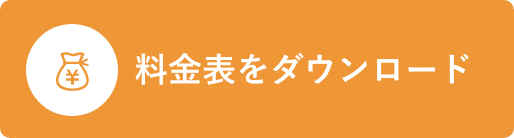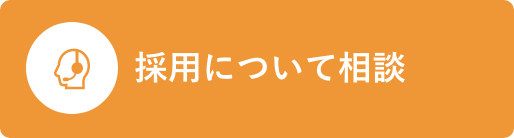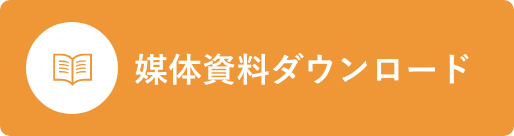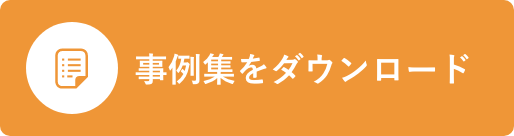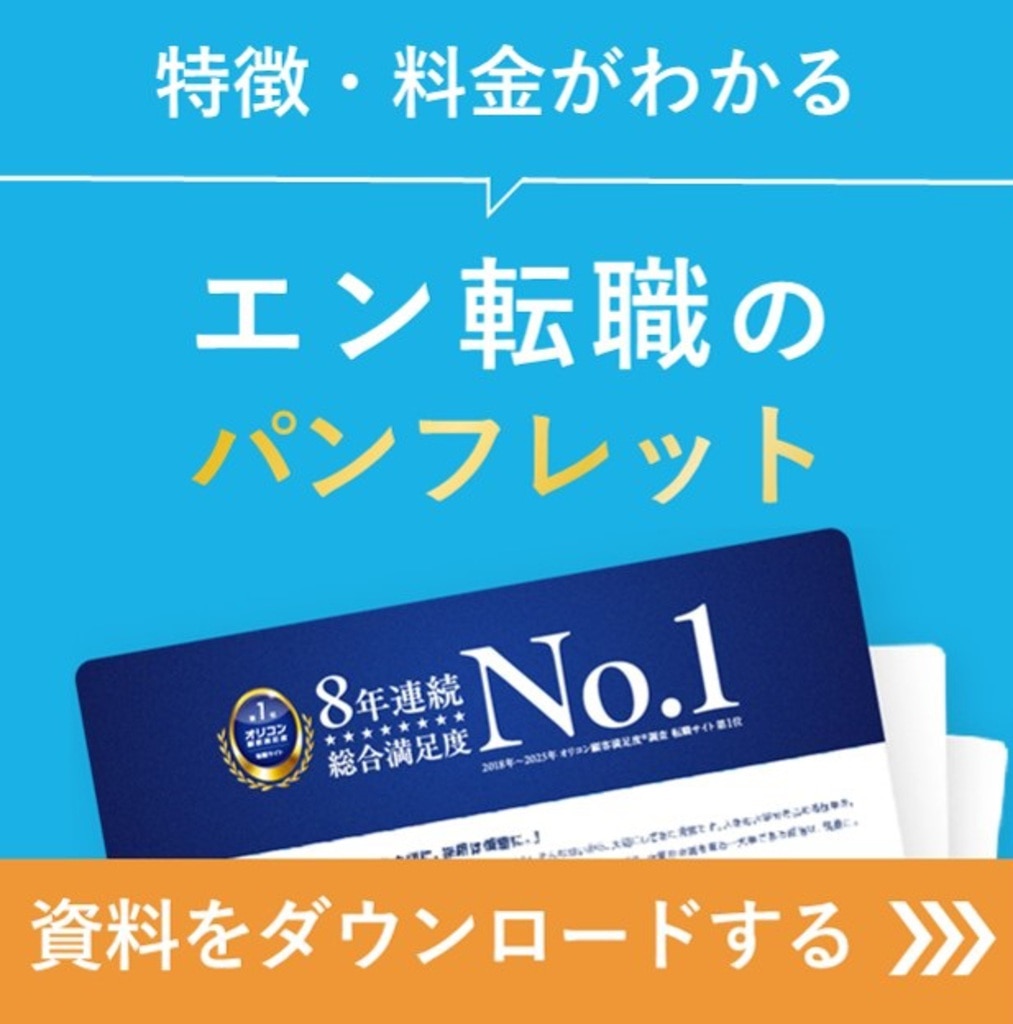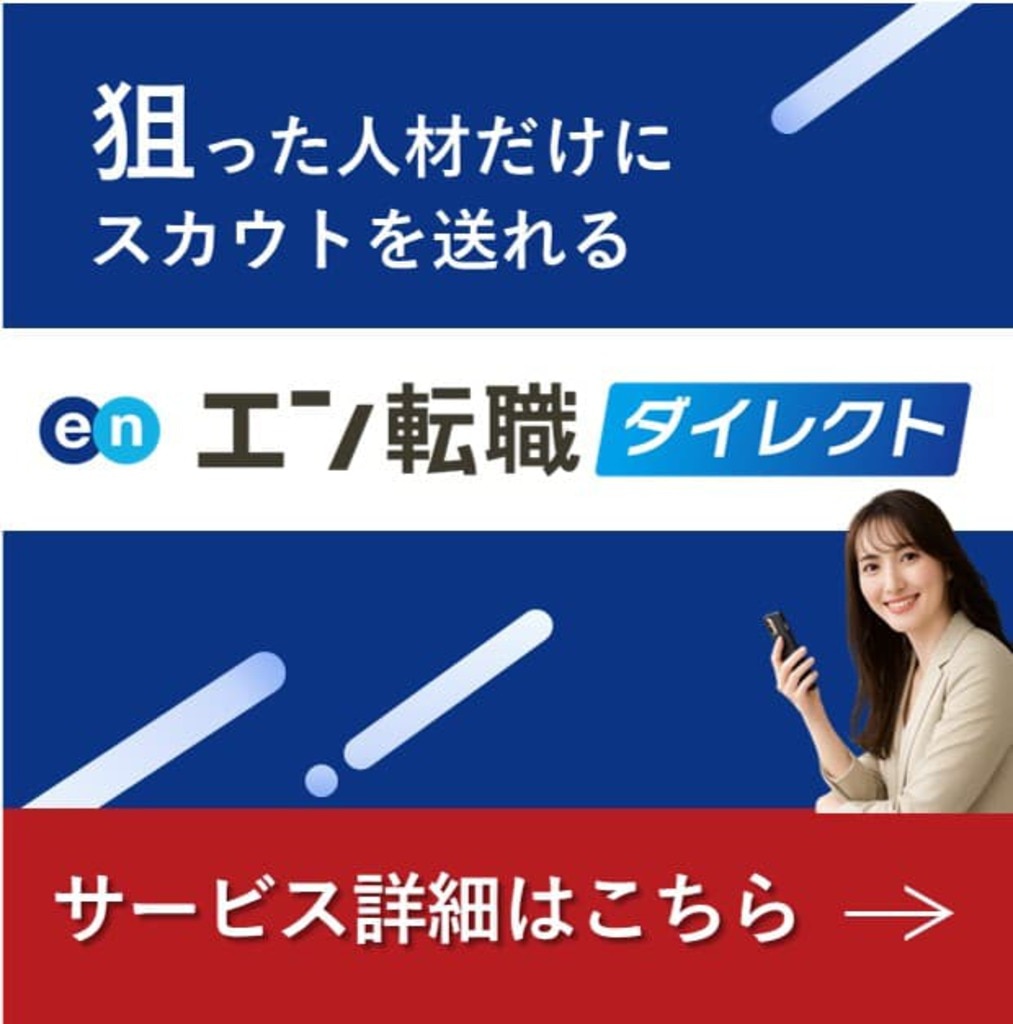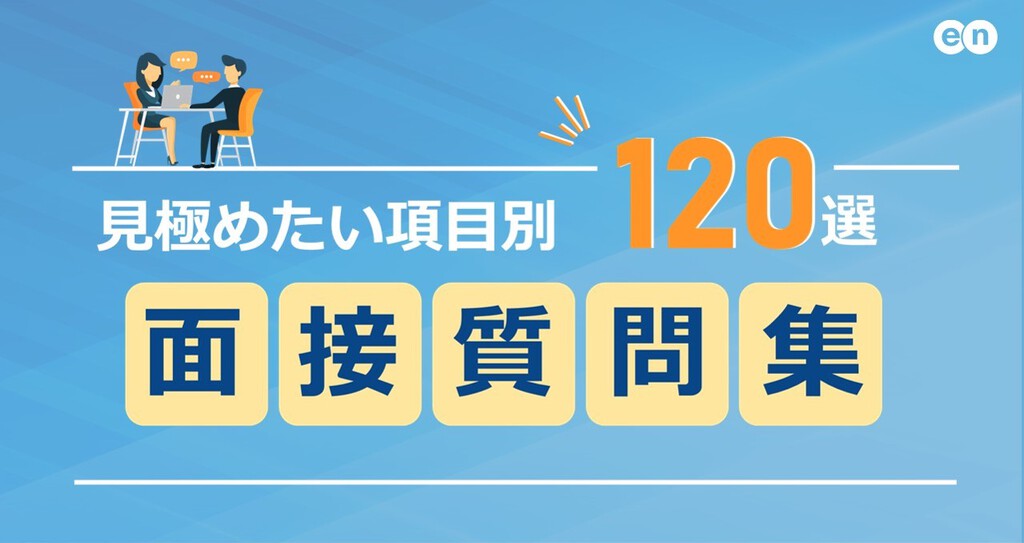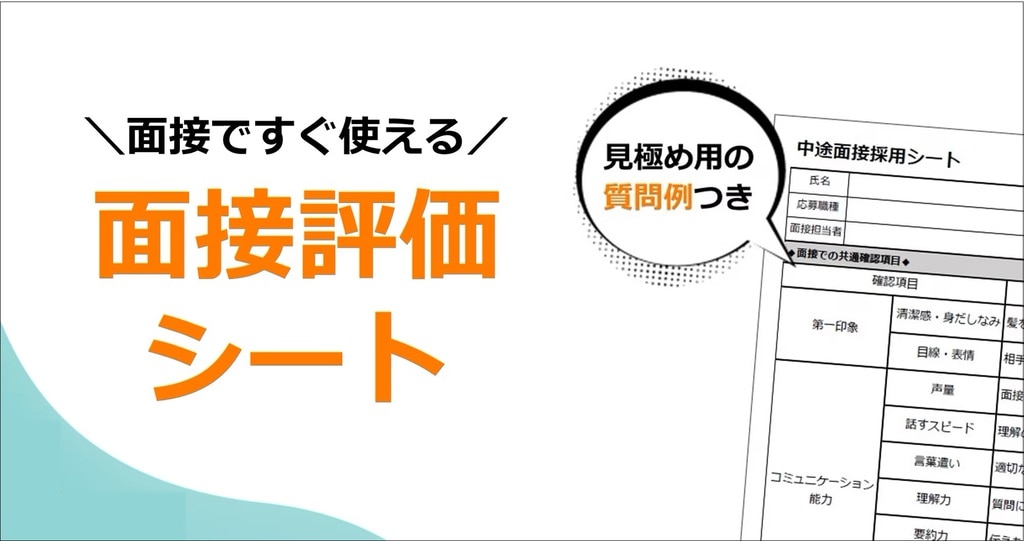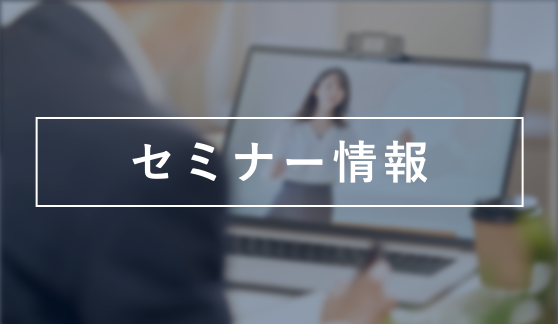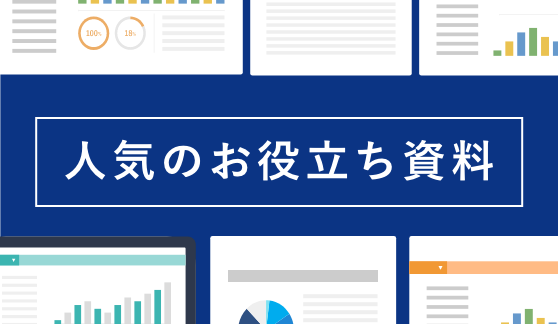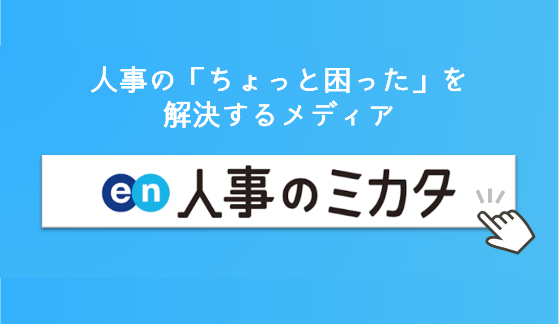個人事業主が人を雇うには? 雇用のメリットや助成金、採用手法も解説

個人事業主として働いている人が、業務過多などの理由により「従業員を雇いたい」と考えるケースは多いものです。本記事では、個人事業主が人を雇うために必要な手続きや、届け出などについて解説します。
また、個人事業主が人を雇うメリット・デメリットや雇用形態、活用できる助成金、採用手法なども紹介します。「個人事業主は従業員を雇えるの?」「雇うためには何をすればいいの?」とお困りの方は、ぜひ本記事をお役立てください。
※ なお、本記事で紹介する制度等の内容は、2025年2月時点のものです。最新の情報は、厚生労働省や国税庁、日本年金機構などのウェブページをご覧ください。
目次[非表示]
- 1.個人事業主が人を雇うときに必要な手続きと届け出
- 1.1.労働条件通知書の作成・交付
- 1.2.労働保険の加入手続き
- 1.3.社会保険の加入手続き
- 1.4.税務署への届け出
- 1.5.源泉徴収の準備
- 2.個人事業主が人を雇うメリット
- 2.1.雇用主の業務効率化につながる
- 2.2.事業拡大につながる可能性がある
- 2.3.家族への給与を経費計上できる場合がある
- 3.個人事業主が人を雇うデメリット
- 3.1.採用や雇用に関する手続きが生じる
- 3.2.保険料の負担が必要になる
- 4.個人事業主が人を雇うときの雇用形態・契約形態
- 4.1.正規雇用(正社員)
- 4.2.非正規雇用(パート・アルバイト等)
- 4.3.業務委託契約
- 5.従業員を雇う際に活用できる助成金・補助金
- 6.個人事業主が人を雇う際に便利な採用手法
- 6.1.ハローワーク(公共職業安定所)
- 6.2.求人検索エンジン
- 6.3.採用支援ツール
- 6.4.求人広告サイト
- 6.5.「個人事業主として人を雇う」「法人化して会社設立」どちらが良い?
- 7.まとめ
個人事業主が人を雇うときに必要な手続きと届け出
個人事業主が人を雇うときに必要な手続き・届け出には、以下の5つが挙げられます。
- 労働条件通知書の作成・交付
- 労働保険の加入手続き
- 社会保険の加入手続き
- 税務署への届け出
- 源泉徴収の準備
各手続き・届け出について、詳しく解説します。
労働条件通知書の作成・交付
労働条件通知書とは、名称の通り、従業員に労働条件を通知するための書類です。労働条件通知書には、主に以下のような内容を記載します。
- 賃金
- 契約期間
- 就業場所
- 業務内容
- 休憩時間
- 休日休暇
- 始業・終業の時刻
- 時間外労働の有無
- 退職に関する事項
- その他(社会保険の加入状況など)
厚生労働省が、労働条件通知書のひな形を作成していますので、ぜひ参考にしてください。
労働保険の加入手続き
労働保険とは、労災保険や雇用保険の総称です。業種や事業規模にかかわらず、従業員を雇う場合は、労働保険に加入する必要があります。
労災保険は原則として、事業主が従業員を1人でも雇用すると加入義務が生じます。労災保険には、パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず加入しなくてはなりません。
また雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、なおかつ31日以上の雇用の見込みがある労働者が加入対象となります。
参照:厚生労働省「事業主の行なう雇用保険の手続き」
社会保険の加入手続き
社会保険とは、健康保険や厚生年金保険の総称のことです。原則として、個人事業主が人を雇う場合は、従業員が5人以上になると社会保険の加入義務が生じます。(農林漁業やサービス業の一部などは除く)
この場合の「従業員」は、正規雇用労働者だけではありません。パート・アルバイトなどの非正規雇用労働者であっても、以下の条件に当てはまる場合は、社会保険の加入対象となります。
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者(正社員等)の4分の3以上である方は被保険者となります。
税務署への届け出
雇用主には、源泉徴収が義務づけられています。源泉徴収とは、給与から一定の所得税をあらかじめ天引きし、従業員本人の代わりに雇用主が税務署へ納付することです。
雇用主が源泉徴収を行なうためには、税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要があります。提出期限は開設・移転・廃止した日から1ヶ月以内です。国税庁のウェブページで、届出書様式をダウンロードできますのでご利用ください。
参照:国税庁「A2-7 給与支払事業所等の開設・移転・廃止の届出」
源泉徴収の準備
源泉徴収を行なうにあたり、給与から差し引く所得税額を計算したい場合は、国税庁のウェブページから「源泉徴収税額表」をダウンロードすると便利です。令和7年分の源泉徴収税額表が公開されていますので、ぜひお役立てください。
また、源泉徴収税額は、従業員の家族構成や家族の所得などによって異なります。従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を毎年記入・提出してもらい、税額を決定しましょう。こちらも令和7年分の給与所得者の扶養控除(異動)申告書が公開されていますので、ぜひご利用ください。
なお、源泉徴収した所得税は、原則として徴収した日の翌月10日までに納めなくてはなりません。しかし、従業員が10人未満の場合は、年2回にまとめて納付できる特例制度があります。特例制度を利用する場合は、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しましょう。
参照:国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
参照:国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
個人事業主が人を雇うメリット
ここからは、個人事業主が人を雇うメリット・デメリットを解説します。まずは、メリットを詳しく見ていきましょう。
雇用主の業務効率化につながる
個人事業主が従業員を雇うと、業務効率化につながります。一般的に、個人事業主は本業としての仕事だけでなく、企業ならば経理スタッフなどが担う事務作業も、すべて一人で行なわなくてはなりません。
休憩中や閉店後、休日中などの時間を割いて、事務作業を行なっている個人事業主も多いでしょう。このような状況の場合、事務担当の従業員を雇うことで、雇用主が本業に集中しやすくなります。
また、事務作業だけでなく、本業に関するさまざまな業務を従業員に手伝ってもらうことも可能です。結果、業務全体が効率化され、本業の利益向上につながる可能性があります。
事業拡大につながる可能性がある
前述の通り、個人事業主が従業員を雇うことで人手が増え、利益向上につながるケースがあります。業績が好調になれば、事業を拡大できるでしょう。
たとえば雇った従業員を、自分と同程度の仕事をこなせる程度まで育成すると、より多くの顧客に対応できるようになります。店舗の拡大や事業所の増設などにつながり、さらなる業績アップが期待できるでしょう。
家族への給与を経費計上できる場合がある
個人事業主が家族を従業員として雇う場合は、一定の条件を満たすことにより、家族への給与を経費計上できます。家族への給与を経費計上するための主な条件は、以下の通りです。
- 確定申告を「青色申告」で行なう
- 家族への給与を「青色事業専従者給与」として経費計上する
- 経費計上したい年の3月15日までに、税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する
なお、より詳細な条件については、国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」をご確認ください。
個人事業主が人を雇うデメリット
続いて、個人事業主が人を雇うデメリットを2つ解説します。
採用や雇用に関する手続きが生じる
個人事業主が従業員を雇うにあたり、さまざまな手続きや届け出が必要となります。税務署など公的機関への提出物には複数の種類があり、それぞれに期限もあるため、雇用主はしばらくの間、事務負担の増加で多忙になるでしょう。
また、採用活動にも多くの労力がかかります。ハローワーク等に求人を出したり、書類選考や面接を実施したりするなど、採用に関する業務を本業の合間に行なわなくてはなりません。無事に採用成功し、雇った従業員が一人前になるまでは、雇用主の業務負担が増えるでしょう。
保険料の負担が必要になる
個人事業主が従業員を雇用する場合、労働保険や社会保険に加入する必要があります。各保険への加入義務が生じた場合は、保険料を負担しなくてはなりません。
保険料の負担を減らしたい場合は、保険の加入義務が生じない範囲で、従業員を雇用する手もあります。労災保険は従業員を一人でも雇用すると、雇用形態に関係なく加入義務が生じますが、その他の保険は一定の条件を下回る場合に未加入が認められています。
なお、労働保険や社会保険の加入条件は、国によって適宜変更されることがあります。最新の情報を知りたい場合は、厚生労働省や日本年金機構などのウェブページを確認するとよいでしょう。
個人事業主が人を雇うときの雇用形態・契約形態
個人事業主が人を雇うときは、正規雇用・非正規雇用のどちらかの雇用形態を選ぶ必要があります。
また、雇用ではなく業務委託という形式で契約を結び、業務の一部を依頼するケースもあります。本章では、個人事業主が人を雇うときの雇用形態・契約形態について解説します。
正規雇用(正社員)
正規雇用とは、従業員を正社員として雇用することです。正規雇用は、期間の定めがない雇用形態であるため、従業員としては安定的に働けるメリットがあります。
一般的に、従業員を正規雇用する場合は、フルタイムで働いてもらうケースが多いでしょう。そのため雇用主には、労働保険や社会保険の負担義務が生じます。
非正規雇用(パート・アルバイト等)
非正規雇用とは、期間の定めがある雇用形態のことです。契約社員やパート・アルバイトなどが非正規雇用に該当します。
一般的に、正規雇用よりも非正規雇用のほうが、週当たりの労働時間が短くなる傾向があります。また、パート・アルバイトの場合は時間給であるため、雇用主が「社会保険の加入義務が生じない範囲で雇いたい」と考えている場合に適しています。
業務委託契約
業務委託とは、雇用契約を締結せずに、外部業者(または外部の個人)へ業務の一部を委託することです。業務委託を行なう場合は、労働保険や社会保険などの加入手続きが不要となります。
ただし、業務委託する相手は、あくまでも外部業者(または外部の個人)であるため、情報漏洩リスクなどに注意する必要があります。業務委託については、以下の記事でより詳しく解説していますので、「雇用だけでなく委託も検討したい」という方は、ぜひご覧ください。
▼業務委託とは? 請負契約・委任契約との違いやメリット、注意点などを紹介
従業員を雇う際に活用できる助成金・補助金
厚生労働省では、事業主が従業員を雇う際に使える助成金・補助金などの制度を設けています。個人事業主が人を雇う際、一定の条件を満たすことによって、活用できる可能性がある制度は以下の通りです。(2025年2月時点)
助成金・補助金の申請には、制度ごとにさまざまな要件が設けられています。詳しくは、厚生労働省が公開している各制度のウェブページをご確認いただくか、管轄の労働局へお問い合わせください。
なお、以下の記事では、特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金などについて、より詳しく紹介しています。ご興味のある方は、ぜひ本記事とあわせてご覧ください。
▼人材採用に活用できる4つの助成金。受給要件と申請方法は?
個人事業主が人を雇う際に便利な採用手法
ここからは、個人事業主が人を雇う際に便利な採用手法を4つ紹介します。
ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が運営する雇用サービス機関です。事業主側・求職者側ともに無料で利用できます。採用活動にコストをかけたくない場合は、活用するとよいでしょう。
ハローワークは窓口で職業紹介などを行なうイメージがありますが、近年はインターネットサービスも開始されています。ハローワークを利用して求人を出す方法は、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
▼ハローワーク求人の出し方|窓口・インターネットサービスでの手続きとコツ
求人検索エンジン
検索エンジンとは、GoogleやYahoo!のように、インターネット上の情報を検索・閲覧できる媒体のことです。求人検索エンジンは、求人情報に特化した検索エンジンを指します。求人検索エンジンの代表的なものには、以下のサービスが挙げられます。
- Indeed(インディード)
- Googleしごと検索
- 求人ボックス
- スタンバイ
基本的に、求人検索エンジンは、無料で求人を掲載できます。なかには「クリック課金」「応募課金」などの有料プランが設けられており、有料プランで利用すると、求人の露出量をアップできるケースもあります。
また、以下の記事では求人検索エンジンのように、無料で求人掲載できるサービスを17個紹介しています。採用活動に使える無料の媒体をもっと知りたいという方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
▼無料で求人掲載できるサービス17選!向いている企業や活用のコツも解説
採用支援ツール
採用支援ツールとは、事業主の求人募集をサポートする便利な機能が搭載された採用サービスのことです。無料で使える採用支援ツールには『engage(エンゲージ)』があります。
engageは、日本最大級の求人サイト『エン転職』でおなじみのエン・ジャパン株式会社が手掛けている採用支援ツールです。engageでは、以下のような基本機能を無料で使うことができます。
- 求人の作成・掲載
- 採用ページの作成
- 応募者の選考状況を管理
- 求職者へDM(ダイレクトメッセージ)を送付
- 求人検索エンジンと求人サイトに求人を同時掲載
engageを活用すると、採用業務の効率化につながります。engageの機能やメリット、プランなどについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
▼engage(エンゲージ)とは|求人掲載するメリット・プラン・手順など
求人広告サイト
求人広告サイトは、ひとつのプラットフォーム上に、さまざまな事業主の求人情報がまとめて掲載されている求人サービスのことです。求人サイトや転職サイトとも呼ばれています。
求職者はプラットフォーム上に掲載されている求人を、好みの条件で検索・閲覧できるほか、応募フォームから直接応募することも可能です。求人広告サイトで費用対効果が高い媒体には、エン・ジャパン株式会社が運営する『エン転職』が挙げられます。
エン転職は登録会員が豊富で、求人の閲覧率・応募率を高める工夫も多数施されているため、採用に成功しやすい媒体として、多くの方々から利用されています。詳しいサービス内容や特徴、料金プランなどは、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
▼エン転職とは?<2025年2月更新> サービス内容や特徴、料金などを解説
「個人事業主として人を雇う」「法人化して会社設立」どちらが良い?
「個人事業主として従業員を雇うのと、法人化して会社として従業員を雇うのは、どちらが良いのだろう?」とお考えの方も多いでしょう。両者のもっとも大きな違いは、所得税の計算方法であるため、どちらのパターンが良いかは業績により異なります。
個人事業主の場合は、累進課税が適用されているため、所得が増えるほど税金も段階的に増加していきます。法人は所得が増加しても税率が一定であるため、所得が多い場合は、法人化を検討するとよいでしょう。
ただし法人化するには、資本金の用意や法人登記の手続きなどが必要であるため、多くの費用と労力がかかります。また、決算書を年に1度作成するなど、財務面で事務負担が増える点にも考慮しなくてはなりません。
従業員を雇うにあたり、個人事業主と法人には、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。判断の目安としては、「売上1,000万円以上が継続している」「黒字が続いている」「さらなる事業拡大を目指している」という状況が重なったタイミングで、税理士などの専門家に相談したうえ、法人化を検討するのがおすすめです。
まとめ
個人事業主が人を雇うために必要な手続きや届け出、メリット・デメリット、採用手法などを解説しました。個人事業主が人を雇うときは、以下のような手続き・届け出を行なう必要があります。
- 労働条件通知書の作成・交付
- 労働保険の加入手続き
- 社会保険の加入手続き
- 税務署への届け出
- 源泉徴収の準備
雇用に関する法令は適宜改正されているため、最新情報を知りたいときは、厚生労働省や国税庁、日本年金機構などのウェブページを確認するか、管轄の労働局へ問い合わせるとよいでしょう。
なお、個人事業主・法人ともに採用活動を実施する際は、費用対効果の高いサービスを活用するのがおすすめです。「費用対効果の高いサービスを使い、採用成功率を上げたい」とお考えの方は、ぜひ『エン転職』にご相談ください。
エン転職は1,100万人以上の会員を保有する、日本最大級の中途採用向け求人サイトです。エン転職は、オリコンヒットチャートでお馴染み「オリコン顧客満足度調査」の「転職サイト部門」において、8年連続 総合満足度第1位を獲得しました(2025年時点)。
いま、もっとも求職者から選ばれている求人メディアだからこそ、専門職などの採用難易度が高い求人募集にもおすすめです。
また、エン転職の求人は「取材専門のディレクター」および「求人作成専門のコピーライター」によって、プロの手で作成されています。専門の担当者が、魅力的な求人原稿を作成しますので、求人を初めて出す方にも安心してご利用いただけます。
採用活動にお悩みがある方は、以下のエン転職お問い合わせ窓口より、ぜひお気軽にご相談ください。
▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。
ほかにも『エン転職』には採用を成功に導く様々な特徴があります。『エン転職』の料金表・パンフレットダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますのであわせてご覧ください。
▼エン転職のサービスページ