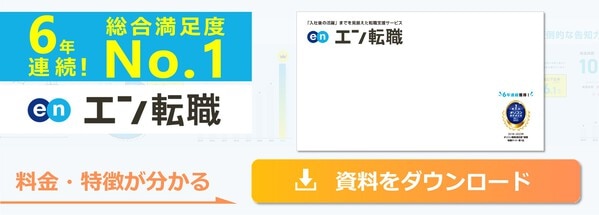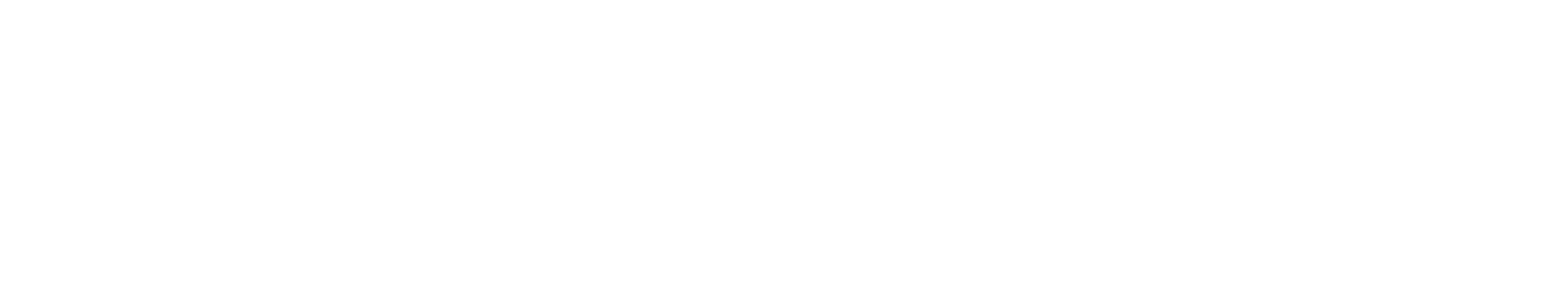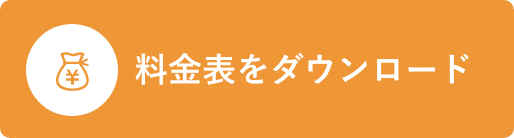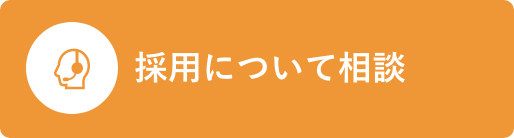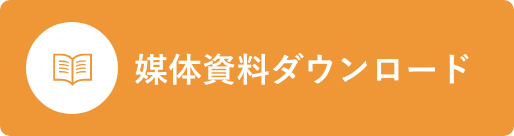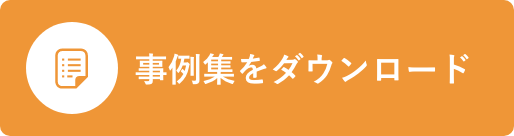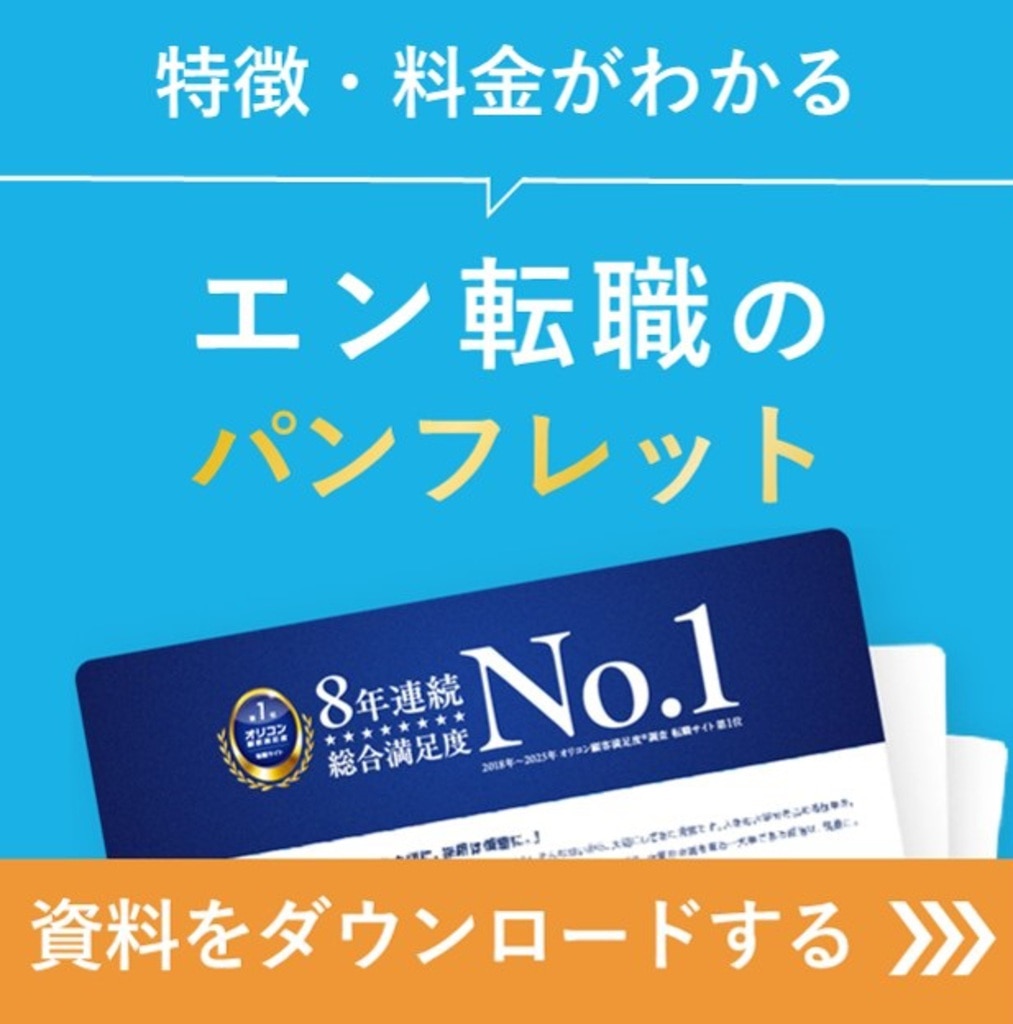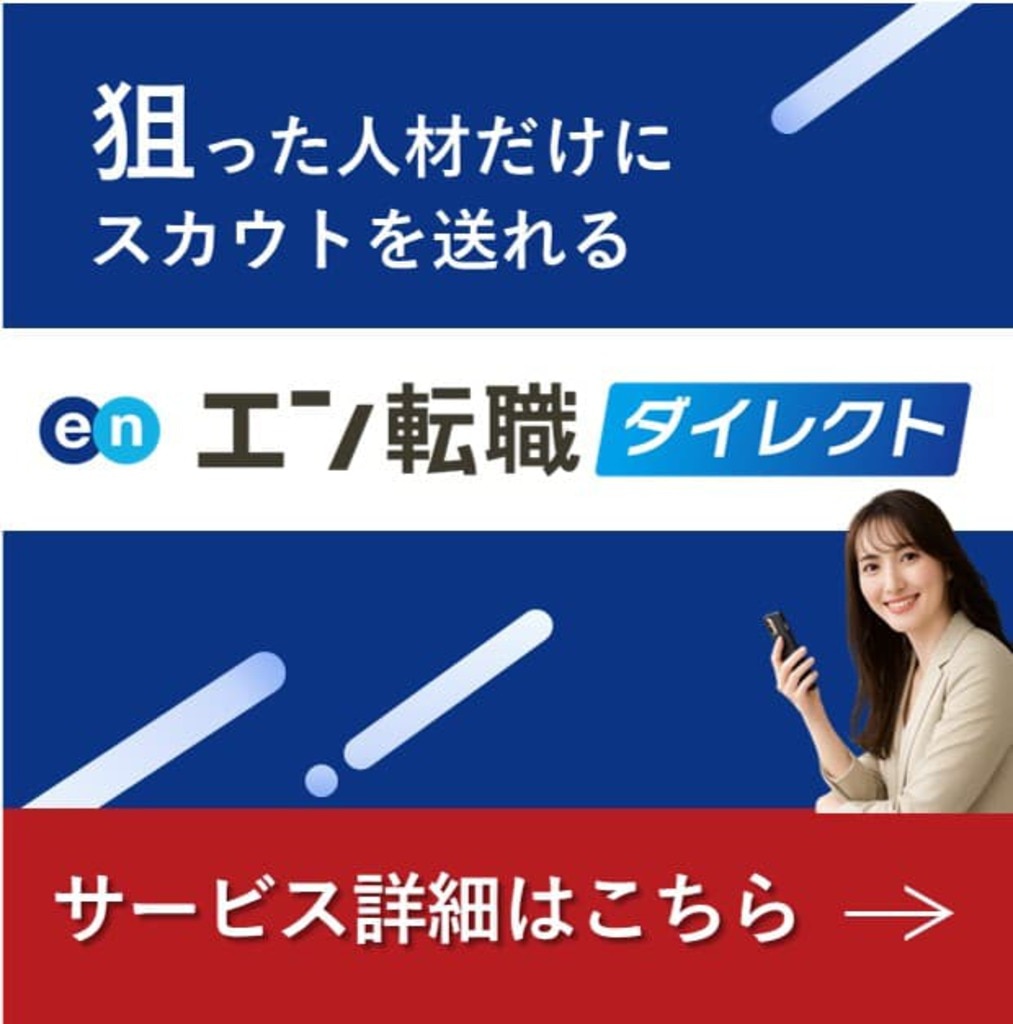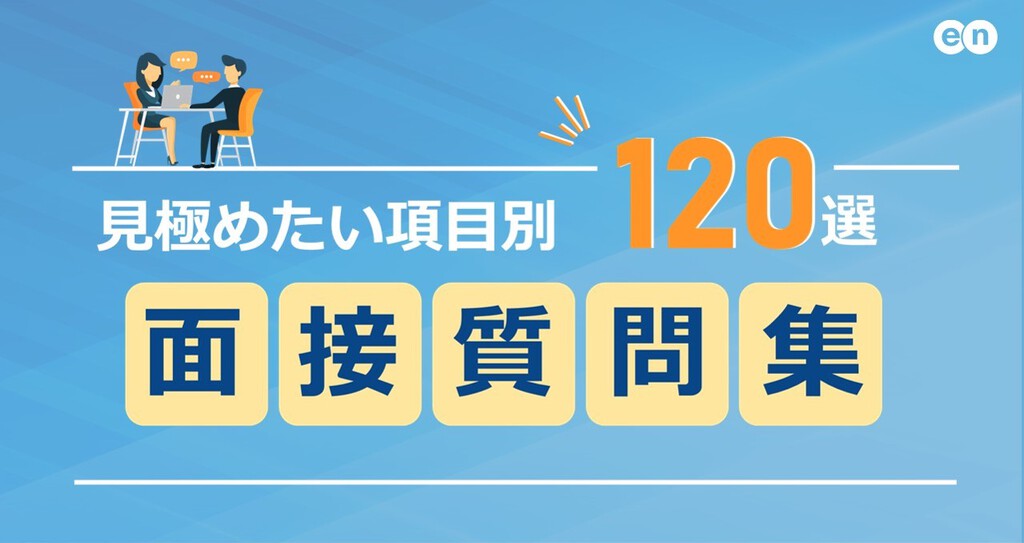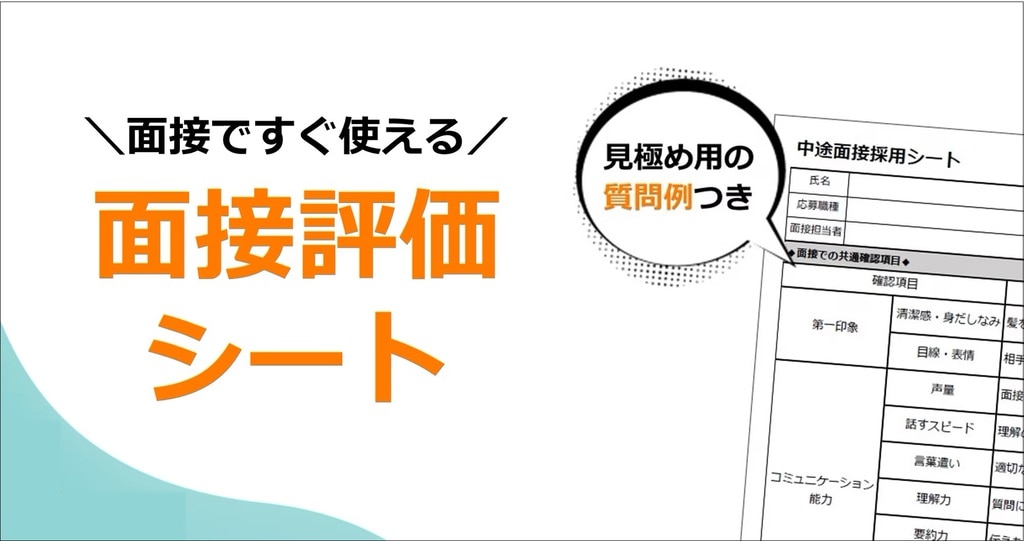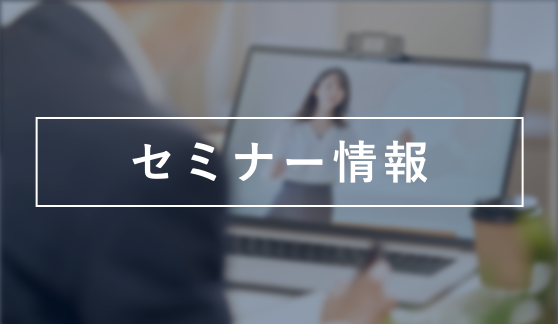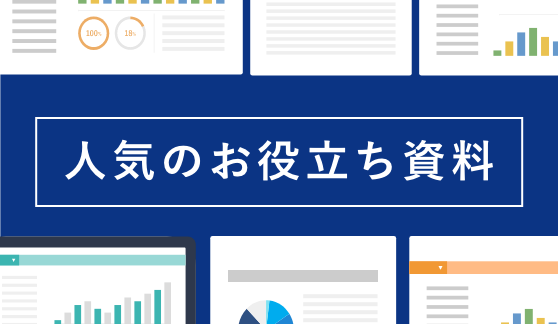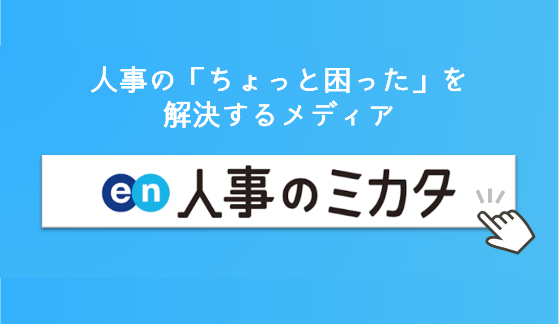業務委託とは? 請負契約・委任契約との違いやメリット、注意点などを紹介

人々の働き方が多様化している昨今。企業と人材が雇用関係を結ばずに仕事を発注・受注する「業務委託」に関心が高まっています。
本記事では業務委託について、契約の種類やメリット・デメリット、契約締結時の流れ、注意点などをご説明します。「即戦力となれる人材に仕事を頼みたい」「コストを抑えて人員を確保したい」など、業務委託を検討中の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
▼本記事をより分かりやすく解説した「業務委託| 契約のメリット・種類・注意点」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼
目次[非表示]
- 1.業務委託とは?
- 2.業務委託の契約の種類
- 3.業務委託を活用する企業が増えている背景
- 4.雇用契約・派遣契約との違い
- 5.業務委託のメリット
- 5.1.専門的な知識・経験のある人材が多い
- 5.2.雇用にともなうコストを削減できる
- 5.3.期間を限定して業務依頼できる
- 5.4.自社社員がコア業務に集中できる
- 6.業務委託のデメリット
- 6.1.情報漏洩リスクがある
- 6.2.自社にノウハウが蓄積されにくい
- 6.3.希望に合う人材を確保できない可能性がある
- 7.業務委託の契約を締結するときの流れ
- 8.業務委託契約書の内容と作成方法
- 8.1.業務委託契約書の主な記載事項
- 8.2.契約によっては収入印紙が必要
- 9.業務委託契約を解除する方法
- 9.1.契約書の内容を確認する
- 9.2.受託者と話し合いを行なう
- 9.3.契約解除合意書を作成して送付する
- 10.業務委託の契約を結ぶときの注意点
- 10.1.下請法に抵触しないよう注意する
- 10.2.偽装請負とならないよう注意する
- 10.3.業務の委託先は慎重に選ぶ
- 10.4.商品・サービスの品質が低下しないよう注意する
- 11.まとめ
業務委託とは?
業務委託とは、企業が雇用契約を結んでいない個人や、外部業者へ仕事を依頼すること。仕事を依頼した企業は、「成果物が契約通りに納品された」「依頼していた役務が遂行された」など、依頼内容が行なわれたことに対して報酬を支払います。
業務委託で仕事を依頼する際に、業務委託契約という言葉がよく使われますが、厳密に言うと法的に「業務委託契約」という契約方法が存在するわけではありません。
民法上の「請負契約・委任契約・準委任契約」という契約の総称が、一般的に「業務委託契約」と呼ばれるようになったのです。
業務委託の契約の種類
業務委託契約には「請負契約・委任契約・準委任契約」の3つがあります。各契約の支払いの条件などについて詳しく解説します。
請負契約
請負契約は、「企業が依頼した仕事を、請負人が完成・完遂させたら報酬を支払う」という契約です。たとえば、以下のような仕事内容が請負契約に含まれます。
- 会社のPRキャラクターのデザイン
- Webメディアの記事作成
- ホームページのロゴ作成
請負契約を結んで仕事を依頼した際に、「請負人が仕事を完成・完遂させられなかった」または「成果物に瑕疵があった」などの問題が生じた場合、仕事を依頼した側には請負人に修正をお願いしたり、契約解除したりできる権利があります。
委任契約
委任契約は請負契約と異なり、依頼内容の完成・完遂を報酬支払いの基準としません。委任契約の場合は、「業務の遂行自体」に報酬を支払います。
たとえば「9時~17時まで記事を作成する」という依頼内容の場合、請負契約では請負人が記事を完成させたら報酬を支払います。しかし委任契約では、「9時~17時まで記事を作成するために作業したこと」に対して報酬を支払うのです。
また委任契約は、依頼する仕事内容が法律行為に該当する場合に適用されます。たとえば以下のような仕事が該当します。
- 税理士に税務関係の書類作成を依頼する
- 弁護士に裁判のための手続きを依頼する
準委任契約
準委任契約も委任契約と同様、「業務の遂行自体」に報酬を支払います。委任契約と違うところは、準委任契約の場合、「依頼する仕事内容が法律行為に該当しない」という点です。たとえば以下のような仕事依頼が、準委任契約に該当します。
- コンサルタントに企業分析を依頼する
- 外部業者に店舗のレジシステムの保守点検を依頼する
依頼する仕事内容が法律行為に該当する場合は委任契約、該当しない場合は準委任契約であると覚えておきましょう。
業務委託を活用する企業が増えている背景
業務委託を活用すれば、採用や育成にコストをかけることなく、即戦力人材に業務を外注できるようになります。
また「繁忙期だけ業務を委託し、落ち着いたら委託先との契約を解除する」といった柔軟な発注も可能なので、時期による業務量の増減に対応しやすくなります。こうしたメリットにより、近年は業務委託を活用する企業が増加しています。
主に経理事務や営業事務、労務管理などのバックオフィス業務や、定型のルーティンワークを中心に業務委託を活用する企業が多くなっています。
雇用契約・派遣契約との違い
業務委託と雇用契約・派遣契約の違いを解説します。業務委託・雇用契約・派遣契約の大まかな違いを以下の表にまとめましたので、参考にしてください。
業務委託 |
雇用契約 |
派遣契約 |
|
雇用主 |
なし |
就業する会社 |
人材派遣会社 |
報酬の対象 |
成果物の納品 業務の実施 |
労働力 |
労働力 |
依頼主の指揮命令権 |
なし |
あり |
あり |
勤務時間・勤務場所の指定 |
なし |
あり |
あり |
社会保険の加入義務 |
なし |
就業する会社で加入 |
人材派遣会社で加入 |
雇用契約(正社員・契約社員・パート・アルバイト)との違い
雇用契約とは、企業が人材を直接雇用する契約のこと。企業の正社員やパート・アルバイトなどが雇用契約に該当します。
雇用契約と業務委託のもっとも大きな違いは、「指揮命令権があるかどうか」「労働法が適用されるかどうか」です。雇用契約の場合は、人材を雇用する企業に指揮命令権があります。
また雇用される人材は、労働力を提供する代わりに労働法で守られており、雇用主による福利厚生制度などの待遇を受けられます。
業務委託の場合、業務の発注側に指揮命令権はありません。発注側と受注側は、あくまでも対等な関係です。個人事業主の場合は労働法も適用されないため、受注側は自身で休日を管理したり、労災へ備えたりする必要があります。
派遣契約(派遣社員)との違い
派遣契約は業務を依頼したい企業が、人材を派遣してくれる派遣会社と労働者派遣契約を結びます。労働者派遣契約が結ばれ次第、人材派遣会社から派遣されたスタッフが依頼企業へ出向き、業務をこなすという流れです。
派遣契約の場合は、依頼企業が派遣スタッフに対して指揮命令権をもちます。業務委託では、依頼側に指揮命令権がないので、この「指揮命令権があるかどうか」が大きな違いとなります。
また派遣契約では、依頼企業が派遣スタッフの就業場所・就業時間などを定めることができます。しかし、派遣スタッフと雇用関係を結んでいるのは、あくまでも人材派遣会社です。そのため、依頼企業が派遣スタッフを社会保険に加入させる必要はありません。
業務委託のメリット
企業が業務委託を活用するメリットを3つ紹介します。導入を検討する際、念頭に置いておくとよいでしょう。
専門的な知識・経験のある人材が多い
業務委託で仕事を請け負う業者や個人事業主などには、専門的な知識・経験を保有する人材が多くいます。即戦力となれるノウハウ・技術をもった人材に仕事を依頼したい場合や、急ぎの仕事を依頼したい場合などに頼もしい存在となるでしょう。
複数の事業者を比べて、より費用対効果が高そうな委託先を見極められると、コストを抑えながら高い成果を得られる可能性もあります。
雇用にともなうコストを削減できる
業務委託には、雇用にともなうコストを削減できるメリットもあります。自社で新たな社員を雇用するときにかかるお金は、給与だけではありません。
社会保険料や労務管理費、労働環境の整備費、仕事に必要な備品の購入費など、多数の費用がかかります。しかし、業務委託で仕事を依頼するのであれば、こういった雇用にともなうコストは不要となるのです。
また先にも述べた通り、業務委託で仕事を請け負う業者や個人事業主には、業務遂行に必要な知識・技術をすでにもっている人材が多くいます。そのため、人材の教育コストも削減可能となります。
期間を限定して業務依頼できる
繁忙期など仕事が忙しい時期に合わせて、必要な人員を確保しやすい点も、業務委託のメリットです。人材を通年で雇用するのが難しい企業であっても、業務委託ならば人手が必要な時期だけに限定して仕事を依頼できます。人件費を削減しつつ、既存社員の業務負担を軽減させられるでしょう。
自社社員がコア業務に集中できる
事務作業などの定型業務を外部へ委託することで、自社の社員がコア業務に集中できるようになります。自社の社員が定型業務から解放され、コア業務に専念できるようになれば、会社の業績アップにつながるでしょう。
業務委託のデメリット
企業が業務委託を活用するデメリットを3つ紹介します。メリット・デメリットをどちらも把握したうえで、活用すべきか検討するとよいでしょう。
情報漏洩リスクがある
業務委託には、情報漏洩リスクがあると忘れてはいけません。業務委託をするということは、「自社で行なう仕事の一部を他事業者へ依頼する」ということ。依頼する内容によっては、自社の顧客情報や商品・サービスの機密情報などを業務委託先へ提供するケースもあるでしょう。
重要な情報が漏洩しないよう、業務委託先は慎重に選ぶ必要があります。業務委託先の情報セキュリティシステムのレベルや、情報保護への取り組み体制を契約前にチェックしておきましょう。
自社にノウハウが蓄積されにくい
先にも述べたように、業務委託のメリットには「専門的知識・経験を保有した、即戦力となれる人材を確保しやすい」という点が挙げられます。しかし逆に言えば、業務委託に頼りすぎてしまうと、業務のノウハウが自社に蓄積されにくくなる恐れがあるのです。
長期的に仕事を依頼して頼りきっていた業務委託先が、突然廃業してしまったり、何らかの理由で自社の仕事を引き受けてくれなくなったりするリスクもあります。長期的な依頼が発生する仕事や、重要度の高い仕事などは、人材を直接雇用する方がよいでしょう。
希望に合う人材を確保できない可能性がある
業務委託には「時期を限定して仕事を任せられる」「複数の事業者から委託先を選べる」などのメリットがあります。しかし人材の流動性が高いゆえに、タイミングによっては希望に合う人材を確保できない可能性もあるのです。
ハイパフォーマンスな人材を求める場合や、難易度の高い業務を依頼したい場合は、スケジュールに余裕をもって委託先を探しましょう。
業務委託の契約を締結するときの流れ
業務委託の契約を締結するときの流れを解説します。下記はあくまでも一般的な例です。企業や業務内容によって、流れは多少異なります。
- 外部へ委託したい業務内容・期間・報酬金額などを決定
- 求人サイトなどで条件を公開し、業務委託先を募集
- 業務委託先の候補となる事業者と契約交渉
- 交渉がまとまったら業務委託の契約書を作成
- 必要に応じて契約書の内容を修正
- 双方の合意がとれたら契約締結
業務委託の契約は、一般的に上記のような流れで締結されます。
報酬や業務範囲などの契約内容は、双方の合意がとれるまで条件をすり合わせる必要があるため、契約書を作成したのちに修正が入るケースも多くあります。確認不足であとから揉めることのないよう、入念にすり合わせましょう。
業務委託を契約するときは、不要なトラブルを避けるためにも発注側・受注側の双方がきちんと連絡を取りあい、密にコミュニケーションをとって契約を進めることが大切です。
業務委託契約書の内容と作成方法
続いて、業務委託契約書の主な内容と、作成方法について解説します。業務委託契約書を受託者としっかり取り交わし、トラブルがないようにしましょう。
業務委託契約書の主な記載事項
業務委託の契約書を作成するときは、下記の項目を最低限含むようにしましょう。
項目 |
概要・注意点など |
委託する業務内容 |
業務内容・業務範囲を詳細に記載する |
報酬金額 |
業務の報酬金額・支払方法 支払のタイミング 各手数料はどちら負担か 業務遂行にかかる諸費用はどちら負担か |
契約期間 |
業務委託の契約期間を記載する |
指揮命令権の所在 |
指揮命令権は受注側にあると明記する ※指揮命令権が発注側にあると、労働者派遣契約とみなされるため |
権利の帰属 |
制作物の著作権・知的財産権などの帰属を記載する |
納品物の修正 |
納品物の修正回数・修正範囲などを詳細に記載する |
損害賠償の範囲 |
損害賠償が発生した際の賠償範囲・補償範囲について記載する ※賠償金額の限度額・補償する損害の種類など |
契約の解除事由 |
受注側の業務に問題があったとき、途中で契約解除できるよう解除事由を明記する |
情報の取り扱い |
業務上やりとりする情報の取り扱いについて明記する |
業務委託の契約書は、企業によって内容が異なります。委託したい業務によっても定めるべき内容が変動するため、自社だけで契約書を作成するのが不安な場合は、労働契約に詳しい弁護士や行政書士を頼るとよいでしょう。
契約によっては収入印紙が必要
収入印紙とは、租税・手数料・その他の収納金徴収のために、政府が発行している証票のことです。業務委託は契約の内容によって、収入印紙が必要となります。
紙媒体の業務委託契約書を作成する際、契約期間が3ヶ月以上の長期になる場合は、4,000円分の収入印紙を用意する必要があります。
ただし、パソコンやスマートフォンなどのデバイスを使って電子契約を結ぶ場合は、収入印紙の添付が不要です。また、契約の種類が請負契約ではなく、委任契約に分類される場合も、収入印紙が不要となります。
業務委託契約を解除する方法
「受託者に問題があった」「委託したい業務が完了した」などの理由で、業務委託契約を解除するケースがあります。ここでは、業務委託契約を解除する場合について、大まかな手順を解説します。
契約書の内容を確認する
業務委託の契約を解除するときは、委託を開始する際に取り交わした業務委託契約書の「解除事由」などに記載した内容に則って、解除手続きを進めましょう。
基本的には、委任契約(準委任契約)であれば、委託者と受託者の双方が、自由に契約解除を申し出られます。ただし、契約形態が請負契約だった場合は、成果物の納品が完了していない限り、解除を申し出ることができないため注意が必要です。
請負契約においては、成果物の納品が完了していないタイミングで解除を申し出ると、その申し出自体が契約違反となってしまう可能性があります。業務委託契約を解除したいときは、委託の際に取り決めた契約形態と、解除事由を重点的に確認しましょう。
受託者と話し合いを行なう
必要に応じて、受託者と委託者で話し合いの場を設けます。契約解除の理由やタイミングなどを、誠意をもってきちんと受託者へ話し、できる限り円満に業務委託契約を終了できるようにしましょう。
委託側が短期間で強引に契約解除しようとすると、訴訟トラブルに発展する可能性があります。円満に契約解除できるよう、解除の申し出も含めて、スケジュールには余裕をもちましょう。
契約解除合意書を作成して送付する
受託者と契約解除について合意できたら、業務委託の契約解除合意書を作成します。委託者から受託者へ契約解除合意書を送付し、双方が署名捺印したら保管しましょう。
業務委託の契約を結ぶときの注意点
業務委託の契約を締結するときは、法律に抵触しないよう注意しなくてはなりません。下請法に抵触したり、偽装請負とみなされたりすることがないよう気を付けましょう。
下請法に抵触しないよう注意する
業務委託をするときは、下請法(下請代金支払遅延等防止法)に抵触しないよう注意しましょう。下請法は親事業者(業務委託の発注者)が、下請事業者に対して買いたたきなどの理不尽な対応をしないよう定めた法律です。
下請法は公正取引委員会によって、対象となる取引が下記のように定められています。親事業者→下請事業者の各資本金規模が、矢印の向きで該当する場合、下請法の対象となります。
① 物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物・役務提供委託を行なう場合
親事業者 → |
下請事業者 |
資本金3億円超 → |
資本金3億円以下(個人を含む) |
資本金1千万円超3億円以下 → |
資本金1千万円以下(個人を含む) |
② 情報成果物作成・役務提供委託を行なう場合(①の情報成果物・役務提供委託を除く)
親事業者 → |
下請事業者 |
資本金5千万円超 → |
資本金5千万円以下(個人を含む) |
資本金1千万円超5千万円以下 → |
資本金1千万円以下(個人を含む) |
親事業者→下請事業者の各資本規模が上記の表に該当する場合、下請法が適用されます。下請法の対象となる取引において、親事業者には以下の行為が義務または禁止とされているので注意しましょう。
義務 |
|
禁止事項(4条) |
|
偽装請負とならないよう注意する
「偽装請負」とは、契約書上は業務委託であるものの、実際の働き方が労働者派遣と同様になっている違法状態を指す言葉です。業務委託の発注者側が、受注者を指揮管理すると、偽装請負とみなされ罰則の対象となってしまいます。
厚生労働省は、偽装請負の代表的なパターンについて、以下のように定めています。該当の違法行為をしないよう注意が必要です。
<代表型>
請負と言いながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしています。偽装請負によく見られるパターンです。
<形式だけ責任者型>
現場には形式的に責任者を置いていますが、その責任者は、発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が指示をしているのと実態は同じです。単純な業務に多いパターンです。
<使用者不明型>
業者Aが業者Bに仕事を発注し、Bは別の業者Cに請けた仕事をそのまま出します。Cに雇用されている労働者がAの現場に行って、AやBの指示によって仕事をします。一体誰に雇われているのかよく分からないというパターンです。
<一人請負型>
発注者と受託者の関係を請負契約と偽装した上、更に受託者と労働者の雇用契約も個人事業主という請負契約で偽装し、実態としては、発注者の指示を受けて働いているというパターンです。
引用:厚生労働省「あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ?」
業務の委託先は慎重に選ぶ
自社の業務を外部業者へ委託するときは、委託先を慎重に選びましょう。特に請負契約の場合は、基本的に委託先から成果物が納品されるまで、進捗を確認できないことがほとんどです。
悪質な業者と契約すると、「納期を守ってもらえない」「成果物に瑕疵がある」「修正の希望を出しても対応してもらえない」などのトラブルが生じてしまう可能性があるので注意しましょう。
商品・サービスの品質が低下しないよう注意する
業務委託の契約先は、あくまでも外部の業者です。自社で研修や教育を受けた社員ではないため、委託時にきちんと業務マニュアルや業務ルールを共有しないと商品・サービスの品質が低下する可能性があります。
委託先が一定の品質を保って業務をこなせるように、わかりやすいマニュアルを作成しておきましょう。また、業務委託したからといって任せきりにせず、委託先と定期的にミーティングを実施するのも効果的です。
ミーティングで業務の疑問点や、困っていることなどをヒアリングし、解消できるように工夫すれば、品質担保につながります。定期的にコミュニケーションをとったほうが、委託先も安心して仕事に取り組めるでしょう。
まとめ
業務委託とは、企業が雇用契約を結んでいない個人や、外部業者へ仕事を依頼すること。業務委託には請負契約・委任契約・準委任契約の3種類があり、それぞれ支払いのタイミングや依頼内容などが異なります。
業務委託を活用するメリットは、「コストを抑えつつ専門的知識・経験のある人材に仕事を任せられる」「期間を限定して仕事を依頼できる」などです。
対して業務委託のデメリットには「情報漏洩リスクがある」「自社に仕事のノウハウ・技術が蓄積されにくい」などが挙げられます。業務委託にするべきか否かは、任せたい業務の重要度や期間によって決めるとよいでしょう。
また、業務委託を募集するにあたり、契約内容にさまざまな注意点があります。求人の書き方も一般的な求人広告とは異なるため、ある程度は法律などの知識が必要です。
「業務委託をしたいけど、自社だけで進めるのは不安…」「そもそもどうやって募集すればいいの?」とお悩みの方は、ぜひ『エン転職』にご相談ください。
『エン転職』は1000万人以上の会員を保有する、日本最大級の中途採用向け求人サイトです。業務委託の募集も可能で、これまでに多くの募集実績があります。
難しい求人作成を採用のプロに任せられるので、初めて業務委託を募集する方にも安心してご利用いただけます。求人募集にお悩みのある方は、以下のエン転職お問い合わせ窓口より、お気軽にご相談ください。
▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。
他にもエン転職には採用を成功に導く様々な特徴があります。エン転職の料金表・パンフレットダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますので合わせてご覧ください。
▼エン転職のサービス紹介サイト
▼本記事をより分かりやすく解説した「業務委託| 契約のメリット・種類・注意点」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼