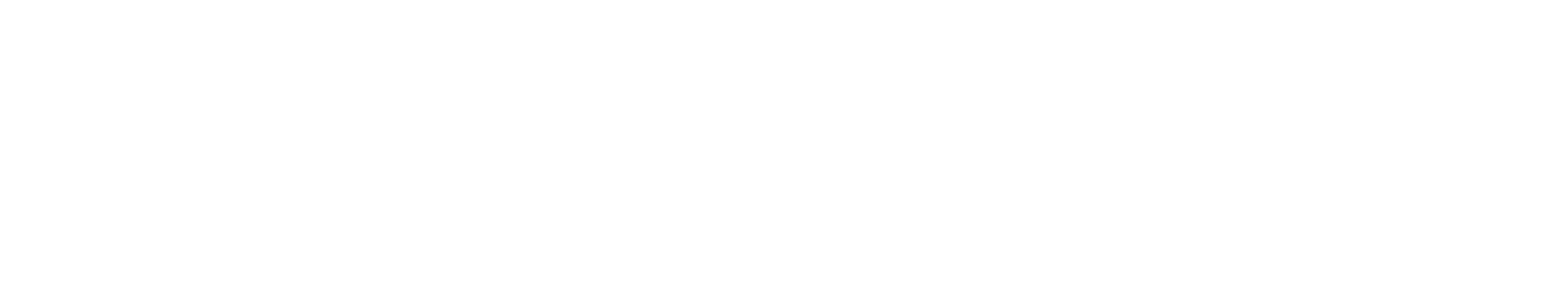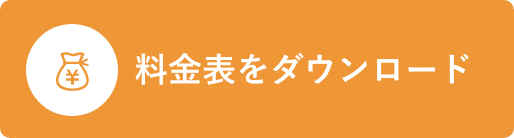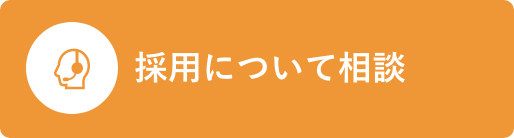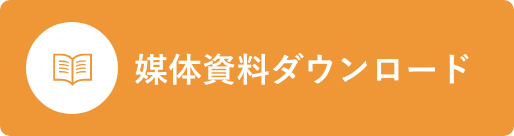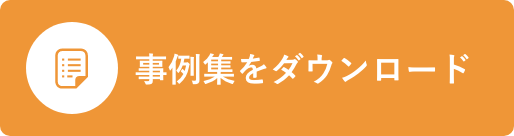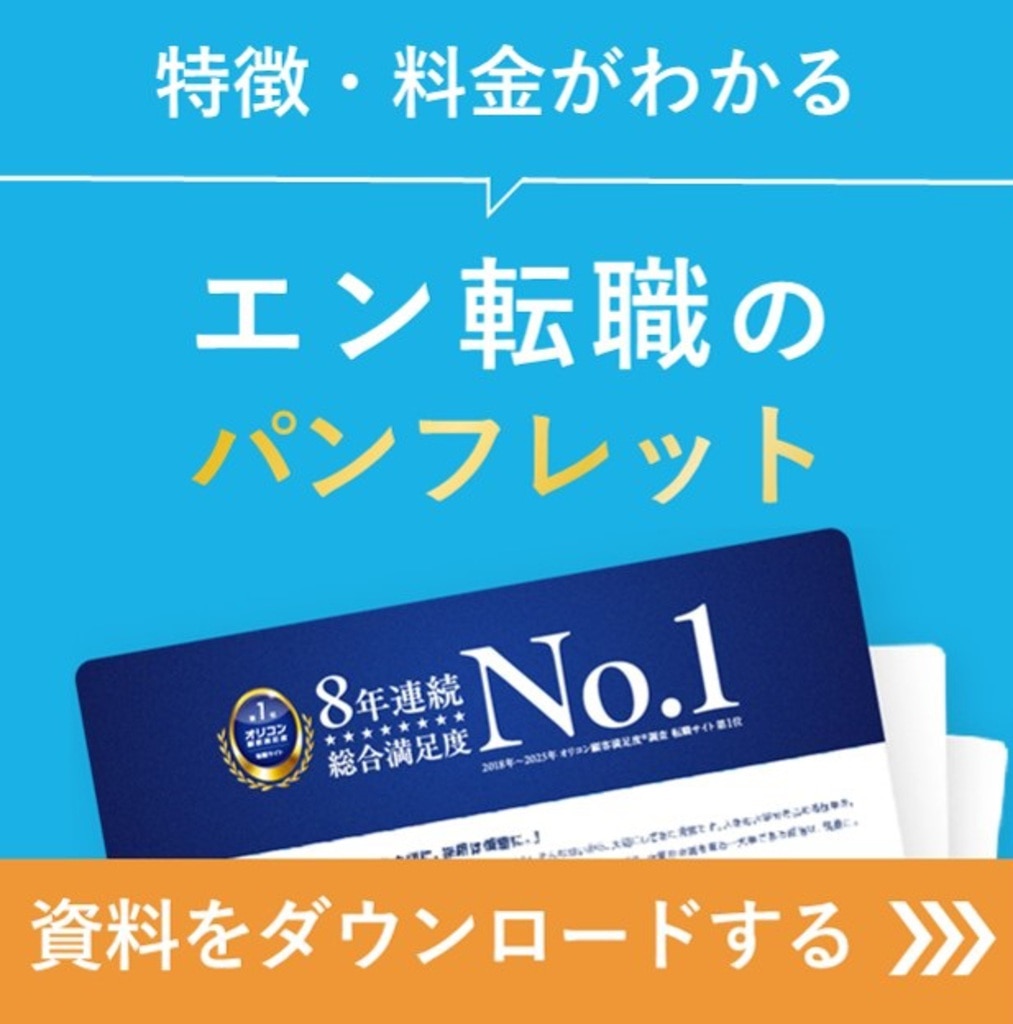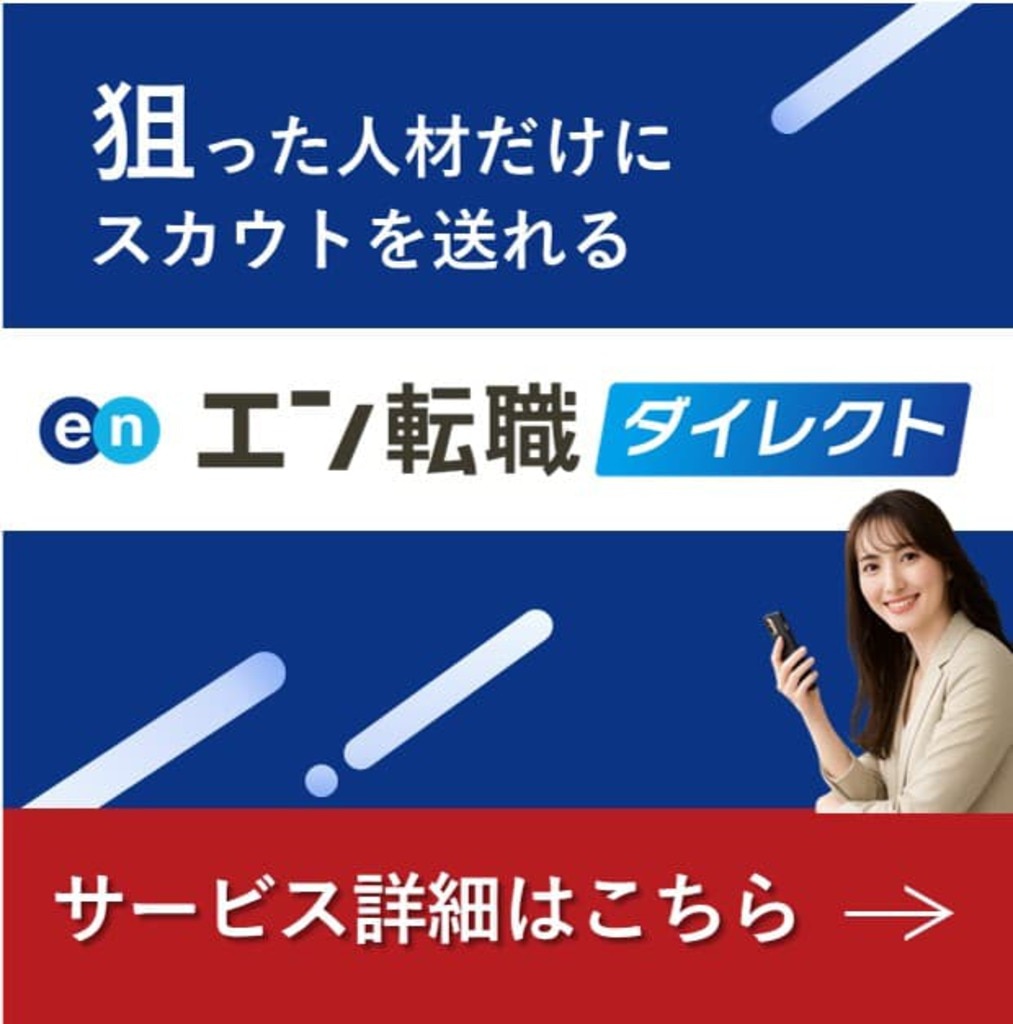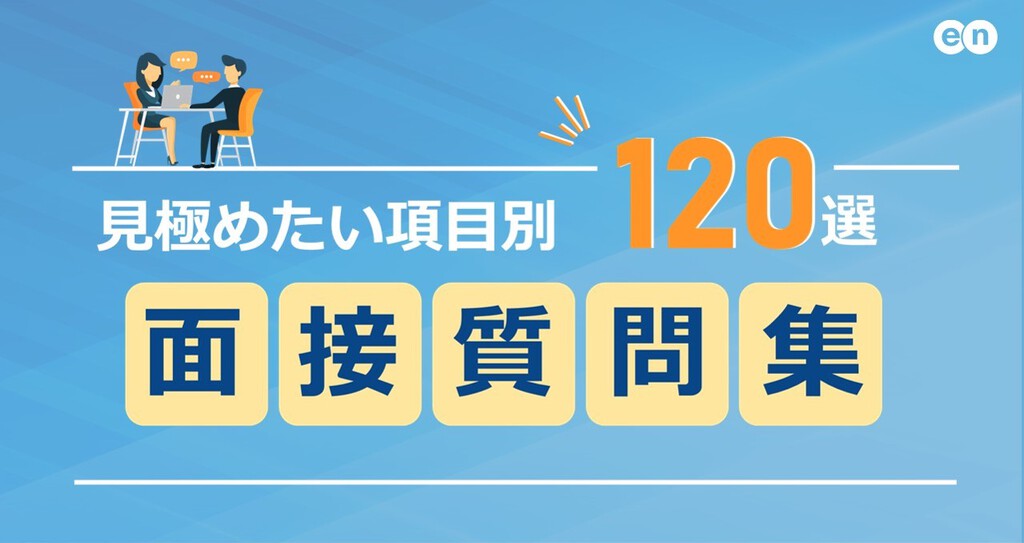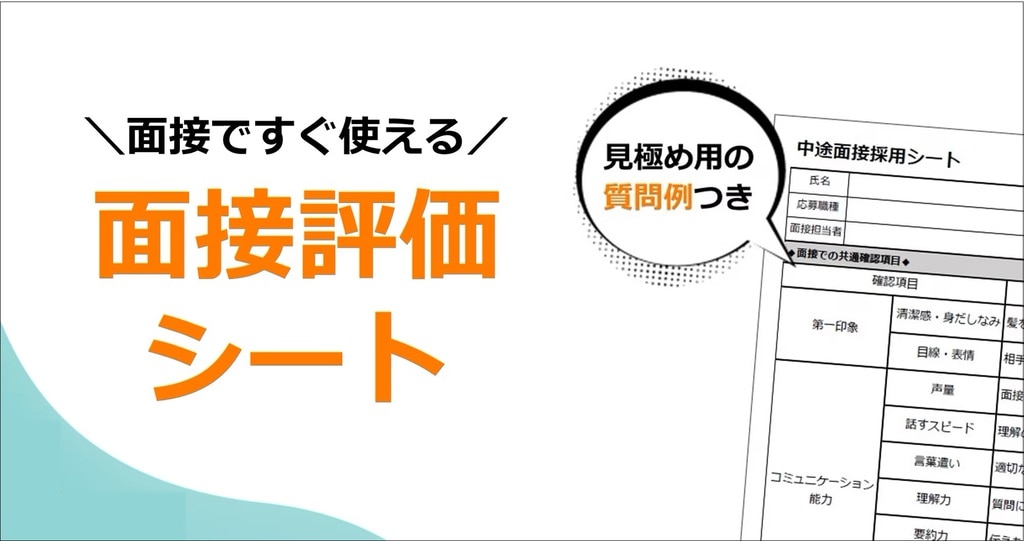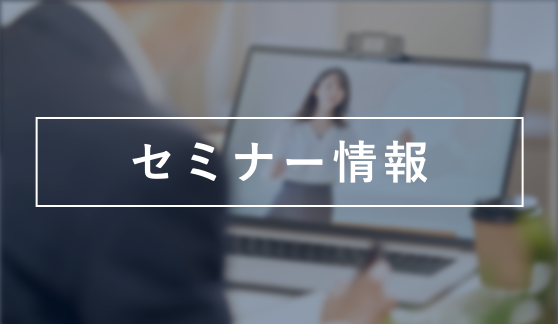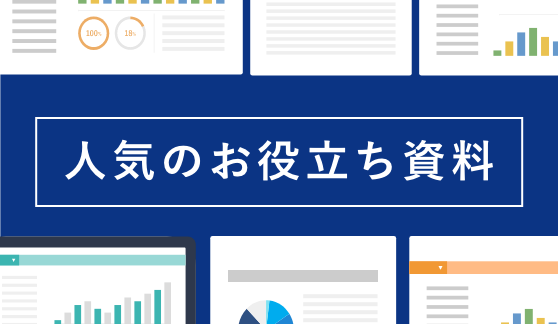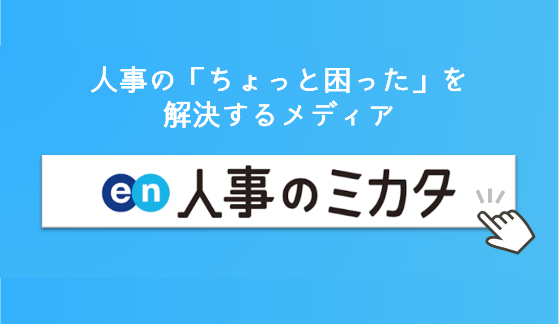ダイレクトリクルーティングとは?他の手法との比較や中途採用に有効な理由

求職者からの応募を待つ従来の採用方法とは異なり、企業から求職者に対して直接アプローチする“ダイレクトリクルーティング”が注目を集めています。大きなメリットとして即戦力となる人材を発掘しやすいことが挙げられ、中途採用で有効活用されています。
中途採用にダイレクトリクルーティングを導入しようと検討している人事・採用担当者のなかには、「中途採用で導入する理由はなんだろう」「どのような流れで行えばよいのだろう」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
この記事では、ダイレクトリクルーティングが中途採用に有効な理由や注意点、実施の流れについて解説します。
なお、ダイレクトリクルーティングの概要については、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
目次[非表示]
ダイレクトリクルーティングとは?
ダイレクトリクルーティングとは、企業が「欲しい人材」に対して、スカウトメールなどを用いて直接アプローチする攻めの採用手法です。
ダイレクトリクルーティングには多くのサービスがありますが、一般的にはサービスの提供会社が保有する人材データベースに、サービスを利用する会社が直接アクセスし、登録されている人材の経歴を見てスカウトする方法が一般的です。
人材の経歴を確認したうえでスカウトできるため、特定の業務に精通した人材や、特定の資格を有している人材、マネジメント経験者、即戦力人材などを確保するのに適した採用方法といえます。
ダイレクトリクルーティングが注目される背景
近年、ダイレクトリクルーティングは多くの企業から注目されており、実際に活用する企業も増えてきています。その背景には、少子高齢化による労働人口減少などの影響で、採用難易度が上昇し、企業間の人材獲得競争が激化していることが挙げられるでしょう。
膨大な求人に埋もれて、求職者に求人を見つけもらいづらくなっています。応募が集まりづらくなり、採用が決まらない求人は残り続けることに。結果、より求人が埋もれやすくなっていくという悪循環が生まれています。
特に「専門的スキルや知識を有する人材」「マネジメント経験のある人材」「特定の業務の経験が豊富な人材」などのハイスキルな人材は、採用するのが年々難しくなっています。
このような状況のなかで、自社に適した優秀な人材を採用する方法のひとつとして、人材の経歴を確認したうえで企業側から直接アプローチできるダイレクトリクルーティングが活用されるようになっているのです。
中途採用の代表的な手法との比較
中途採用には「転職サイトでの求人掲載・転職イベント・転職エージェントサービス・リファラル採用」など、さまざまな手法があります。ダイレクトリクルーティングと、その他の代表的な中途採用手法を以下の表にまとめましたので、比較の参考にしてください。
▼中途採用の手法例
種類 |
詳細 |
転職サイト |
さまざまな企業の求人広告が掲載されているWebサイトを利用する手法 |
転職イベント |
企業が求職者とコミュニケーションを図れるイベントに参加する手法 |
自社の採用サイト |
自社で運営する中途採用向けのオウンドメディアで情報を発信する手法 |
公共職業安定所 (ハローワーク) |
求職者・事業主を無償で雇用支援を行う総合的雇用サービス機関を利用する手法 |
転職エージェントサービス |
自社が求める人材に合う求職者を紹介してもらえるサービスを利用する手法 |
リファラル採用 |
自社の従業員から友人・知人を紹介してもらう手法 |
ダイレクトリクルーティング |
企業から求職者に対して直接アプローチできる手法 |
上記で紹介した手法は、基本的に求職者からの応募を待ちます。しかし、7種類のなかでダイレクトリクルーティングが唯一「企業から求職者へアプローチできる」という強みがあり、特に中途採用に有効だといわれています。
ダイレクトリクルーティングのメリット
ダイレクトリクルーティングの主なメリットには、以下の4つが挙げられます。
- 転職潜在層にアプローチしやすい
- 経験やスキルが豊富な人材を採用しやすい
- 使いこなせば採用コストを抑えられる
- 自社に採用ノウハウが蓄積される
ダイレクトリクルーティングは「転職を検討しているものの、求人に応募するなど具体的な行動には移せていない」という転職潜在層に直接アプローチしやすい採用方法です。
人材データベースを確認し、経歴をチェックしてからアプローチできるため、スキルや業務経験が豊富な人材に、効率よく自社をアピールすることも可能となります。
また、ダイレクトリクルーティングの費用相場は、一般的な人材紹介サービスなどに比べて安価であるため、サービスを使いこなせば採用活動にかかるコストを削減できます。
ダイレクトリクルーティングを進めるにあたり、スカウトメールなどを作成する手間はかかりますが、その分、採用活動のノウハウが自社にストックされやすくなるでしょう。
ダイレクトリクルーティングのデメリット
ダイレクトリクルーティングの主なデメリットには、以下の3つが挙げられます。
- 採用担当者の業務負担が増える
- 成果を出すためにはノウハウが必要
- 短期的な採用活動には向いていない
ダイレクトリクルーティングでは、求職者へ送るスカウトメールを企業の採用担当者が作成します。スカウトする人材の絞り込みなども採用担当者が実施するため、担当者の業務負担が増大する点はデメリットといえるでしょう。
また、ダイレクトリクルーティングで成果を出すには、一定以上の採用ノウハウが必要です。メールの文面や送る人材の属性などを適宜変更しながら、長期的な視点で採用活動を進めていく必要があるため、「すぐに人員不足を解消したい」といった短期的な人材確保には不向きです。
ダイレクトリクルーティングの費用形態
ダイレクトリクルーティングの費用形態は、大きく分けて「成果報酬型」と「先行投資型」に分けられます。それぞれの特徴を以下で詳しく説明します。
成果報酬型
成果報酬型は、ダイレクトリクルーティングサービスを経由して応募・採用があった場合に、料金が発生する費用形態です。料金を支払うタイミングは、利用するサービスにより異なりますが、採用後・入社後などのタイミングで既定の料金を支払うのが一般的です。
また、料金は採用する職種や、勤務地などによって異なります。採用活動にかけられる予算や、採用したい人数に応じて、成果報酬型のサービスを利用するか否か決めるとよいでしょう。
先行投資型
先行投資型は、ダイレクトリクルーティングサービスの運営会社が提供する「人材データベースの利用料金」を数ヶ月~1年単位で先払いする費用形態です。
利用期間内であれば、何人採用しても支払金額は変わりません。たとえば、総合人材サービスを運営するエン・ジャパンが提供しているダイレクトリクルーティングサービス「エン転職ダイレクト」では、以下のような料金形態となっています。
ベーシック |
アドバンス |
プロ |
|
サービス利用料 |
80万円 |
180万円 |
330万円 |
スカウト1通の単価 |
2,000円 |
1,800円 |
1,650円 |
入社時の成功報酬 |
なし |
なし |
なし |
利用期間内であれば、何人採用しても料金が変わらないため、採用する人数が増えるほどコストを削減できるといえます。エン転職ダイレクトの料金やプランについて、より詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
▼エン転職ダイレクトの料金と機能一覧|特徴・強み・導入事例も紹介
ダイレクトリクルーティングが中途採用に有効な3つの理由
中途採用をダイレクトリクルーティングで行うことが“有効”だといわれる理由は、主に3つ挙げられます。
なお、ダイレクトリクルーティングのメリットについては、以下の記事で解説しています。メリットを詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
①自社の求めている人材にアプローチできる
1つ目は、自社が求める人材に直接アプローチできるという理由です。
従来の採用方法では、求人広告を出したあと求職者からの応募を待つ必要があり、「応募が来ない」「応募はあるけれど自社の要件に合う人物がいない」という場合には採用につなげにくい状況でした。
ダイレクトリクルーティングであれば、データベースから求職者の情報を閲覧して、自社の希望する能力・技術・スキルを持った人材がいれば、直接アプローチを行うことが可能です。
▼自社の求める経験・スキルの例
- 営業経験が2年以上ある方
- IT業界でヘルプデスク経験が3年以上ある方
- 海外で勤務経験のある方
- 部長やマネージャー、ディレクターなどマネジメント経験のある方 など
求人サイト・採用サイトだけでは出会えなかった即戦力となる優秀な人材と出会える可能性が期待できます。
②転職潜在層にもアプローチできる
2つ目の理由は、転職を考えているけど行動できていない“転職潜在層”にもアプローチできることです。
ダイレクトリクルーティングサービスには、転職について自分から積極的に求人を探す等の行動はできていないものの、現職や現状に対して不満を抱えている求職者も多く登録しています。
「現職より条件がよければ転職したい」と考えている人であれば、企業から直接声がかかることで転職への意欲アップ、自社への入社を検討してもらえる可能性があります。
③採用力の向上につながる
3つ目の理由は、採用ノウハウの蓄積によって採用力の向上が期待できる点です。
ダイレクトリクルーティングは、採用工程のほとんどを自社で行うため、採用の数が増えるほどノウハウが社内に蓄積されます。
求職者とマッチングするためのターゲット選定や、スカウトメールの書き方などに関するノウハウが蓄積されると、より優秀な人材を採用するための方法をブラッシュアップできます。
採用力の向上にはノウハウの蓄積・分析や改善、新たな施策実行などの工数も必要ですが、長期的な視点で考えると採用活動の効率化も期待できます。
なお、ダイレクトリクルーティングは中途採用に限らず、新卒採用でも活用されています。ダイレクトリクルーティングサービス全般のメリットについては、以下の記事でより詳細に解説しています。メリットを詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
▼ダイレクトリクルーティングのメリットと注意点。成功に導くポイントとは?
中途採用でダイレクトリクルーティングを利用する際の注意点
ダイレクトリクルーティングは中途採用に有効だといわれる一方で、採用活動に取り入れる際には注意点もあります。
①業務負担が増えやすい
デメリットの項目でも述べましたが、ダイレクトリクルーティングでは、多数いる登録者から自社と親和性の高い人を選定したり、個別にスカウトメールを送ったりする必要があります。
個別対応が必要になることで採用工数が増加しやすくなるため、人事・採用担当者の業務負担が増える可能性があります。
また、業務負担が増えやすい点への解決策を以下の記事でも紹介していますので、ぜひご一読ください。
▼ダイレクトリクルーティングの3つの課題と解決策
②大量採用が難しい
求職者一人ひとりに個別のアプローチをするダイレクトリクルーティングでは、一度に多くの人材を採用につなげることが難しくなります。また、採用工数をかけてアプローチしても、すべてが採用につながるわけではありません。
大量採用を考えている場合には、ダイレクトリクルーティングに加えて、求人サイトや自社の採用サイトなどを併用して取り組むことが重要です。
③すぐに成果がでるわけではない
ダイレクトリクルーティングでは、PDCA(※)を回しながらノウハウを蓄積していく必要があります。そのため、採用ノウハウの確立していない状態では、すぐに成果につながりにくいともいえます。
また、採用担当者のスキル・経験によってアプローチの品質が左右されやすいため、培ったノウハウを社内共有して採用体制を安定化させていくことが重要です。
このように、長期的な視点で根気強く取り組む必要があることを理解しておくと焦らずに進められます。
※PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(測定・評価)、Action(対策・改善)の頭文字をとった用語で、継続的にサイクルを回し業務改善を行う手法のこと。
ダイレクトリクルーティングの流れ
中途採用でダイレクトリクルーティングを始める際は、以下の3つの流れで採用活動を行います。
▼ダイレクトリクルーティングの流れ
- ダイレクトリクルーティングサービスを選定する
- 人材を選定してスカウトメールを送信する
- 面談・面接を設定して、選考を行う
ダイレクトリクルーティングでは、人材データベースやスカウト機能が備わったサービスを利用することが一般的です。人材データベースの数やサポート体制の充実度など、自社の求める人材に出会いやすいサービスの選定が重要です。
次に、求職者のプロフィールを基に、自社の要件とマッチする人材を選定して、スカウトメールを送信します。返信があった場合には、面談・面接の日程を決定して選考へと進みます。
面談・面接時には希望をヒアリングするとともに、入社後のイメージがしやすいように自社の魅力や強み、働き方などをアピールすることが重要です。
なお、スカウトメールの返信率を高める方法については、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
まとめ
この記事では、中途採用におけるダイレクトリクルーティングについて、以下の内容を解説しました。
- 中途採用の代表的な手法
- ダイレクトリクルーティングが中途採用に有効な理由
- 中途採用で利用する際の注意点
- ダイレクトリクルーティングの実施の流れ
中途採用でダイレクトリクルーティングが有効なのは、即戦力となる人材を発掘しやすいほか、転職潜在層にも直接アプローチできる、採用力が向上するなどの理由があります。
ただし、採用工数が増えるため、担当者の業務負担が増えやすい、大量採用が難しい、長期的な視点で取り組む必要があるなどの注意点もあります。効率的に採用活動を進めるには、自社の採用ターゲットが多く利用しているサービスを選ぶことがポイントです。
ダイレクトリクルーティングサービスを検討するのが初めての方や、過去にダイレクトリクルーティングを導入したがうまくいかなかったという経験をお持ちの方は、『エン転職ダイレクト』を試してみることをおすすめします。
エン転職ダイレクトは、スカウト型のダイレクトリクルーティングサービスです。数あるダイレクトリクルーティングサービスのなかでも、人材データベースの数は413万人(2023年12月末時点)と業界最大級。スカウトメール文面の作成や送り先の選定などについて、専属のカスタマーサクセスがサポートするため、初めての方も安心して利用いただけます。
また、エン転職ダイレクトの料金やサービスの詳細はこちらで解説しています。ぜひご一読ください。