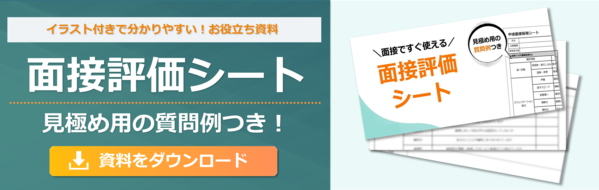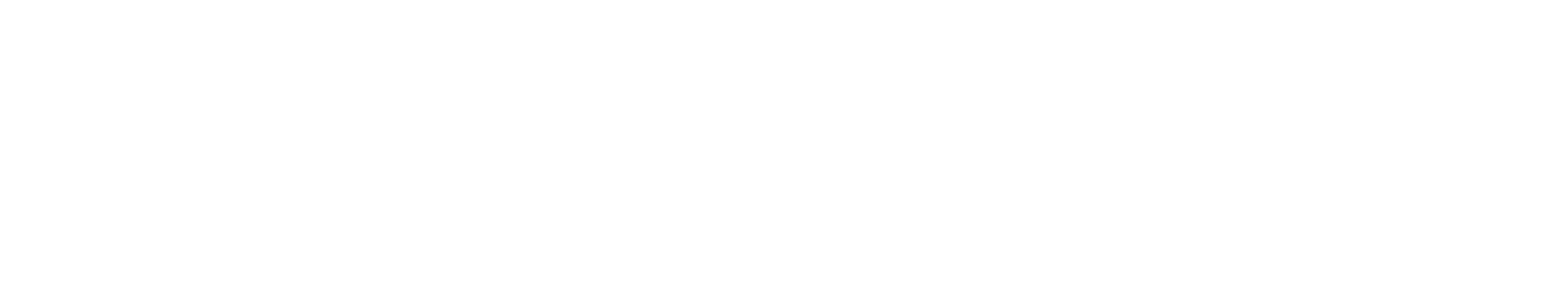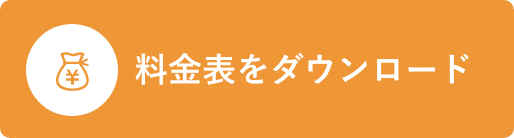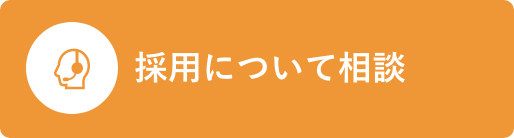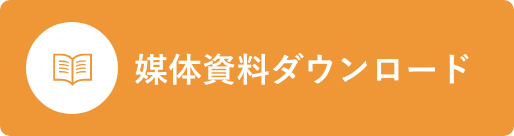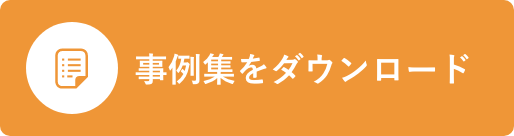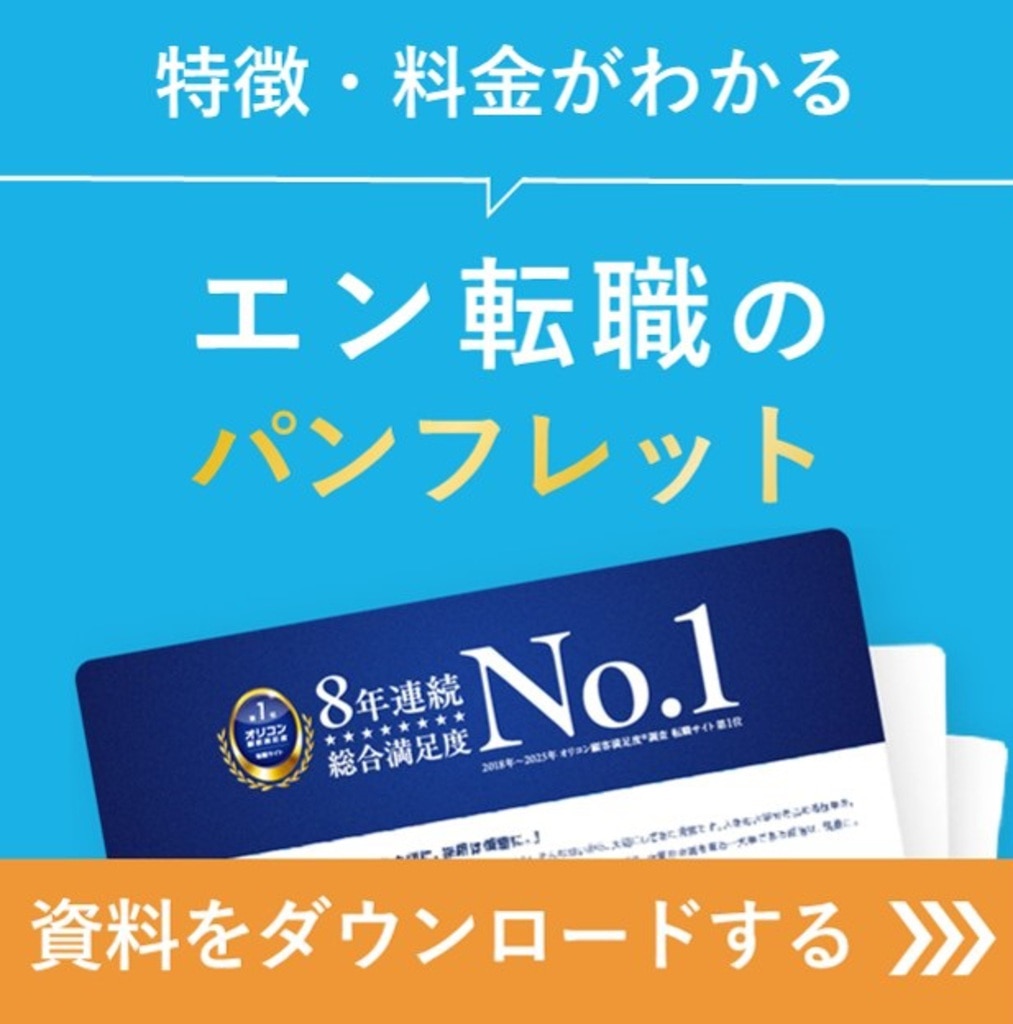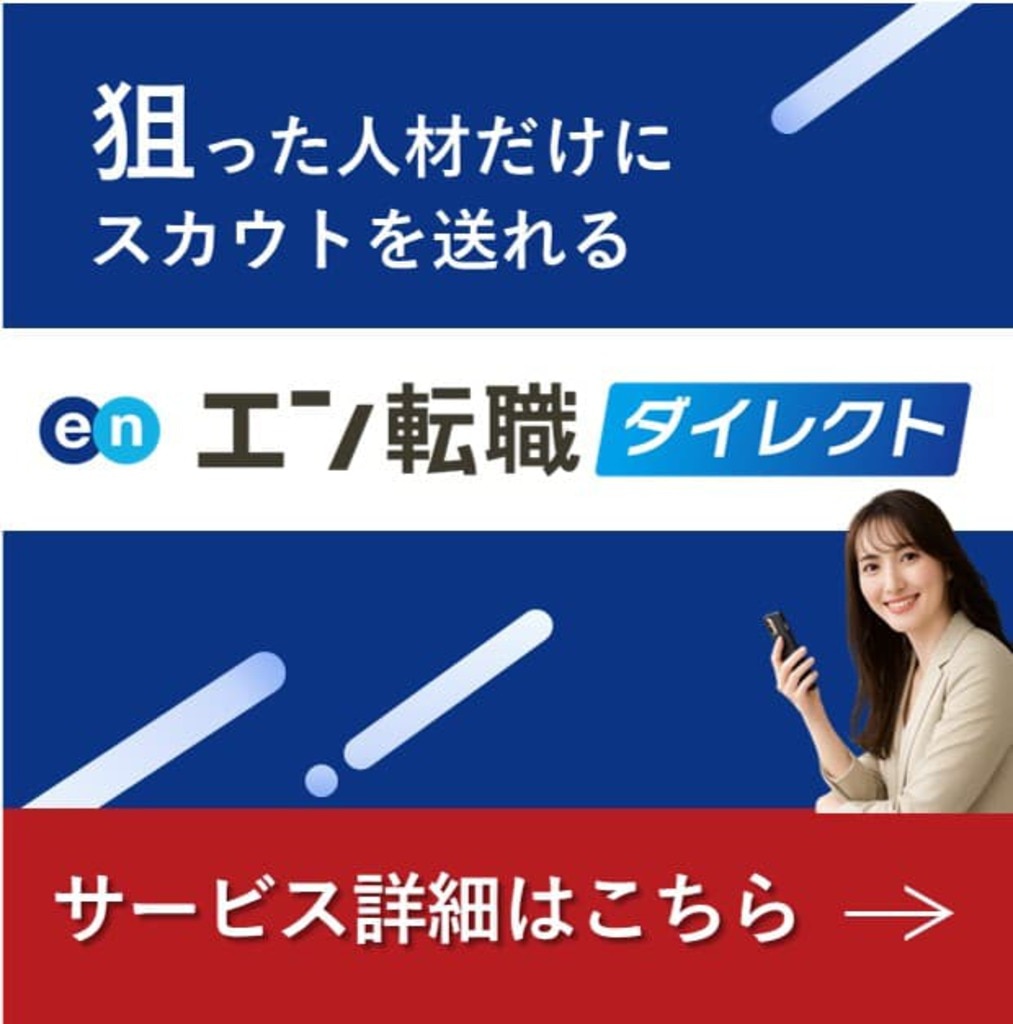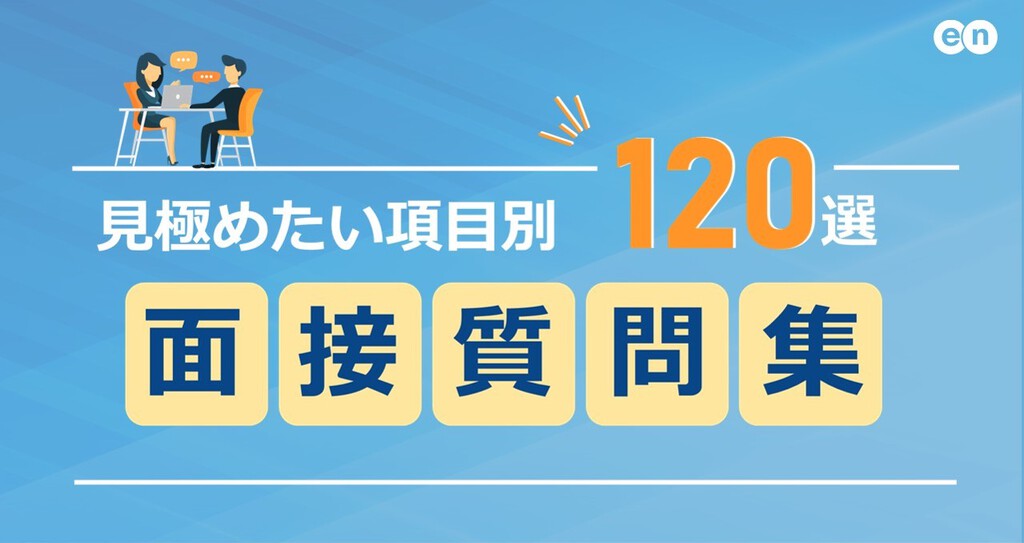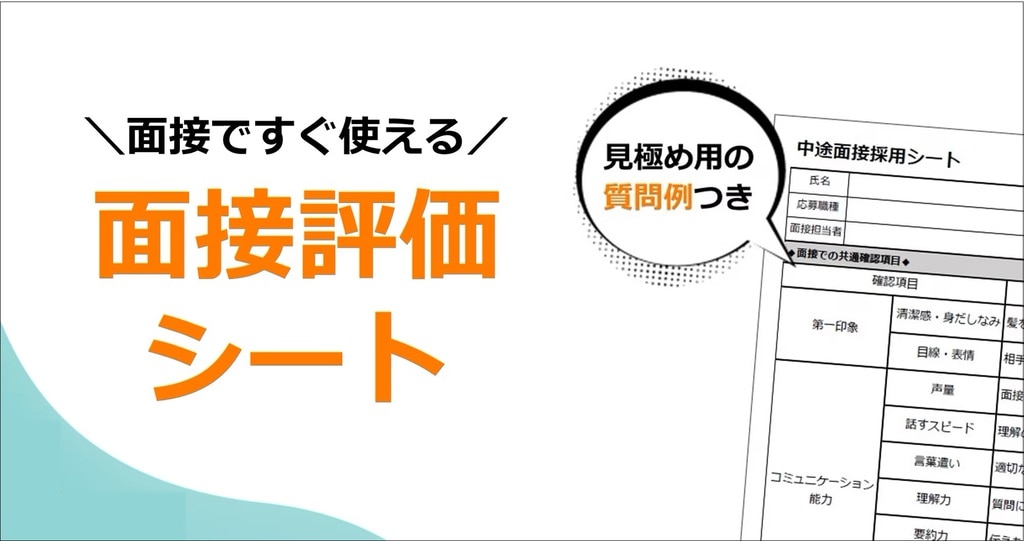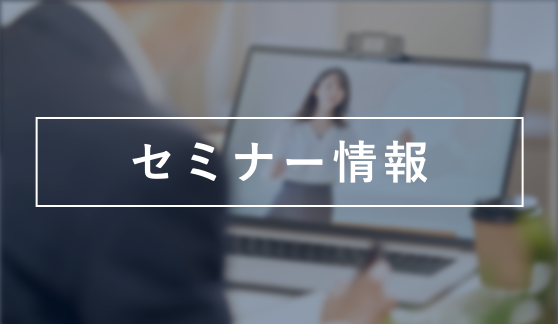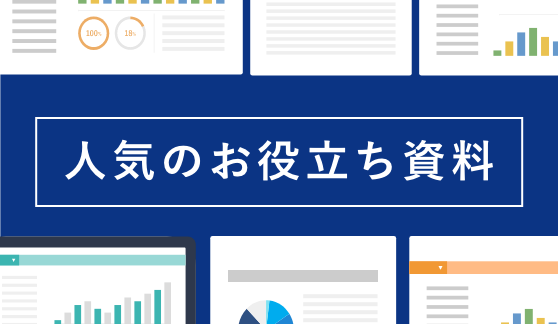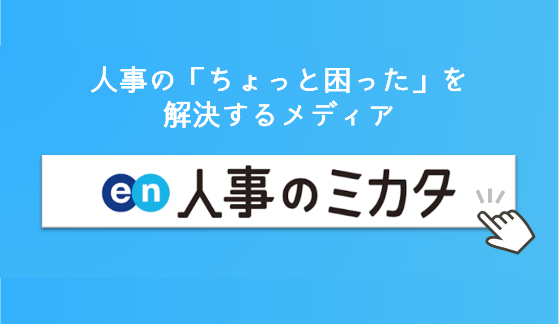構造化面接とは? メリット・デメリットや質問例、注意点などを解説

構造化面接とは、面接官が応募者への質問項目や評価基準を事前に設計しておき、定めた手順通りに進める面接のことです。構造化面接には、面接官の主観による評価のバラつきを防げるなどのメリットがあります。
しかし同時に、質問項目や評価基準を設計するための手間がかかったり、応募者を深掘りするのが難しくなったりするデメリットもあります。構造化面接を効果的なものにするためには、「面接官の見極めスキルを育成する」「質問項目を工夫して設計する」などの取り組みも必要です。
本記事では構造化面接について、詳しく解説します。構造化面接と似ている面接手法との違いや、メリット・デメリット、質問例、導入手順などをご説明しますので、「採用選考に構造化面接を取り入れたい」とお考えの方は、ぜひお役立てください。
目次[非表示]
- 1.構造化面接とは?
- 1.1.構造化面接と他の面接手法との違い
- 1.2.構造化面接が重要視されている理由
- 2.構造化面接を実施するメリット
- 3.構造化面接を実施するデメリット
- 4.構造化面接の質問例
- 5.構造化面接を導入する手順
- 5.1.自社の採用基準・評価項目・評価基準を設定する
- 5.2.面接の質問を設計する
- 5.3.面接官のトレーニングを行なう
- 5.4.実際に構造化面接を実施する
- 6.まとめ
構造化面接とは?
構造化面接とは、面接官が応募者への質問項目・評価項目・評価基準などを事前に設計しておき、定めた手順通りに進める面接手法のことです。
構造化面接は近年、Google社の採用選考で導入されていることが話題になりました。応募者への質問内容や評価が、面接官によってバラつくのを防ぎやすいため、人材を適切に見極められる手法として、多くの企業から注目されています。
構造化面接と他の面接手法との違い
構造化面接と似ている手法に「非構造化面接・半構造化面接」があります。非構造化面接は、構造化面接とは真逆の面接手法です。応募者への質問項目を事前に設定することなく、面接官が自由に面接を進めます。
半構造化面接は、面接の途中まではあらかじめ設定した質問項目に沿って進めますが、途中からは面接官が自由に質問を行ないます。3種類の面接手法の違いを下記にまとめましたので、参考にしてください。
面接の種類 |
面接の進め方 |
構造化面接 |
|
非構造化面接 |
|
半構造化面接 |
|
構造化面接が重要視されている理由
構造化面接が重要視されている主な理由には、以下の3点が挙げられます。
- 企業の採用競争が激化しているため
- 採用のミスマッチを防止するため
- 面接選考を公平・公正に行なうため
近年の日本社会は、少子高齢化による労働人口減少の影響で、企業の採用競争が激化しています。
自社に適した優秀な人材を採用するためには、公平・公正な選考で企業と求職者のミスマッチを防ぎ、より良い人材を他社よりも早く確保しなくてはなりません。
構造化面接は、企業の採用選考を迅速かつ適切に実施するための有効な手法のひとつとして、注目されているのです。
構造化面接を実施するメリット
ここからは、構造化面接を実施するメリット・デメリットについて解説します。まずはメリットから見ていきましょう。
構造化面接を実施する主なメリットには、以下の3点が挙げられます。
- 主観による評価のばらつきを防げる
- 応募者を客観的に評価しやすい
- 採用のミスマッチを防ぎやすい
構造化面接は、質問の項目や順番を事前に設計し、定めた手順に沿って面接を進める手法です。評価基準や評価項目も綿密に設計したうえで実施するので、面接官の主観に頼らない客観的な面接を行なうことが可能となります。
構造化面接を実施するデメリット
構造化面接を実施する主なデメリットには、以下の3点が挙げられます。
- 質問を設計するための手間がかかる
- 応募者の回答が偏りやすい
- 応募者を深掘りするのが難しい
構造化面接を実施するためには、あらかじめ面接の質問項目や順番、評価基準などを設計しなくてはならないため、手間と時間がかかります。また、標準的な質問ばかりを用意してしまうと、応募者の潜在的な能力や、人柄などを深掘りするのは難しくなるでしょう。
構造化面接を実施するときは、事前準備に十分な時間をとり、なおかつ質問内容にも工夫を施す必要があります。以降で質問例を紹介しますので、構造化面接を行なうときの参考にしてください。
構造化面接の質問例
構造化面接の代表的なパターンには「STAR面接・状況設定型面接(シチュエーション面接)」の2つがあります。ここからは、構造化面接におけるパターン別の質問例を紹介します。
STAR面接|行動に基づく質問
STAR面接とは、「応募者が過去にとった行動」についての質問を行ない、応募者の課題解決能力や考え方などを掘り下げていく面接方法です。別名「行動面接」とも呼ばれます。
STARは「Situation(状況)・Task(課題)・Action(行動)・Result(結果)」の頭文字をとって組み合わせたものです。4つの観点から応募者の過去の行動を深掘りし、思考や行動の傾向を評価します。
STAR面接の質問例を以下にまとめましたので、面接の流れを設計する際の参考にしてください。
▼Situation(状況に関する質問例) |
|
▼Task(課題に関する質問例) |
|
▼Action(行動に関する質問例) |
|
▼Result(結果に関する質問例) |
|
STAR面接では「どのような状況で・どのような課題を抱え・どのように行動して・どのような結果を得たのか」を深掘りできます。各項目の質問内容を、自社で募集する業務やポジションに当てはめ、適性のある人材を見極められるようにしましょう。
なお、STAR面接については、以下の記事で詳しく解説しています。より詳しい評価方法や注意点などを知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
▼誰でも応募者を深掘りできる面接フレームワーク│STAR面接とは?
状況設定型面接|未来の状況や仮説に基づく質問
状況設定型面接とは、「もし○○という状況が起こったら、どう対処するか?」を質問し、応募者の問題解決能力などを見極める面接方法です。未来の状況に基づいた質問を行なうため、「シチュエーション面接」とも呼ばれます。
状況設定型面接の質問例を以下にまとめましたので、質問の設計にお役立てください。未来の状況や仮説に基づく質問を行ない、応募者がもつスキルや能力を見極めましょう。
▼状況設定型面接の質問例 |
|
構造化面接を導入する手順
続いて、構造化面接を導入するための手順について解説します。構造化面接を自社の採用選考に取り入れたいときは、以下の流れに沿って準備を進めるとよいでしょう。
自社の採用基準・評価項目・評価基準を設定する
構造化面接を導入するにあたり、自社の採用基準・評価基準・評価項目などを明確に定める必要があります。
「どのような人材を採用したいのか」
「その人材をどのような評価項目によって見極めるのか」
こういった基準が不明瞭なままだと、面接の質問を設計できません。まずは、採用選考をするにあたって重要な「自社の基準」を明確にしましょう。
人材を採用する基準を定めるときは、こちらの記事が参考になります。採用基準の具体的な設定方法を解説していますので、ぜひご覧ください。
▼採用基準とは? 設定方法やポイント、注意点、人材の適切な見極め方を紹介
また、面接での評価項目や評価基準を定めるときは、以下の記事が参考になります。加点方式・段階評価など面接の評価方法も解説していますので、ぜひご覧ください。
▼面接の評価基準を設定する方法とポイント。自社が求める人材を見極めるには
面接の質問を設計する
採用基準や評価項目が決まったら、面接で行なう質問の流れを設計していきます。質問の流れを設計するときは、まず起点の質問から定めましょう。
起点の質問とは「あなたが今までで一番苦労した業務は何ですか?」というような、話の起点となる質問のことです。構造化面接では以下の例のように、まず起点となる質問を行ない、その質問への回答をもとにして応募者をさらに深掘りします。
▼質問の流れの例 | |
起点となる質問の例 |
あなたが今までで一番苦労した業務は何ですか? |
深掘りする質問の例 |
その業務をどのように乗り越えましたか? |
起点となる質問および、深掘りする質問を何にするかは、前述した質問例を参考にするとよいでしょう。
面接官のトレーニングを行なう
面接質問の設計まで終わったら、面接官に対してトレーニングを行ないましょう。面接官役・応募者役にそれぞれ社員を割り振り、面接のロールプレイングを実施するのもオススメです。
- 質問の流れは不自然ではないか?
- 応募者について知りたい内容を聞き出せているか?
- 自社の評価項目に沿った質問内容となっているか?
このような観点から質問の流れをチェックし、面接本番できちんと人材を評価できるようにしましょう。
また、面接の流れが構造化されている中でも、応募者が話しやすい雰囲気をつくることは重要です。応募者がリラックスして話せなければ、本来の能力を見極めるのが難しくなるでしょう。
構造化面接を有意義なものにするため、下記のような観点でも十分なシミュレーションを行ない、面接官の面接スキルを向上させましょう。
- 質問をするとき棒読みになっていないか?
- 矢継ぎ早に質問をして圧迫面接のようになっていないか?
- 応募者の回答を一方へ誘導するような聞き方になっていないか?
実際に構造化面接を実施する
面接官のトレーニングまで済んだら、実際に構造化面接を採用選考で実施します。今までに設計してきた質問項目や評価基準、トレーニングしてきた内容を活かして、応募者が自社の採用基準に適しているか見極めましょう。
また、面接での評価をしっかりと記録したいときは、「面接評価シート」を作成するのが便利です。以下のリンクより、テンプレートを無料ダウンロードしていただけますので、適宜アレンジをしてお使いください。
▼「見極め用の質問例つき! 面接評価シート」を無料ダウンロードする
まとめ
構造化面接について、似ている面接手法との違いや、メリット・デメリット、質問例、導入手順などを解説しました。構造化面接とは、面接官が応募者への質問項目・評価項目・評価基準などを事前に設計しておき、定めた手順通りに進める面接手法です。
構造化面接の主なやり方には、STAR面接や状況設定型面接などがあります。自社の採用基準や評価基準を定めて、質問例をもとに面接の質問を考えましょう。
また、人材の見極め精度を高めたいときは、「求人の書き方を工夫すること」も有効です。求人の書き方を工夫して、面接前の段階で「求める人材からの応募数」を増せれば、面接での見極めがより高精度になります。
「求める人材からの応募数」を増やしたい場合は、ぜひ『エン転職』にご相談ください。エン転職は1000万人の会員を保有する、日本最大級の中途採用向け求人サイトです。
エン転職は業界内でも珍しく、取材専門の「ディレクター」と、求人専門の「コピーライター」を自社で雇用・育成しています。採用およびライティングのプロが求人広告を作成するため、ただ単純に応募を集めるだけでなく、活躍できる可能性が高い人材からの応募を集めやすくなります。
また、エン転職は求人広告の質が高いため、過去20回開催されている「求人広告賞」のうち、半数を超える通算11回を受賞しています。採用でお悩みの際は、以下のエン転職お問い合わせ窓口より、お気軽にご相談ください。
他にもエン転職には採用を成功に導く様々な特徴があります。エン転職の料金表・パンフレットダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますので合わせてご覧ください。
▼エン転職のサービス紹介サイト