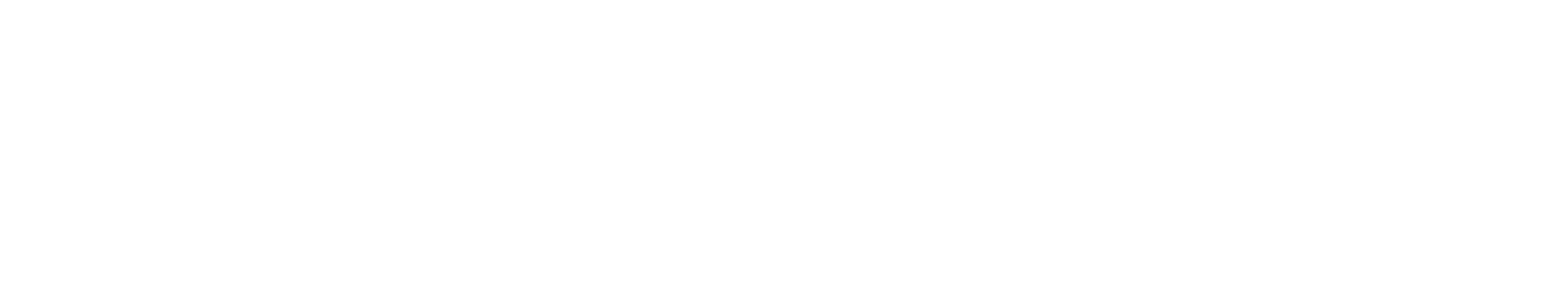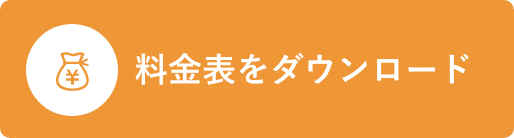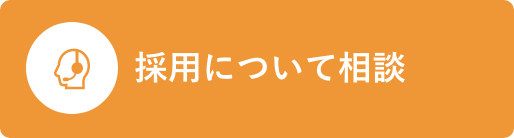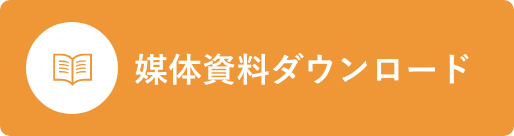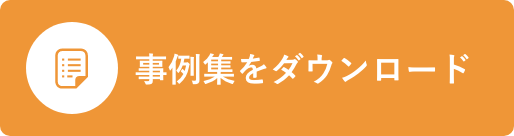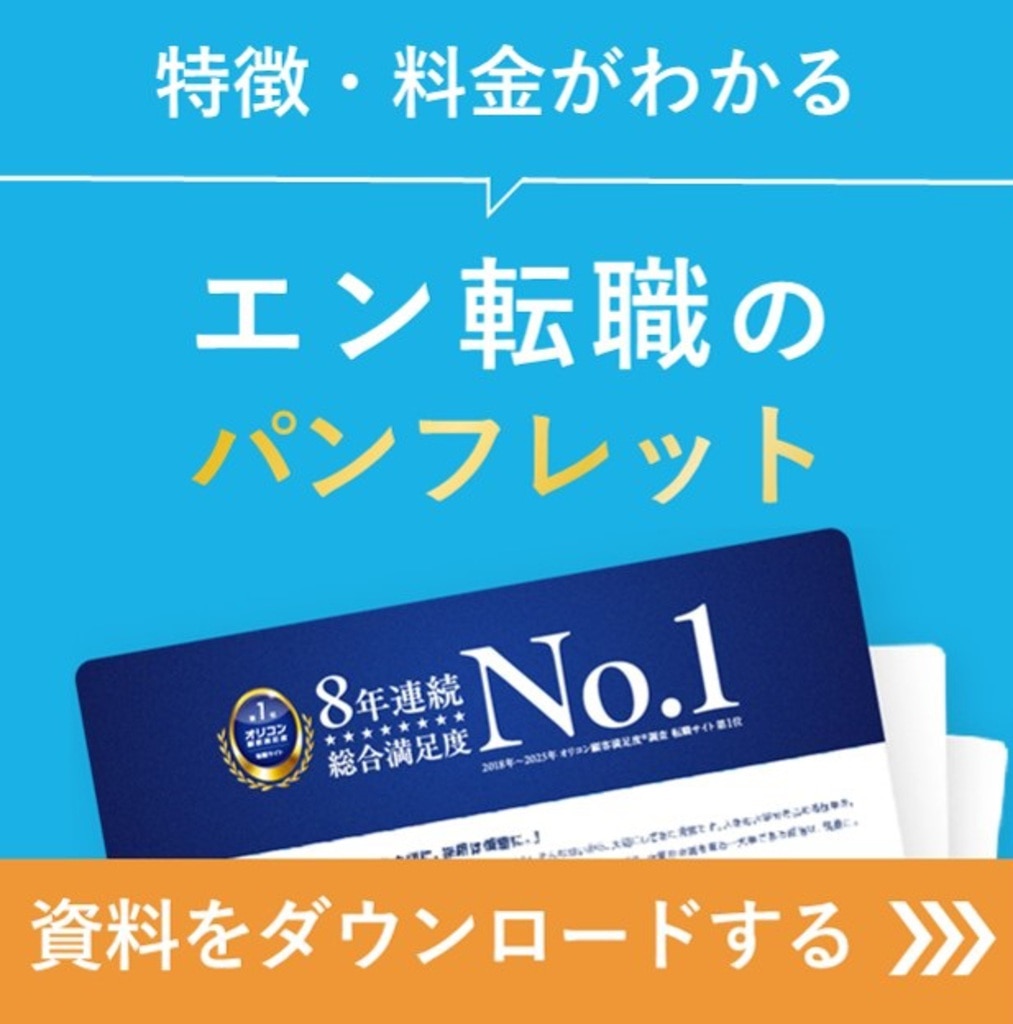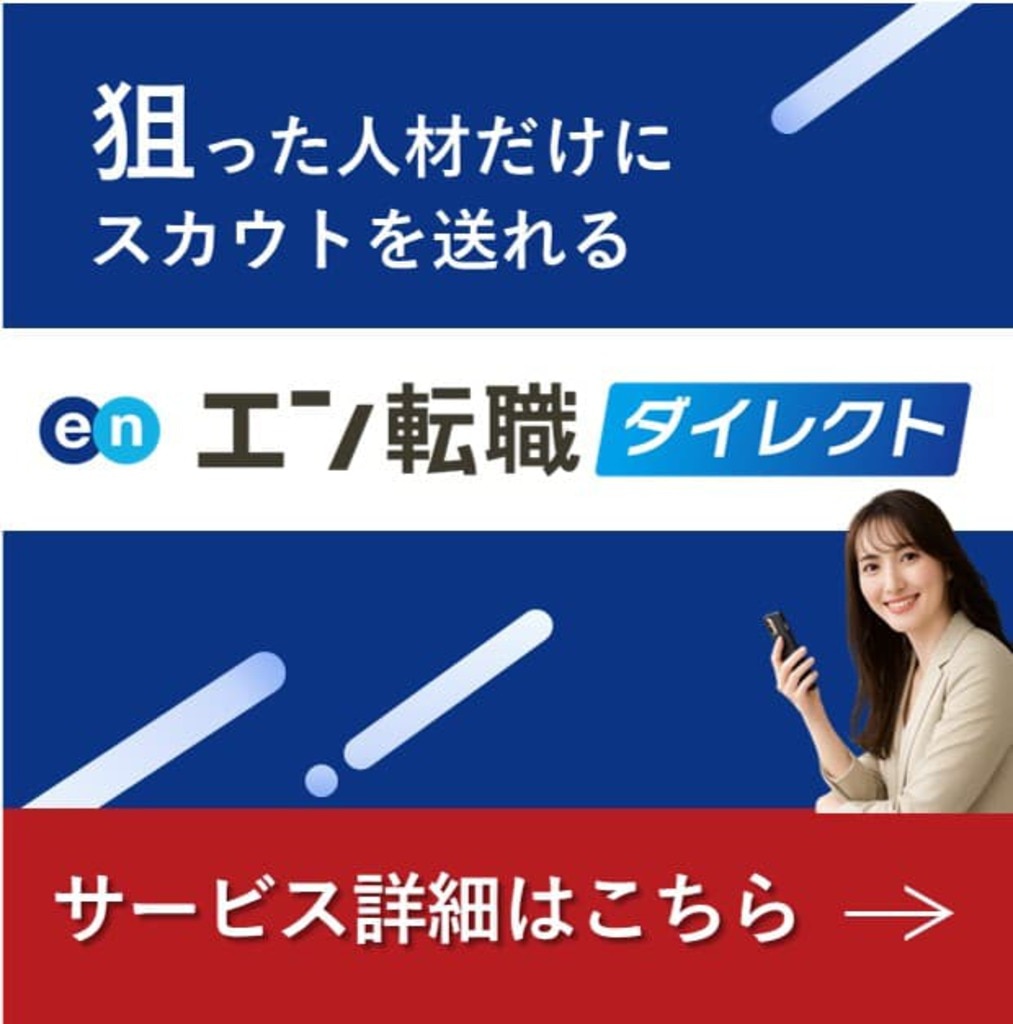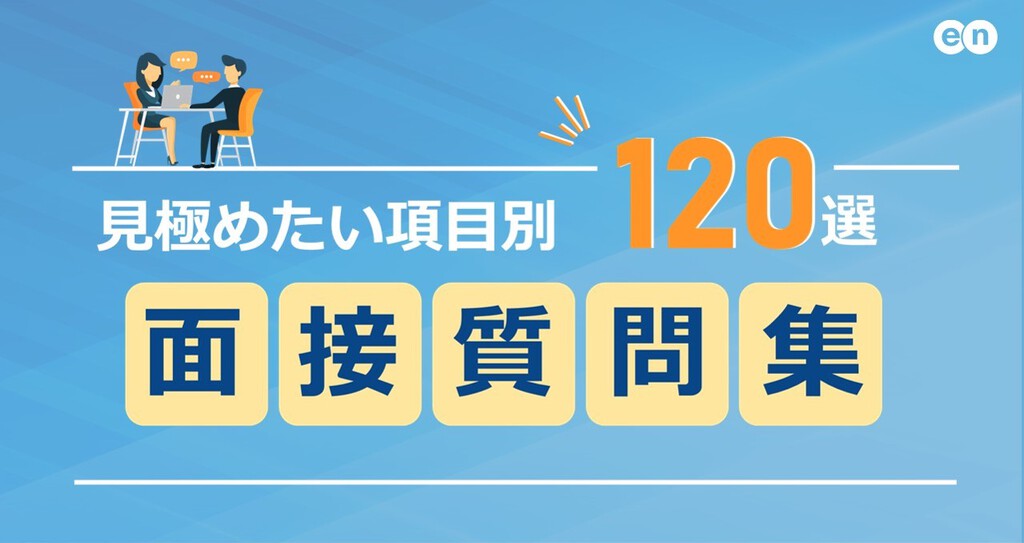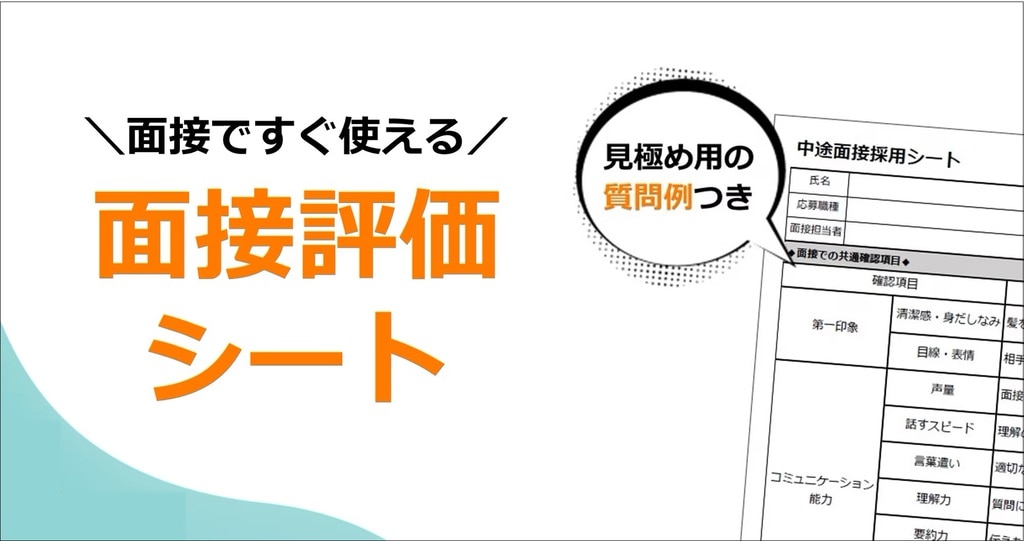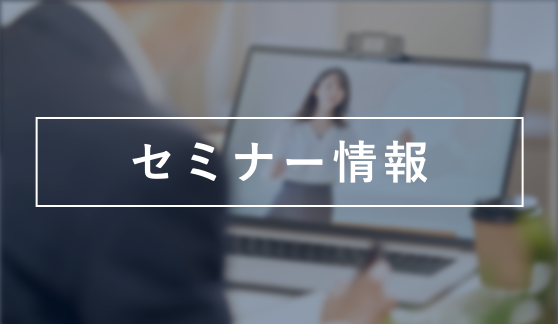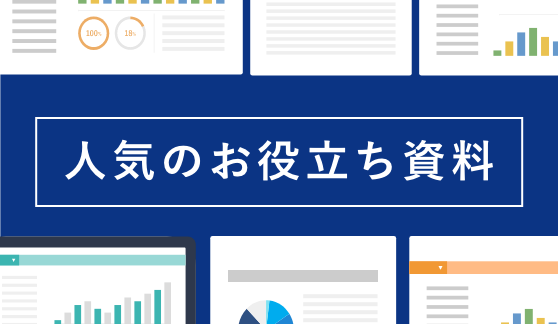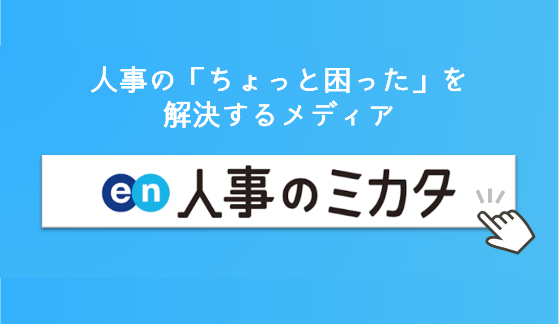【質問例つき】面接で聞いてはいけないこととは? 令和の時代で禁止されている質問例を紹介!

採用面接では、公正な採用選考が義務づけられており、厚生労働省は特定の質問事項について、人権尊重の観点から配慮すべきとしています。人事・採用担当者は、意図しない職業差別を防止するために、どのような質問が禁止されているのか理解を深めておくことが必要です。
禁止されている質問事項は細かく定められているため、「どのような質問をしてはいけないのか」「質問する際の注意点はあるのか」などと気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、採用選考の基本姿勢を踏まえつつ、面接で聞いてはいけないことについて質問例とともに紹介します。
▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「面接で聞いてはいけないNG質問」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼
目次[非表示]
- 1.公正な採用選考を行うための基本姿勢
- 1.1.応募の門戸を広く開く
- 1.2.適正・能力に基づいて選考する
- 2.【質問例あり】面接で聞いてはいけないこと
- 2.1.本人に責任のない事項
- 2.2.本来自由であるべき事項
- 3.採用選考を行うときの注意点
- 3.1.適性・能力に関係のない事項を把握しない
- 3.2.応募条件を不合理に制限しない
- 4.面接で聞いてはいけないことを聞いてしまった場合のリスク
- 5.まとめ
公正な採用選考を行うための基本姿勢
企業の人事・採用部門には公正な採用選考を行うことが義務づけられています。採用選考の公正性を保つために、以下の2つの基本姿勢を理解しておくことが求められます。
応募の門戸を広く開く
公正な採用選考のためには、特定の人を除外することなく、誰でも応募できるようにすることが必要です。
人種や性別、病気・障がいの有無、性的マイノリティなどにかかわらず、採用基準に当てはまる人のすべてが応募できるようにすることが求められます。
適正・能力に基づいて選考する
採用面接の際は、「業務の遂行に必要な適性・能力を持っているか」という点に基づいて選考することが重要です。
家族や思想、宗教などの本人には責任のない事項のほか、本来自由であり業務を遂行するにおいて無関係な事項を採用基準に含めてはいけません。
出典:厚生労働省『R03.02・公正採用選考啓発リーフレット』『公正な採用選考の基本』『公正な採用選考を目指して』
前提として、面接は企業にとって「選ぶ側」でもあり、「選ばれる側」でもあります。求人募集をしている企業が無数になる中で、自社を選んでもらうために面接官の態度・立ち居振る舞いには注意が必要です。面接官として押さえておきたい心得については、以下の記事で詳細に解説しておりますので、あわせてご覧ください。
▼【面接官マニュアル】採用面接の心得と基本のやり方。気をつけることとは?
【質問例あり】面接で聞いてはいけないこと
公正な採用選考を行うために、面接時には応募者本人に責任がない事項や、業務に無関係な事項に関する質問をしてはいけないと定められています。ここからは、具体的な事項を質問例とともに解説します。
本人に責任のない事項
本人に責任のない事項とは、以下のような内容が挙げられます。
▼本人に責任のない事項
- 本籍に関すること
- 家族に関すること
- 住宅状況に関すること
- 生活・家庭環境に関すること
面接で聞いてはいけない質問例には、以下が挙げられます。
▼不適切な質問例
「ご出身はどちらですか」
「ご両親の出身地はどこですか」
「生まれてから、ずっと現住所に住んでいますか」
「ご両親はどのようなお仕事をされていますか」
「ご自宅は持ち家ですか」
「学費は誰が出しましたか」
「家庭はどのような雰囲気ですか」
「〇〇駅のどちら側に住んでいますか」
「家は○○市のどのあたりですか」
「お住まいの地域はどのようなところですか」
出典:厚生労働省『R03.02・公正採用選考啓発リーフレット』『公正な採用選考の基本』『公正な採用選考を目指して』/大阪労働局『就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例』
本来自由であるべき事項
本来自由であるべき事項とは、以下のような内容が該当します。
▼本来自由であるべき事項
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観に関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合・社会運動などに関すること
応募者に聞いてはいけない質問例には、以下が挙げられます。
▼不適切な質問例
「信仰されている宗教はありますか」
「ご家族やあなたの支持している政党はありますか」
「どのような本を愛読していますか」
「あなたの人生観を教えてください」
「購読している新聞はどこですか」
「尊敬する人物は誰ですか」
「日本社会で生きることについてどう思っていますか」
「過去に学生運動に参加されたことはありますか」
「結婚、出産したとしても働き続けますか」
「結婚の予定はありますか」
出典:厚生労働省『R03.02・公正採用選考啓発リーフレット』『公正な採用選考の基本』『公正な採用選考を目指して』/大阪労働局『就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例』
▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「面接で聞いてはいけないNG質問」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼
採用選考を行うときの注意点
採用選考を行うにあたっては、面接で直接質問する内容のほかにもいくつか注意点があります。ここでは、選考を行う際の注意点について解説します。
適性・能力に関係のない事項を把握しない
業務への適性・能力に関係のない事項については、面接時に尋ねたり、応募用紙・エントリーシートに記載させたりしてはいけないと定められています。
▼適性・能力に関係のない事項
- 戸籍謄本・住民票に関すること
- 思想及び信条
- 業務において合理性のない健康診断に関すること
- その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
ただし、特別な職業上の必要性が存在したり、業務の目的の達成に必要不可欠であったりする場合には、 目的を示した上で本人からこれらの事項を把握することが認められます。例えば健康診断に関して、業務上の適性・能力を測るために必要と客観的に判断される場合には、実施しても問題ないとされています。
また、身元調査を実施して採否の判断材料とすることは、職業差別に該当するおそれがあるため注意が必要です。例えば、応募者の居住地域や生活環境を実地で調べたり、本人とその家族に関する情報を集めたりすることが挙げられます。
出典:厚生労働省『R03.02・公正採用選考啓発リーフレット』『平成 11 年労働省告示第 141 号』『公正な採用選考を目指して』
面接ではこうしたNG質問をさけつつ、応募者の本質を見極める必要があります。応募者の本質を見極める質問例については以下の記事で解説しておりますので、あわせてご一読ください。
▼採用面接で応募者の本質を見抜く質問例と注意点
応募条件を不合理に制限しない
採用サイトや求人広告に記載する応募条件には、職務を遂行するために必要な適性・能力に関係のない項目を設けてはいけないことも定められています。
応募条件を求人サイトや求人広告に記載する際は、特定の人が一律に排除されていないかどうか、求人情報の書き方に注意する必要があります。
出典:厚生労働省『R03.02・公正採用選考啓発リーフレット』『公正な採用選考の基本』『公正な採用選考を目指して』
面接で聞いてはいけないことを聞いてしまった場合のリスク
採用面接の際に不適切な質問をした場合には、『職業安定法』第48条の4において行政指導や改善命令などが行われるリスクがあります。
行政指導や改善命令に従わない場合は、同法第65条に基づいて6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課される可能性があります。
▼職業安定法第48条の4
特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。
引用元:e-Gov法令検索『職業安定法』
▼職業安定法第65条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第三項の規定に違反したとき。
二 第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
三 第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。
四 第三十六条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
五 第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつたとき。
六 第三十九条、第四十条又は第四十三条の三の規定に違反したとき。
七 第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。
八 第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
九 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
十 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。
十一 労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき。
引用元:e-Gov法令検索『職業安定法』
また、人権尊重に配慮しない不適切な面接は、会社のイメージダウンにつながるおそれがあります。その結果、業績に影響したり、採用の応募者が減少したりする可能性があるため注意が必要です。
出典:e-Gov検索『職業安定法』/厚生労働省『公正な採用選考をめざして』
まとめ
この記事では、面接での質問について以下の内容を解説しました。
- 公正な採用選考を行うための基本姿勢
- 面接で聞いてはいけない事項
- 採用選考を行うときの注意点
- 判断が難しい質問事項と対応
- 面接で聞いてはいけないことを聞いてしまった場合のリスク
公正な採用選考を行うには、応募の門戸を広く開き、業務の適性・能力に基づいて評価することが大切です。本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事項について聞くことは、職業差別につながるおそれがあるため、質問しないように注意する必要があります。
また、面接時の質問だけでなく、求人媒体での応募条件の書き方にも注意が必要です。公正な採用選考の妨げとなる項目を記載しないような配慮が求められます。
求人の訴求力を上げて競合他社と差別化を図りたいとお考えであれば、日本最大級である1,000万人の会員を保有する中途採用向け求人サイト『エン転職』がおすすめです。
エン転職では、取材専門の「ディレクター」と、求人専門の「コピーライター」を自社で雇用・育成していることが特徴です。人権に配慮した掲載内容をはじめ、会社や仕事の魅力が最大限に伝わる求人を作成いたします。
エン転職は求人広告の質の高さが強みの一つであり、2018年から2021年まで、「求人広告賞」を4年連続受賞中。過去に開催された18回のうち、半数を超える通算10回をエン転職が受賞しています。
採用でお悩みの際は、以下のエン転職お問い合わせ窓口よりお気軽にご相談ください。
ほかにも、エン転職には採用を成功に導くさまざまな特徴があります。掲載料金や特徴については、こちらをご確認ください。
なお、面接時に活用できる質問集について、こちらの記事でまとめています。ぜひご活用ください。
▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「面接で聞いてはいけないNG質問」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼