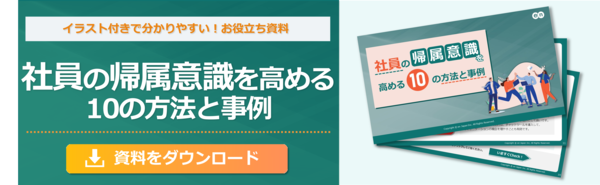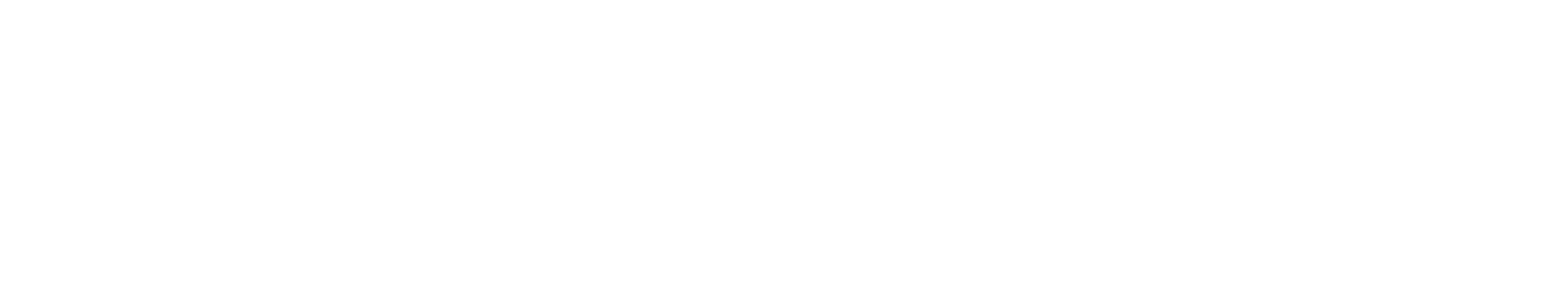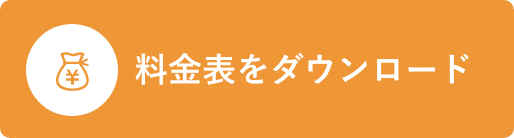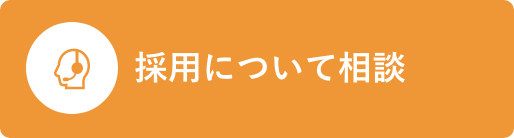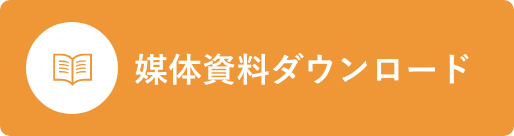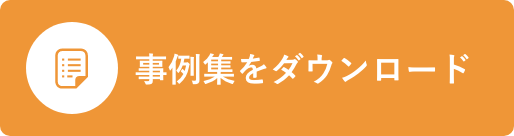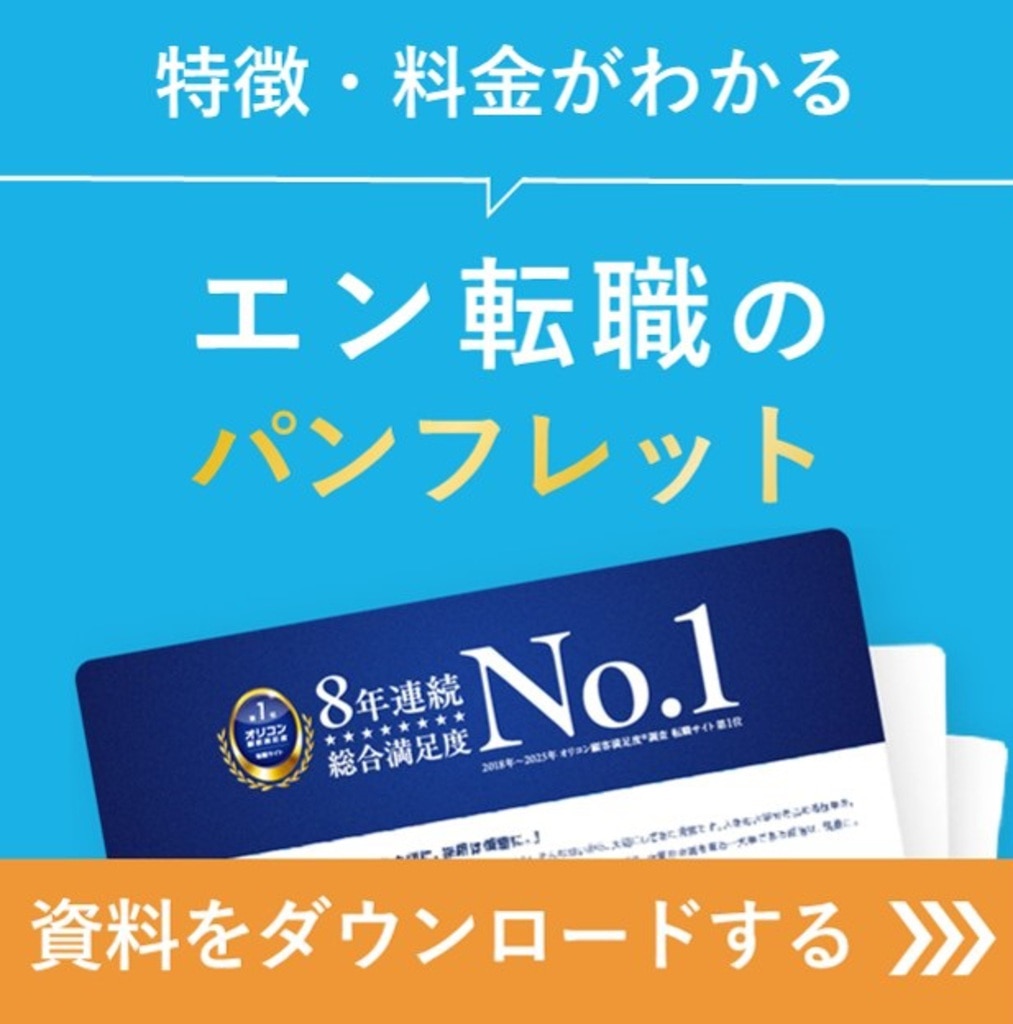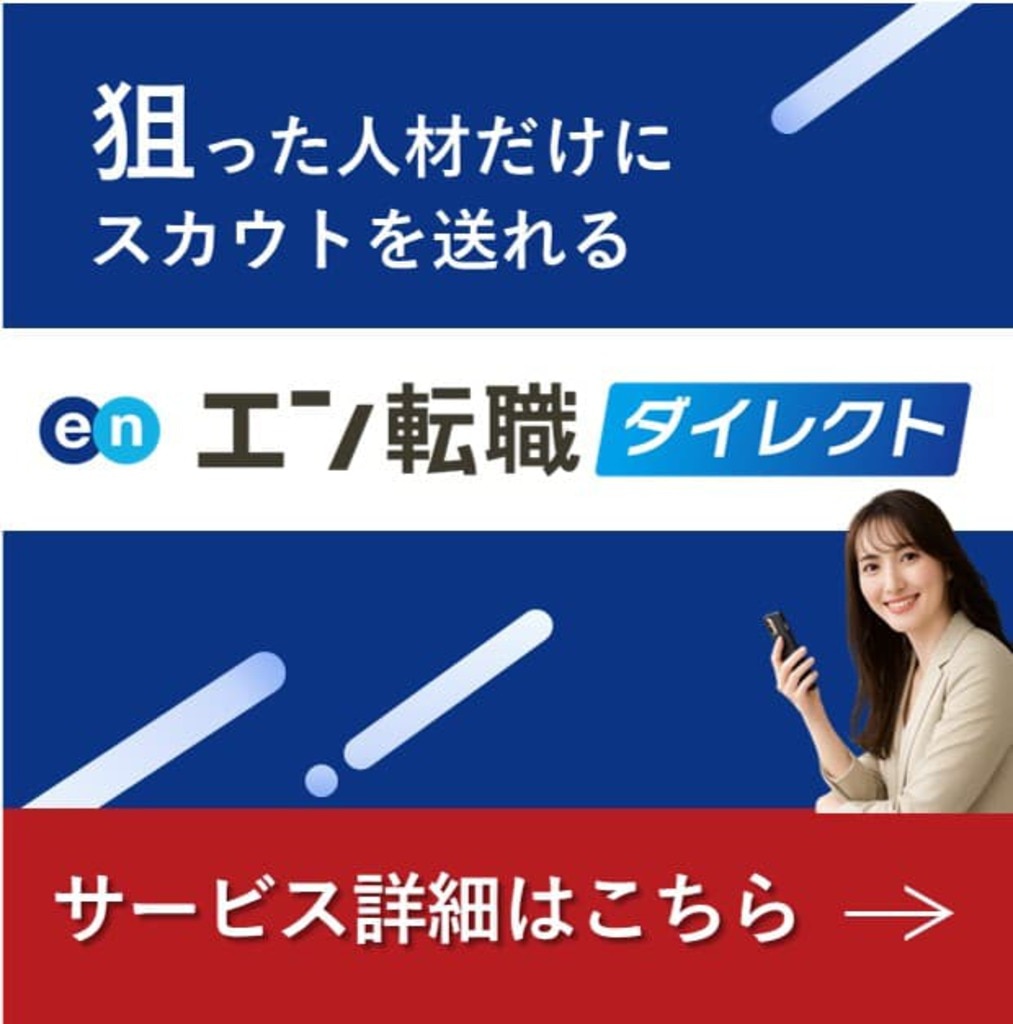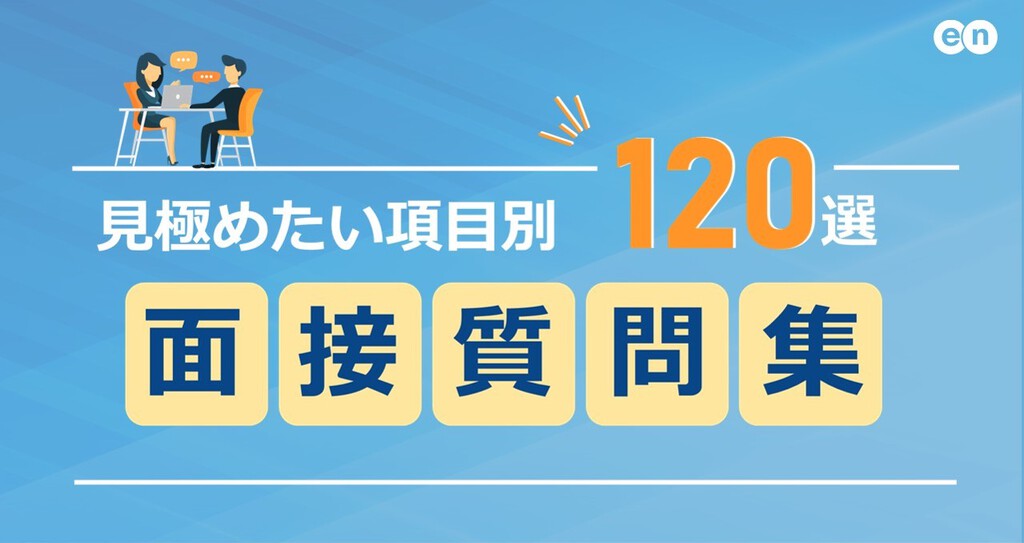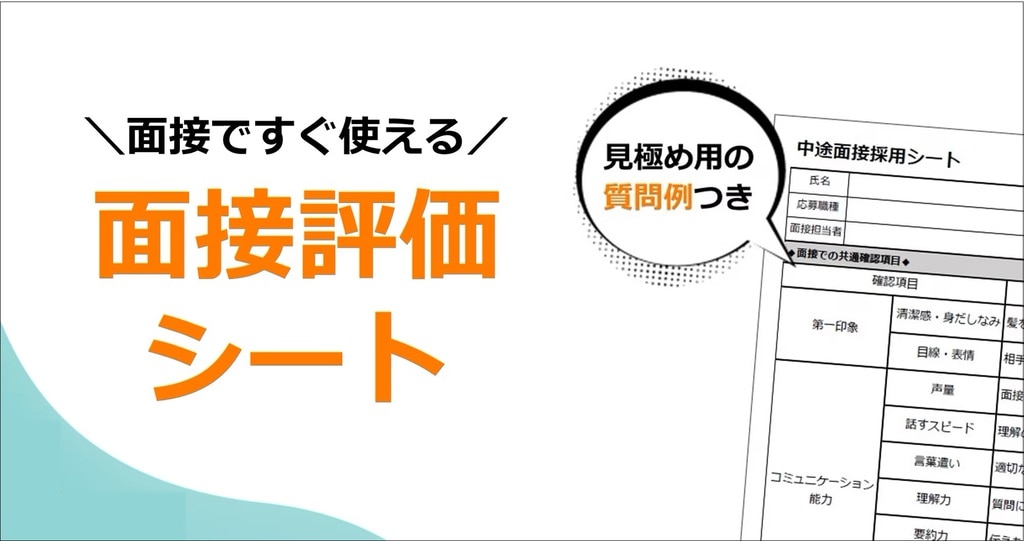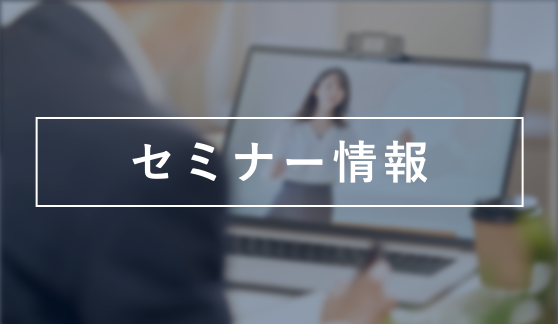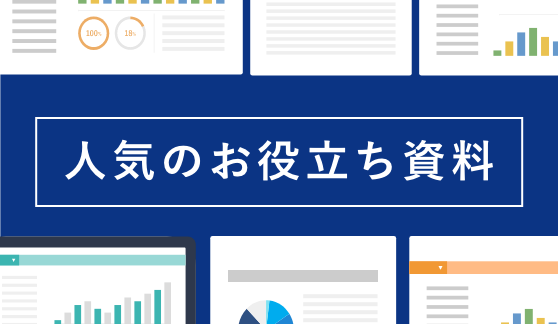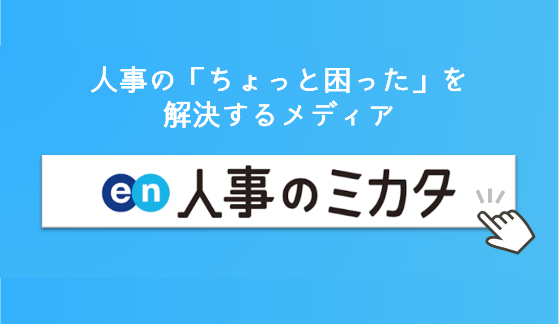帰属意識とは?企業が意識すべき理由、向上に向けた10の具体策を解説

働き方の多様化が広がる今、企業にとって「帰属意識」を高める動きは不可欠です。しかし、「どういうメリット・デメリットがあるのか分からない」「実際にどう高めていくのか想像がつかない」という方も少なくないでしょう。そこで、この記事では、帰属意識の用語解説や、帰属意識を高める10の方法をお伝えします。
▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「社員の帰属意識を高める10の方法と事例」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼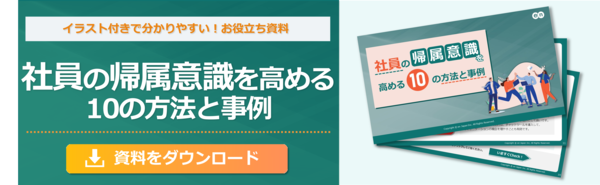
目次[非表示]
- 1.帰属意識とは
- 1.1.企業の組織づくりで重要な考え方
- 1.2.エンゲージメント、ロイヤリティとの違い
- 1.3.帰属意識のコロナ禍における変化
- 2.帰属意識の低下がもたらすリスク
- 2.1.意欲低下により生産性ダウン
- 2.2.退職による人員不足や事業計画の崩れ
- 3.帰属意識が企業にもたらすメリット
- 4.帰属意識を高める方法
- 4.1.仕事のやりがいを感じられる風土の醸成
- 4.2.福利厚生・待遇の改善
- 4.3.評価制度の見直し
- 4.4.コミュニケーションの活性化
- 4.5.入社者・内定者のフォロー
- 4.6.リファラル採用の活用も有効
- 4.7.採用段階から意識
- 5.採用の工夫で帰属意識を高める方法
- 6.求人の工夫で帰属意識の高い人材を採用した事例
- 6.1.株式会社JUT JOY
- 6.2.株式会社ウィル
- 7.まとめ
帰属意識とは
「帰属意識」というのは、組織や集団の一員であるという意識や感覚を表す言葉です。もともとは心理用語の一つ。「帰属意識が高い」というのは、所属組織・集団に対して一体感を持ち、愛着、興味・関心を抱いている状態を表します。
企業の組織づくりで重要な考え方
人事領域における「帰属意識」とは、社員が所属企業の一員であるという自覚のことを指します。社員の帰属意識が高いほど、企業に貢献するモチベーションにつながります。例えば、組織における問題を“自分事”として捉えて取り組むようになったり、業務に責任感を持って向き合うようになったり、といったことが考えられます。
エンゲージメント、ロイヤリティとの違い
帰属意識と似た言葉に、エンゲージメント、ロイヤリティがありますが、エンゲージメント、ロイヤリティとはベクトルや立ち位置が異なります。
エンゲージメントも、社員の企業への愛着や思い入れを表す言葉です。しかし、帰属意識は社員から企業への一方向の姿勢を指すのに対して、エンゲージメントは社員から企業、企業から社員と双方向的な姿勢を指します。
エンゲージメントについては以下の記事でより詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。
また、ロイヤリティも企業への献身的な態度を指す言葉になります。しかし、ロイヤリティは企業が上位にあり、社員が下位にある“主従関係”を前提としていますが、帰属意識にそういった前提はありません。
帰属意識のコロナ禍における変化
まずは、帰属意識が着目されている背景から整理します。もともと日本では終身雇用制度が中心でしたが、近年ではその制度が実質崩壊していることで、帰属意識という考え方に注目が集まっています。
就職から定年まで一つの企業で働くことが当たり前の時代では、自ずと帰属意識が高まっていました。しかし転職が当たり前となった現代では、企業が帰属意識を意識的に上げる工夫をしなければ、向上させるのが難しくなっています。
さらに、コロナ禍において多様な働き方が普及したことが、働く人々の帰属意識に影響をもたらしています。例えば、リモートワークの推進によって社員同士のコミュニケーションが不足し、組織への愛着が薄まってしまうことも。アフターコロナと言われ、人々の働き方が変わりゆく今、帰属意識への取り組みがさらに必要となるでしょう。
帰属意識の低下がもたらすリスク
社員の帰属意識が低い場合、企業にどのような影響を与えるのか。具体例を交えながら、詳しく解説します。
意欲低下により生産性ダウン
帰属意識が低下している状態では、もちろん仕事へのモチベーションも高くなりません。社員にとっては「頑張る意味」の一つがなくなってしまうためです。組織全体の業務効率や生産性が下がれば、事業に悪影響が及ぶことも考えられます。
退職による人員不足や事業計画の崩れ
「この会社で働く意味」を十分に感じられず、他の環境を求めて企業を去る社員が増えれば、企業や組織が人員不足となってしまうことも。退職により他の社員に過度な負担がかかり、さらに帰属意識が低下する、といった悪循環が生まれてしまうかもしれません。
また、企業は事業計画をもとに動きますが、例えば管理職クラスの社員が抜ければ、計画自体を変更しなければならない可能性もあります。新たな人材を採用し、育成するには時間や費用の面でコストが発生するでしょう。帰属意識が低下することで、無駄な損失が出てしまうのです。
帰属意識が企業にもたらすメリット
ここまで、企業にとって帰属意識の向上がいかに重要か述べてきましたが、実際に施策に取り組むことでどのようなメリットがあるのでしょうか。以下では、帰属意識が企業にもたらすメリットを見ていきます。
社員定着率の向上
人事・採用担当や経営者にとって「社員定着率」は最も気になる数値の一つです。帰属意識が高まり、「この会社で、この組織で、この仕事を頑張りたい」と思われることで、長く勤める社員が増えていくでしょう。社員定着率が高ければ、新たな採用を行なう際も、求職者に良い印象を与えることができます。
さらなる事業成長
意欲的な姿勢を持った社員が、企業や事業をしっかり理解して携わっていくため、事業がより良い方向に向かい、業績向上なども見込めます。企業成長という形で成果が出ることで、社員のモチベーションはさらに高まっていくでしょう。
帰属意識を高める方法
これまで企業が帰属意識に気を配る必要性をご説明してきましたが、以下では「帰属意識を高める方法」をご紹介します。企業の状況に合わせて、よろしければ導入をご検討ください。
仕事のやりがいを感じられる風土の醸成
社員が「今の仕事はやりがいを感じられず、自分が働く意味を感じられない」といった思いを抱いているとき、高い帰属意識を持つことは難しいでしょう。そういった場合は例えば、感謝を伝え合う文化をつくる、社員の頑張りを賞賛するイベントを開催する、経営者が仕事の意義を何度も発信するなど、やりがいを感じられる風土を醸成する取り組みが必要です。
福利厚生・待遇の改善
「十分な待遇を得られず、生活が難しい」など、福利厚生・待遇は、社員のモチベーションに大きく影響します。社員が不満に思っているポイントを探り、福利厚生・待遇の改善を行なうことも大切です。社員が求める環境を用意する姿勢があり、実際に改善を図ることができる企業であれば、「ここで長く働きたい」と思ってもらえるでしょう。
評価制度の見直し
年功序列ではなく実力主義の企業も増えている今。「頑張ってもなかなか評価されない」という社員の不満が、帰属意識の低下につながります。そのため、改めて評価制度を見直し、「評価基準は企業方針や組織風土、社員のタイプなどに合っているか」「成果などに対して正当な評価ができているか」などを確認し、改善していくことが求められます。
コミュニケーションの活性化
前段でご説明しましたが、コロナ禍を経た今、多くの職場でコミュニケーションが不足していると言われています。そこで、まずは上司や人事からの日頃の声かけを行ない、定期面談などで相談の場を設けることが大切です。
また、固定の席を持たず、社員が自由に席を選んで働く「フリーアドレス制」を導入するのも一つの手です。普段は交流のない社員も、周囲に座っていれば話しかけやすいはずです。
同様の理由でオフィスに「ラウンジスペース」を設置し、気軽に話ができる場所をつくることも、帰属意識への取り組みとして良いでしょう。リモートワークの企業であれば、チャットツールを導入してコミュニケーションの機会を増やすことも有効です。
どのような施策が社員の定着率向上や組織のコミュニケーションの活性化につながるのか、エン・ジャパンが運営する「入社後活躍研究所」と「甲南大学 尾形教授」の共同研究結果が発表されています。ぜひあわせてご覧ください。
入社者・内定者のフォロー
新たに採用された方々が帰属意識を持っているか都度確認することで、早期退職のリスクを防ぐことができます。そこで、例えば毎月社員への自動Webアンケートを行なう 『HR Onboard』など、ツールの導入もおすすめです。帰属意識の低下が見られる社員に対して、工数少なく、いち早くフォローすることができます。
リファラル採用の活用も有効
「リファラル採用」とは企業が社員から、友人や知人を紹介してもらう採用手法です。すなわち、入社者は「企業への一定の理解」「仲間がいる安心感」を持って入社するため、帰属意識につながりやすいです。さらに、既存社員にとっては企業や組織、仕事の魅力を再確認する良い機会となります。詳しい活用方法は別記事で紹介していますので、こちらもよろしければご覧ください。
採用段階から意識
上記では主に既存社員に向けた帰属意識を高める取り組みを紹介してきましたが、「自社に愛着・興味・関心を持っている人材」を採用することで帰属意識の高い社員を増やしていくことも大切です。
ここからは、採用に活かせる「帰属意識を高める方法」をご紹介します。
採用の工夫で帰属意識を高める方法
「帰属意識」となると、今いる社員に目を向けることが多いでしょう。しかし、採用段階においても工夫次第で、入社者に帰属意識を持ってもらうことができるのです。
筆者は求人専門のコピーライターとして4年携わってきましたが、帰属意識まで意識して採用を行なう企業は入社後の活躍度・定着度も高い傾向にあります。そこで、以下では、帰属意識の向上への取り組みをご紹介します。
衛生要因だけでなく動機付け要因でも魅力付けする
「衛生要因」「動機付け要因」という言葉を初めて目にした方も多いのではないでしょうか。アメリカの臨床心理学者であるフレデリック・ハーズバーグが提唱した「二要因理論」では、仕事の“満足”に関わる要因を「動機付け要因」とし、仕事の“不満足”に関わる要因を「衛生要因」としています。
■ 仕事の「満足」に関わる要因
=「動機づけ要因」(承認・称賛・達成・成長・責任など)
■ 仕事の「不満足」に関わる要因
=「衛生要因」(給与・賞与・休日・福利厚生など)
従来の求人ではこの「衛生要因」が強調されてきました。しかし、給与・福利厚生だけに惹かれた人材を採用すると、より良い「衛生要因」の会社を見つけるとまた転職してしまう可能性があります。
だからこそ、「この会社でしか得られない仕事の意義・やりがい・成長・承認・賞賛」といった「動機付け要因」を求人でアピールして、そこに惹かれた人材を採用することが帰属意識の向上につながるのです。
入社者・経営者のインタビューを活用する
採用における帰属意識の施策として、インタビューで“中の人”たちの声を届けることも重要です。例えば、中途で入社した社員へのインタビューで、企業ならではの魅力をしっかり語ってもらうことで、求職者は「所属する意味」を感じられるでしょう。
また、インタビューを通じて経営者の考えを伝えることで、経営方針・事業のビジョンに共感する人材からの応募が集まりやすくなり、帰属意識が高い人材の獲得が期待できます。
求人や採用HPで企業の理念・方針を見せる
共感は強い帰属意識につながります。経営者インタビューと少し似た話になりますが、企業の理念・方針を求職者に伝えることが大切です。人事・採用担当からかみ砕いて説明したり、社員同士で対談を行なったり、実際に理念・方針が仕事に活かされている場面を取り上げたり…伝え方も工夫することで、企業への帰属意識が高い求職者を集めることができます。
求人の工夫で帰属意識の高い人材を採用した事例
実際に求人の工夫で帰属意識の高い人材の採用に成功した事例を2つご紹介します。
株式会社JUT JOY
ITベンチャー「JUT JOY」は急成長を遂げており、主体的に仕事に取り組める人材を必要としていました。帰属意識が高く、企業貢献を考えられる方を採用するために、以下の工夫を行なっています。
今回、求人作成にあたり、『トップメッセージ』を導入しました。『エン転職』では通常の求人情報以外に、インタビュー記事の掲載が可能です。トップメッセージの記事では、代表の思いや会社の展望を伝えることができます。「求職者に企業理解を深めてもらいたい」「方針・風土にマッチする人材を集めたい」といったニーズに対応する追加オプションです。
こうした工夫により、「理念に共感した」「代表と話してみたい」という方から応募があり、トップメッセージを見て「地方のDXに興味がある」と面接で語る人が増えました。その結果、社風に合った、高い帰属意識が期待できる人材からの応募獲得につながっています。
株式会社ウィル
「ウィル」は通信企業に特化した派遣会社です。入社後にギャップを感じ、社員の早期退職が起こっていることに困っていました。そこで、『エン転職』への求人掲載と同時に、Webアンケートツール『HR OnBoard』を導入し、面接の担当者や面接方法を改善。帰属意識の向上につなげています。
実際に入社された方のお話では、入社の決め手は「面接で経歴や志望動機ではなく、自分の話を聞いてくれたこと」だと言います。この方は高校卒業後に就職活動を行なっていましたが、学歴や経験の浅さから書類選考の段階で落ちてしまっていたそう。しかし、同社からは面接の機会を設けてもらうことができ、「私自身を見てくれている」と感じられたことで、入社につながっています。
このように、帰属意識のデータを測り、それをもとに採用活動の改善を図ることも、帰属意識を高める方法の一つです。
上記では採用成功事例の一部をご紹介しました。豊富な採用ノウハウがある『エン転職』であれば帰属意識を高める採用が可能です。よろしければ他の事例もご覧ください。
▼『エン転職』採用成功事例の一覧はコチラ
まとめ
人材の流動化が激しい今、「同じ企業で働き続ける意味」を生み出すという意味で、帰属意識を高めることは重要です。できれば、既存社員への取り組みだけでなく、採用段階から帰属意識の高い人材を採用できるとより良いでしょう。
そこで、『エン転職』の活用をおすすめします。「入社後活躍」をテーマに掲げる『エン転職』は、帰属意識を高める採用についても得意分野です。実際に、『エン転職』経由の入社者は他サイトに比べ、離職率が「半分以下」となっています。
求人専門のディレクター・コピーライターが入社後の活躍・定着まで意識した求人を作成しているからこそ、高い定着率を実現可能です。 掲載時のフォローも手厚く行ないます。貴社が抱える課題解決のために、まずはお気軽にご相談ください。
ほかにも『エン転職』には採用を成功に導く様々な特徴があります。『エン転職』の料金表・パンフレットダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますのであわせてご覧ください。
▼エン転職のサービスページ
▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「社員の帰属意識を高める10の方法と事例」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼