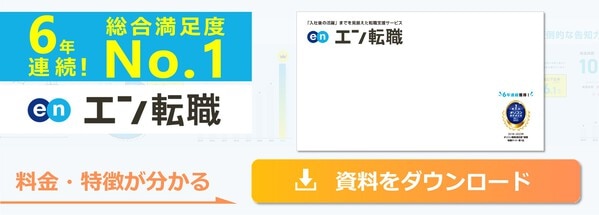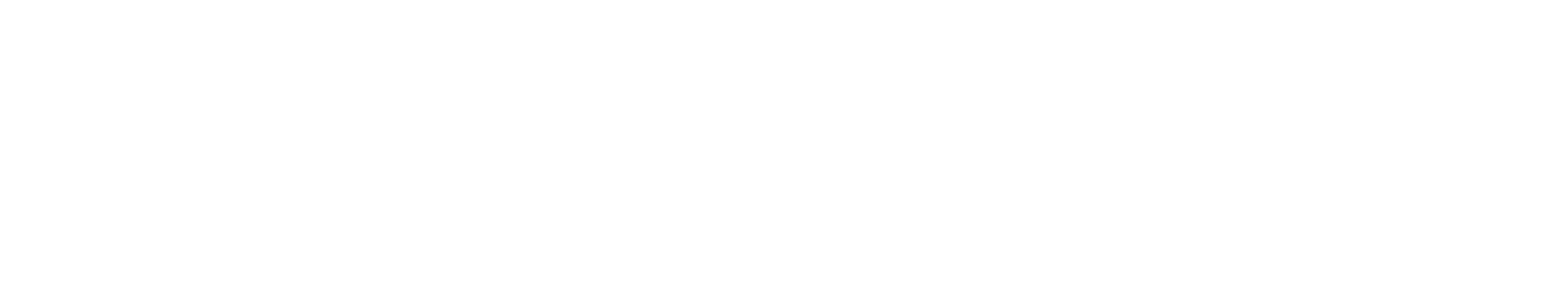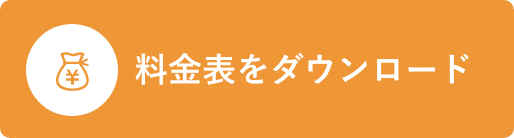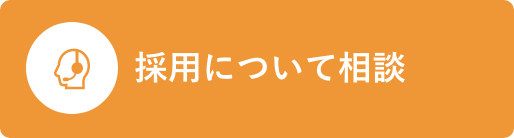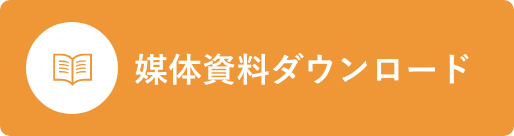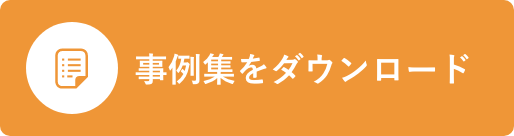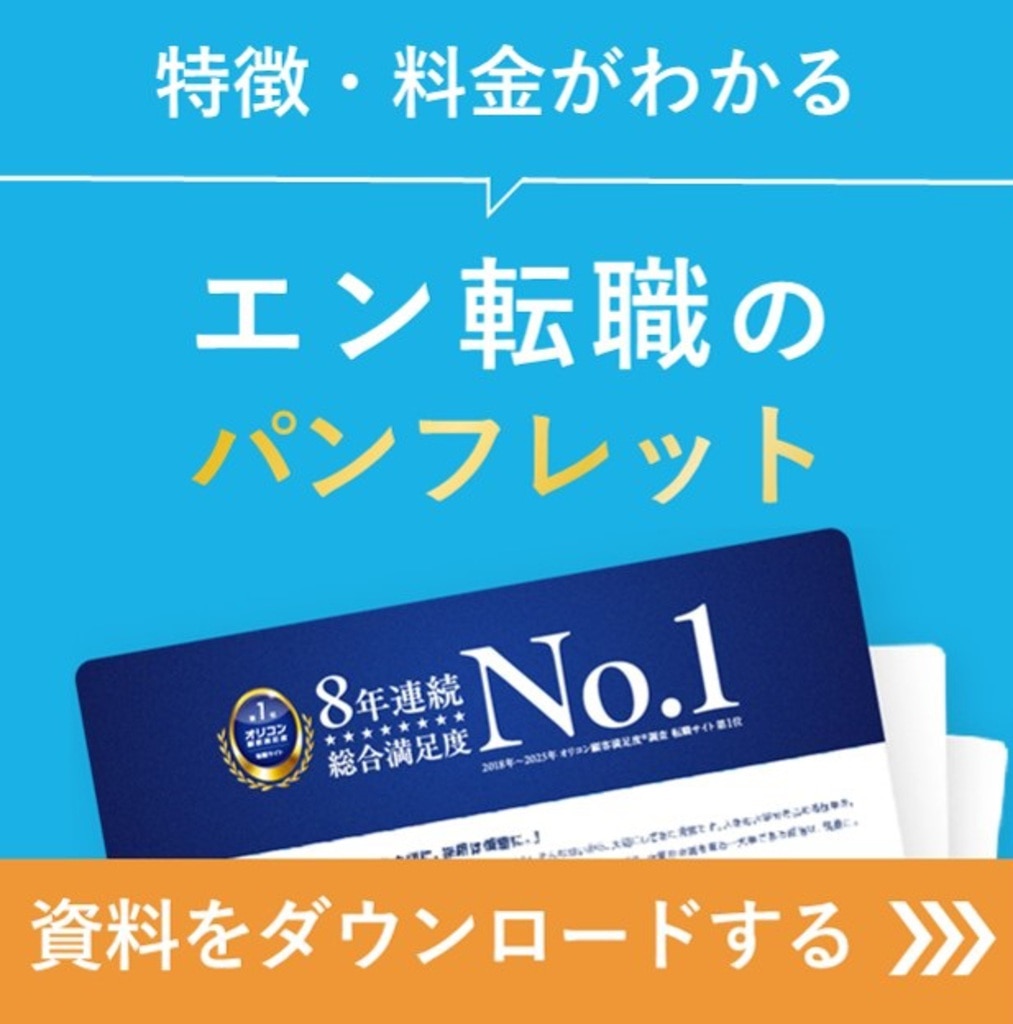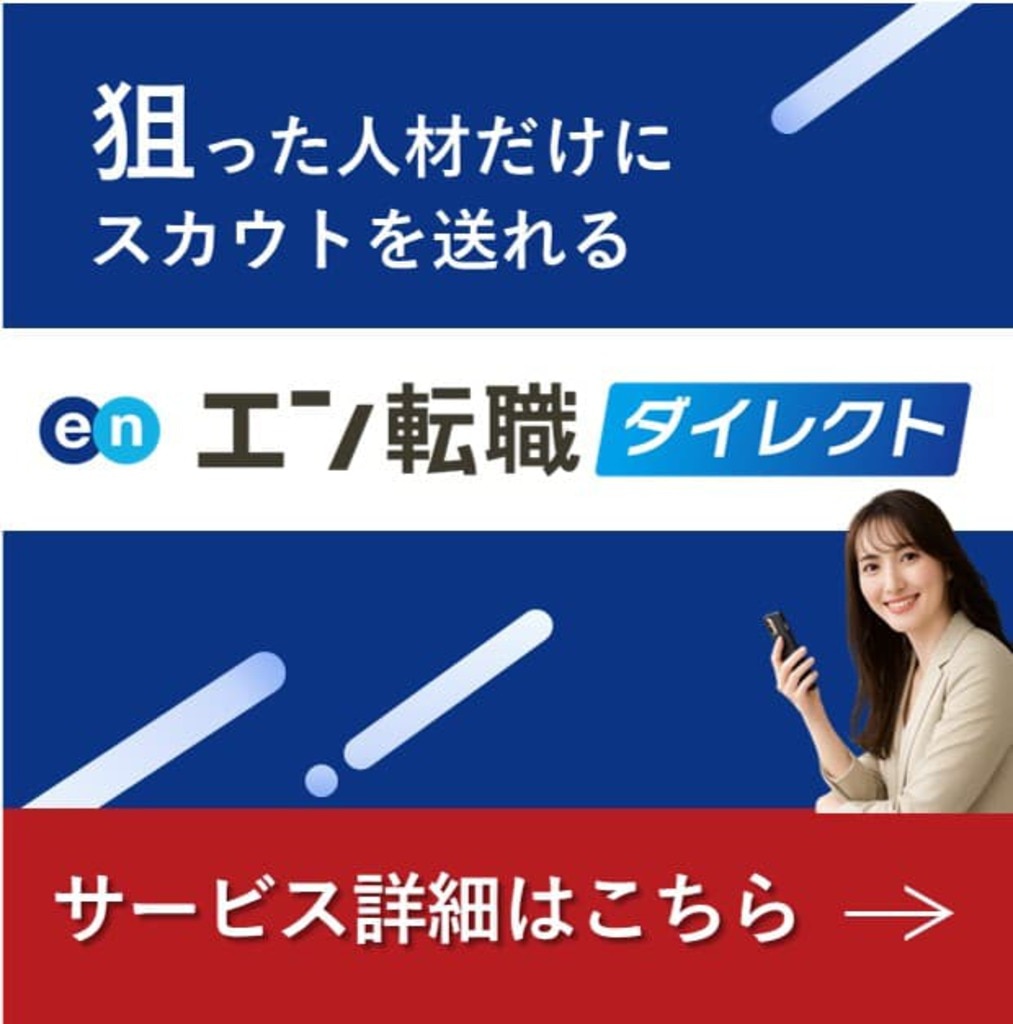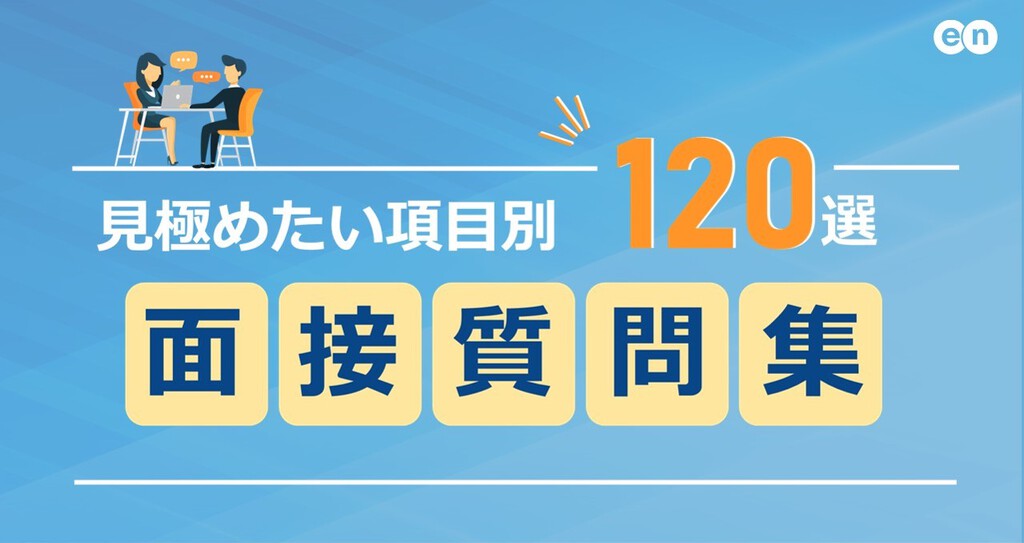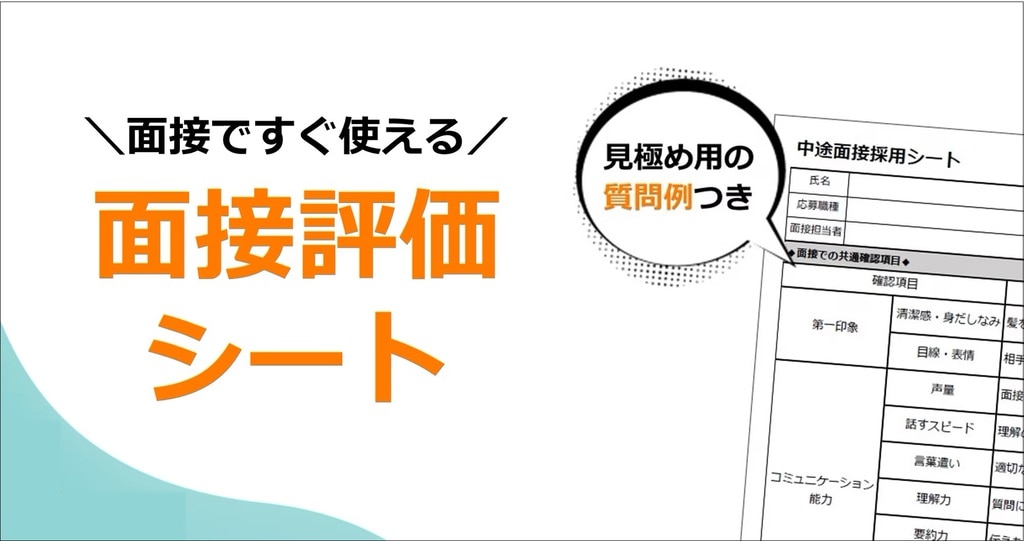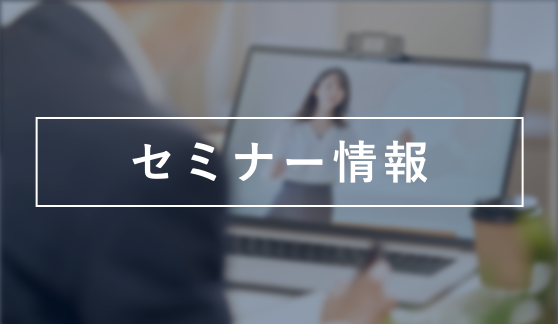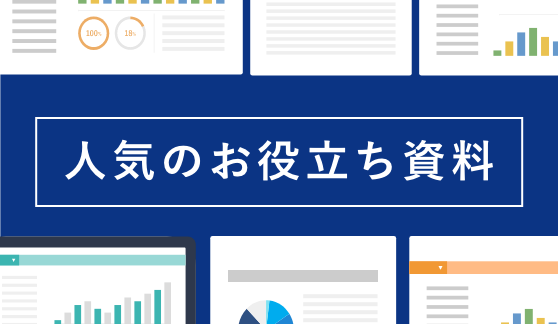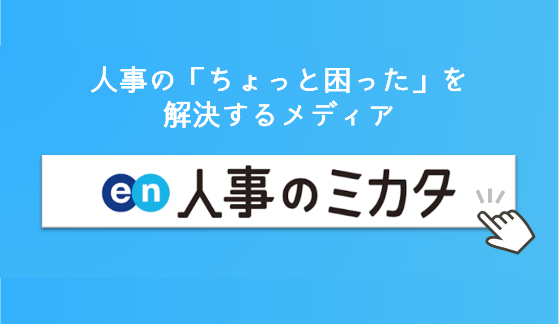アセスメントとは? 分野別の意味や使い方、導入手順をわかりやすく解説

昨今インターネット上の記事など、さまざまなメディアでよく目にする「アセスメント」。聞き覚えはあるものの、詳しい意味や活用方法までは知らない…という方も多いでしょう。
アセスメントとは「人や物事の傾向・特性などを客観的・数値的に評価すること」をいいます。アセスメントは、対象となる人や物事を客観的に評価して判断できるため、採用・人事・医療・介護・保育などの分野で多く活用されています。
本記事ではアセスメントの分野別の意味や、使い方などをわかりやすく解説します。また、企業の採用や人事に活用されている「人材アセスメント」についても詳しく解説しますので、「具体的な活用方法を知りたい」という方は、ぜひ一読して採用活動や人材配置などにお役立てください。
目次[非表示]
- 1.アセスメントとは?
- 1.1.アセスメントの意味
- 1.2.アセスメントの使い方と文例
- 1.3.アセスメントと似ている言葉
- 2.アセスメントの分野別の意味
- 2.1.人材アセスメントとは?
- 2.2.組織アセスメントとは?
- 2.3.医療・看護アセスメント
- 2.4.介護・福祉アセスメント
- 2.5.環境アセスメント
- 2.6.ライフサイクルアセスメント
- 2.7.リスクアセスメント
- 3.人材アセスメントの目的・メリット
- 3.1.人材を客観的に評価できる
- 3.2.採用のミスマッチを防止できる
- 3.3.客観的かつ公平な人事評価ができる
- 4.人材アセスメントの活用方法
- 4.1.採用選考に使う
- 4.2.人材育成に使う
- 4.3.人員配置・管理職の抜擢に使う
- 5.人材アセスメントの実施方法やツール
- 5.1.アセスメント研修
- 5.2.適性検査
- 5.3.360度評価(多面評価)
- 5.4.エニアグラム
- 6.人材アセスメントの導入手順
- 6.1.人材アセスメントの目的を明確化する
- 6.2.目的に適したツール・評価方法を選ぶ
- 6.3.アセスメントした結果を目的に活用する
- 7.人材アセスメントを実施するときのポイント
- 7.1.自社の評価基準を定める
- 7.2.実施目的を周知させる
- 7.3.実施結果をフィードバックする
- 7.4.継続的に情報収集と効果測定を行なう
- 8.まとめ
アセスメントとは?
まずは、アセスメントの意味や使い方、文例、類義語などを解説します。
アセスメントの意味
アセスメント(assessment)は「評価・判断・査定」などの意味をもつ単語です。ビジネスや福祉、政治などのシーンでは「人や物事の傾向・特性などを客観的・数値的に評価すること」といった意味合いで使われています。
アセスメントの主な目的は、対象となる人や物事の現状・傾向・特性などをアセスメントツールの活用によって客観的に分析し、適切に対処することです。アセスメントは用途が広く、採用・人事・医療・介護・環境整備など多くの分野で活用されています。
アセスメントの使い方と文例
「アセスメントを文中でどのように使えばよいかわからない」という方も多いでしょう。具体的な使い方と文例を紹介しますので、参考にしてください。
▼採用や人事にアセスメントを使う例 | |
例文 |
自社に適した人材を採用するため、応募者のアセスメントを実施する |
解説 |
企業が自社求人に応募してくれた人材のスキルや特性を分析し、評価することを表している文例です。 |
▼医療や看護にアセスメントを使う例 | |
例文 |
緊急搬送された患者をアセスメントした結果、熱中症であると判明した |
解説 |
アセスメントは医療現場でも使われます。上記は医療従事者が、患者の状態を分析することを表した文例です。 |
アセスメントと似ている言葉
アセスメントと似ている言葉に「エバリュエーション」「モニタリング」などが挙げられます。
エバリュエーション(evaluation)は「評価・算定」などの意味をもつ単語です。
エバリュエーションは主に、実行した物事を分析して評価する際に使われます。たとえば実行した介護サービスに対して、その内容が良かったか否かを評価するときなどに、エバリュエーションを使うということです。そのため、エバリュエーションは「事後評価」とも呼ばれています。
モニタリング(monitoring)は、「観察・観測・監視」などの意味をもつ単語です。対象を一定期間観察し、変化や状態を把握することを指します。
たとえば、依頼した介護サービスがスタートしてから、終了するまでの間の様子を観察し、定期的に現状を把握することは、モニタリングに当たります。
一方、アセスメントは対象を客観的に分析し、評価することをいいます。アセスメントでは、客観的かつ数値的に対象を分析・評価するケースが多いため、エバリュエーションやモニタリングに比べて、より深い分析が求められるといえるでしょう。
アセスメントの分野別の意味
アセスメントは採用・人事・医療・介護・環境整備など多くの分野で活用されています。ここからは、代表的な分野別の意味を紹介します。
人材アセスメントとは?
人材アセスメントとは、人材の能力や性格特性などを客観的に分析・評価することです。人材アセスメントは、適性検査や心理テストなどのアセスメントツールを使って行われます。
基本的に、第三者機関によって人材を分析・評価するため、社員の主観に頼らない客観的な採用選考や人事評価が可能となります。たとえば、以下のような項目を客観的・数値的に評価することが可能です。
知的能力検査 |
|
性格検査 |
|
組織アセスメントとは?
組織アセスメントとは、組織としての能力や特性などを客観的に分析・評価することです。人材アセスメントとは視点が異なり、個人ではなく組織について詳しく分析します。
組織アセスメントでは、まず組織に所属している社員を客観的・数値的に分析し、組織内にどのような能力やスキルが保有されているか導き出します。そのうえで「組織に不足している能力やスキル」を明確化し、組織強化・改善につなげます。
医療・看護アセスメント
医療や看護におけるアセスメントは、患者の状態を詳しく分析・評価し、適した看護計画を立てたり、最適なケアを実行したりするために活用されています。
医療や看護の現場で、よく使われているアセスメント方法に「SOAP」があります。SOAPとは、主観的・客観的情報から患者の状態を分析・評価し、根拠に基づいて適切な看護計画を立てる方法です。
S(Subject=主観的情報) |
患者の話や訴えから得られた主観的な情報を記録する |
O(Object=客観的情報) |
身体診察・検査などから得られた客観的な情報を記録する |
A(Assessment=評価) |
分析・評価した内容を記録する |
P(Plan=計画) |
Aに基づいた治療の方針や看護計画を記録する |
介護・福祉アセスメント
介護・福祉の分野では、対象者の健康状態や生活状況、要望などを詳しく把握して分析し、最適な介護プランを立てるために、アセスメントが実施されています。
介護・福祉分野のアセスメントに使える評価シートとして有名なのが、厚生労働省による「課題分析標準項目(23項目)」です。生活状況や主訴、コミュニケーション能力、住居環境などの23項目からなるアセスメントシートで、対象者の生活課題を分析して特定することに役立ちます。
環境アセスメント
環境アセスメントは、大きな建設プロジェクトなどの大規模な開発事業を実施する際、周囲の環境にどの程度影響があるかを事前に分析・評価することです。「環境影響評価」とも呼ばれ、自然環境を保護するために役立てられています。
ライフサイクルアセスメント
自然環境を保護するためのアセスメントには、ライフサイクルアセスメント(LCA)もあります。
ライフサイクルアセスメントとは、商品の原材料の調達から、廃棄してリサイクルされるまでのライフサイクルにおいて、環境負荷がどの程度あるかを分析し、評価することです。
ライフサイクルアセスメントを行なうことで、より環境にやさしい商品を製造・販売できるようになります。
リスクアセスメント
リスクアセスメントは、職場における事故や危険を防ぐために行なわれます。職場でどのような事故や危険が起こりうるか事前に分析し、その対策方法を考案します。
リスクアセスメントは、製造業や建設業などの危険が多い業界をはじめとして、さまざまな分野で実施されています。職場で起こりうるリスクを特定し、危険度や有害性に応じて優先順位をつけ、その優先順位にしたがって対策を講じます。
人材アセスメントの目的・メリット
ここからは、企業の採用活動や人事で使われる「人材アセスメント」について解説します。人材アセスメントの目的は「その人がもつ知的能力や性格特性を客観的に分析・評価し、採用選考や組織編成などに活かすこと」です。人材アセスメントの具体的なメリットを3つ紹介します。
人材を客観的に評価できる
人材アセスメントを実施するもっとも大きなメリットは、人材を客観的に分析・評価できることです。本来は目に見えない知的能力・性格特性などの内面を数値的に評価できるようになるため、採用選考や人員配置に役立ちます。
たとえば採用面接を行なうとき、応募者を面接官の主観だけで評価すると、本質を見極められず「採用すべき人材を不採用にしてしまった」などの失敗が起こる恐れがあります。人材アセスメントを行なうことで、そういった採用シーンの失敗を防ぎやすくなるのです。
採用のミスマッチを防止できる
人材アセスメントは、採用のミスマッチを防止するのにも役立ちます。採用のミスマッチとは、企業側と求職者側の認識がお互いにズレたまま採用してしまうことです。採用のミスマッチが生じると、せっかく採用した人材が、内定辞退や早期退職するリスクがあります。
人材アセスメントを採用シーンで活用すると、従来の書類選考や面接だけではわからなかった求職者の内面を数値的に分析・評価できるようになります。結果的に、自社の業務内容や社風に適した人材を採用しやすくなるのです。
採用のミスマッチを防止する方法については、こちらの記事でも詳しく解説していきます。採用のミスマッチ防止にお悩みの方は、ぜひご覧ください。
▼採用ミスマッチの理由とは? 早期離職を防ぐための4つの対策
客観的かつ公平な人事評価ができる
人材アセスメントは人事評価にも効果的です。人事評価をするときに、適性検査などのアセスメントツールを活用すると、従業員一人ひとりが現状もっている知的能力や性格特性を客観的に分析・評価できるようになります。
人材アセスメントで判明した結果とともに、上司やチームメンバーからの評価も掛けあわせて、総合的な評価をすることで、客観的かつ公平な人事評価が可能となるのです。
人材アセスメントの活用方法
人材アセスメントのメリットがわかったところで、具体的な活用方法を見ていきましょう。
採用選考に使う
先にも述べたとおり、人材アセスメントは採用選考で「求職者を客観的な視点で見極める」ために役立ちます。採用選考でよく使われる人材アセスメントツールは適性検査です。
適性検査は、求職者の知的能力や性格、価値観などを数値的に可視化するツール。書類選考を通過後、一次面接の前に受検してもらうのが一般的です。
適性検査の詳しい内容や種類については、こちらの記事で解説しています。採用選考に適性検査の導入を検討している方は、ぜひご覧ください。
▼適性検査とは? 主な目的や実施方法、種類などを徹底解説
人材育成に使う
人材アセスメントを社員の育成に活用するケースもあります。適性検査などの人材アセスメントツールを使うと、社員それぞれの得意・不得意領域が数値的に可視化されるので、「誰の・どんな能力を鍛えるべきか」がわかりやすくなるからです。
社員本人が自分で気づいていなかった得意・不得意領域が判明する場合もあるほか、一人ひとりに合わせた教育プログラムを組みやすくなるメリットもあります。ただやみくもに研修を受けさせたりするよりも、効率よく人材育成できるでしょう。
人員配置・管理職の抜擢に使う
前述のとおり、人材アセスメントは客観的かつ公平な人事評価をするために役立ちます。そのため、人材を適材適所に配置したり、管理職を抜擢したりするシーンにも活用しやすいのです。
人材アセスメントを人員配置・管理職の抜擢に活用したいときは、適性検査などテスト形式のツールだけでなく、「360度評価」などの評価方法も効果的です。「360度評価」とは、評価対象と関わるいろいろな立場の人が、多面的に人材評価を行なうアセスメント方法です。
たとえば、社員に対して「360度評価」を行なう場合は、社員の上司・同僚・部下など、違う立場の人々がそれぞれの視点で対象を評価します。異なる立場からの評価が可視化されるので、「直属の上司だけが評価する」という従来通りのやり方よりも、社員一人ひとりを適した役割に配置しやすくなるでしょう。
人材アセスメントの実施方法やツール
ここからは人材アセスメントの具体的な実施方法や、便利なツールを紹介します。
アセスメント研修
アセスメント研修とは、実際に業務をこなしているときと同じ状況をつくり、その状況下で対象者の言動を観察・分析するものです。アセッサーと呼ばれる評価者が、ディスカッションやプレゼンなどを通して研修の対象者を観察し、評価項目に沿って評価していきます。
業務中と同様の状況で対象者を観察することにより、対象者がもつ本来の能力やスキル、業務への姿勢などを判断できます。
適性検査
適性検査は、対象者の知的能力や価値観、考え方などの内面を数値化・可視化できます。入社後の人材アセスメントだけでなく、入社前に採用選考の一環として活用している企業も多くあります。
適性検査については、以下の記事で詳しく解説しています。具体的な検査内容や種類などを知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
▼適性検査とは? 主な目的や実施方法、種類などを徹底解説
360度評価(多面評価)
360評価(多面評価)とは、対象者の上司・同僚・後輩など業務上関係のある人物が、対象者を多面的に評価する方法です。複数の異なる視点から対象者の能力やスキル、人格などを評価するので、客観的な分析が可能となります。
自己評価と他者から見た評価を比較し、乖離しているポイントを分析することで、対象者の課題点や改善点を明確化することができます。
エニアグラム
エニアグラムとは、人物の性格を下記の9タイプに分類して診断する方法です。ビジネスシーンだけでなく、教育現場や医療カウンセリングなどでも活用されています。
タイプ |
性格分類 |
タイプ1 |
自分なりの基準に則り、正しい間違いのないことをしたい |
タイプ2 |
人の役に立つことで、愛を得たい |
タイプ3 |
成果を出して、賞賛を得たい |
タイプ4 |
自分らしさを表現することで、感動を味わいたい |
タイプ5 |
情報を分析し、物事の本質を見極めたい |
タイプ6 |
責任を果たすことで仲間として認められ、安心したい |
タイプ7 |
いろいろな可能性に挑戦して、人生を楽しみ幸せでいたい |
タイプ8 |
自分の影響力を行使して、存在を感じていたい |
タイプ9 |
他者と融和することで、平和な気持ちでいたい |
引用:日本エニアグラム学会「エニアグラムについて」
エニアグラムは対象者の思考傾向や価値観、考え方、性格などを分析するのに役立ちます。企業においては、職務適正を見極めるための参考になるでしょう。
人材アセスメントの導入手順
続いて、人材アセスメントをどのように導入すればよいか説明していきます。
人材アセスメントの目的を明確化する
まず、人材アセスメントを導入する前に、目的を明確化しましょう。人材アセスメントツールにはさまざまな種類があるため、導入目的が明確でないと、的外れな方法を選択してしまう恐れがあるからです。
自社の目的に適した方法を選ぶことが大切なので、まずは以下のように「何のために人材アセスメントを導入したいのか」洗い出しましょう。
- 採用のミスマッチを防止したい
- 社員を適材適所に配置したい
- 効率よく社員を育成したい
- 管理職に適性のある人材を見極めたい
こういった導入目的を洗い出し、適したアセスメント方法を選択しましょう。
目的に適したツール・評価方法を選ぶ
人材アセスメントの導入目的を明確にしたら、目的に適したツール・評価方法を選んでいきます。人材アセスメントには、主に以下のような方法があります。
ツール・評価方法 |
概要 |
適性検査 |
|
360度評価 |
|
エニアグラム |
|
アセスメント研修 |
|
それぞれの方法ごとに、分析しやすい領域が異なります。目的に応じたアセスメント方法を慎重に検討しましょう。
「初めて人材アセスメントを実施するため何を選べばよいかわからない…」という方には、人材の知的能力・性格・行動特性などを総合的に分析できる適性検査がおすすめです。
エン・ジャパン株式会社が開発した適性検査「TALENT ANALYTICS」は企業の人材見極め精度を向上させてくれます。適性検査の実施にご興味のある方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。
▼エン・ジャパンの適性検査「TALENT ANALYTICS」とは?人材の見極めで悩む方、必見!
アセスメントした結果を目的に活用する
ツールや評価方法を選定し、人材アセスメントを実施したら、結果を目的に活かしましょう。人材アセスメントは、「ツールを使うだけ」では目的を達成したとは言えません。
ツールを使って人材を分析・評価したあと、「その結果にもとづいて採用選考や人事評価を実際に行なって課題を解決する」ことで、初めて導入目的が達成されたと言えるのです。ツールを導入し、各シーンで実際に活用しましょう。
人材アセスメントを実施するときのポイント
最後に、人材アセスメントを実施するときのポイントを4つ紹介します。以下の4点を押さえておくことで、より効果的な人材アセスメントが行なえるでしょう。
自社の評価基準を定める
人材アセスメントを行なうにあたり、自社の評価基準を定めておきましょう。自社の評価基準が明確でないと、「どの領域の数値が高ければ良しとするのか」がわからず、採用選考や人事評価において適性の有無などを判断できないからです。
たとえば採用選考で適性検査を導入する場合、「どんな人材であれば合格とするのか」という採用基準が設定されていないと、検査結果をもとに合否を判断できません。人材アセスメントツールをうまく活用するためには、自社に適した評価基準を設定しておくことが大切なのです。
採用基準の設定方法や手順は、こちらの記事で詳しく解説しています。採用選考に人材アセスメントの導入を検討している方は、あわせてご覧ください。
▼採用基準とは? 人材を見極めるための設定方法や注意点を解説
実施目的を周知させる
人材アセスメントを社員に対して実施するときは、目的をきちんと周知させましょう。実施目的を丁寧に説明した方が、受検者の結果に対する納得感が高まるからです。
また人材アセスメントは、実施するにあたって検査や研修を受けたり、他者からの人材評価を複数受け取ったりします。受検者が慣れないことに不安を感じる恐れがあるので、実施目的をしっかり伝えて、不安感を解消してあげましょう。
実施結果をフィードバックする
人材アセスメントを実施したら、受検者へ結果をフィードバックします。「上司だけが結果を知り、受検者本人には通知されない」という状況になると、受検者本人は時間や手間をかけて人材アセスメントを受けた意味がわからず、不信感を抱いてしまう恐れがあるためです。
人材アセスメントを行なったら受検者にも必ず結果を共有し、「何が得意・不得意なのか」「何の能力を伸ばしていくべきなのか」などをフィードバックしましょう。分析結果を業務目標や課題解決につなげて、受検者をしっかりフォローしていくことが重要です。
継続的に情報収集と効果測定を行なう
人材アセスメントは、1回実施して終わりというものではありません。実施した結果を目的に活用し、「ツール選びや評価基準は適切だったか」などを見直して、改善していく必要があります。
「人材アセスメントツールを使って採用した人材が、きちんと自社に定着しているか在籍期間をチェックする」「採用した人材の活躍度・貢献度をチェックする」などのように、効果測定を行ないましょう。
もし、予想していたほど人材が活躍していないなどの問題が生じている場合は、評価基準やツール選びを見直す必要があるかもしれません。こういった情報収集・効果測定を継続的に行なっていくと、より精度の高い人材アセスメントが実施できるようになります。
まとめ
人材アセスメントとは、「人材の知的能力や性格特性などを客観的に分析・評価すること」です。人材アセスメントは、適性検査や心理テストなどのアセスメントツールを使って行われます。
人材アセスメントの主なメリットは、対象となる人材を多面的に分析・評価するため、主観に頼らない客観的な採用選考や人事評価が可能となることです。採用のミスマッチを防いだり、管理職に適した人材を見極めたりするために活用されています。
人材アセスメントを実施するときは、目的を明確化し、実施目的に適した方法を選ぶことが大切です。社内で評価基準をきちんと設けて、継続的に効果測定を行なっていけば、より精度の高い人材評価が可能となるでしょう。
採用のミスマッチを防ぎ、入社後に活躍・定着する人材を採用したいとお考えの方は、ぜひ『エン転職』をご活用ください。『エン転職』は1000万人の会員を保有する、日本最大級の中途採用向け求人サイトです。
『エン転職』では、求人に「仕事の厳しさ」「向いていない人」という項目を設けることで、早期離職の防止や入社後のミスマッチの軽減を行なっています。
早期離職の原因のひとつは、入社後ギャップ。「思ったよりキツイ…」「求人には書いていなかった…」という不満が退職に繋がります。
あらかじめ仕事の厳しい側面を求人上で伝え、それでも働きたいと思わせる意欲を醸成。こうした取り組みにより、エン転職経由の入社者の定着率は格段に高いとご好評いただいております。
採用でお悩みの際は、以下のエン転職お問い合わせ窓口よりお気軽にご相談ください。
▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。
他にもエン転職には採用を成功に導く様々な特徴があります。エン転職の料金表・パンフレットダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますので合わせてご覧ください。
▼エン転職のサービス紹介サイト