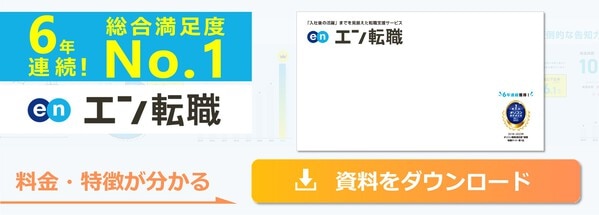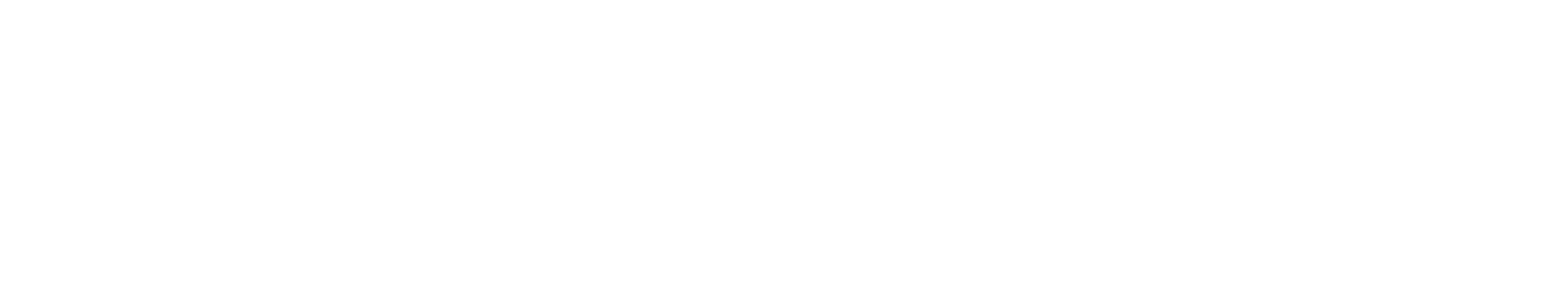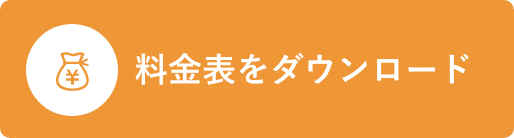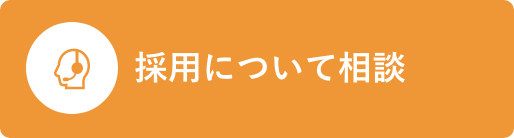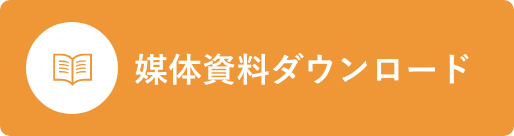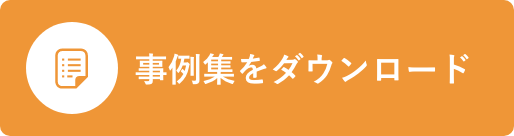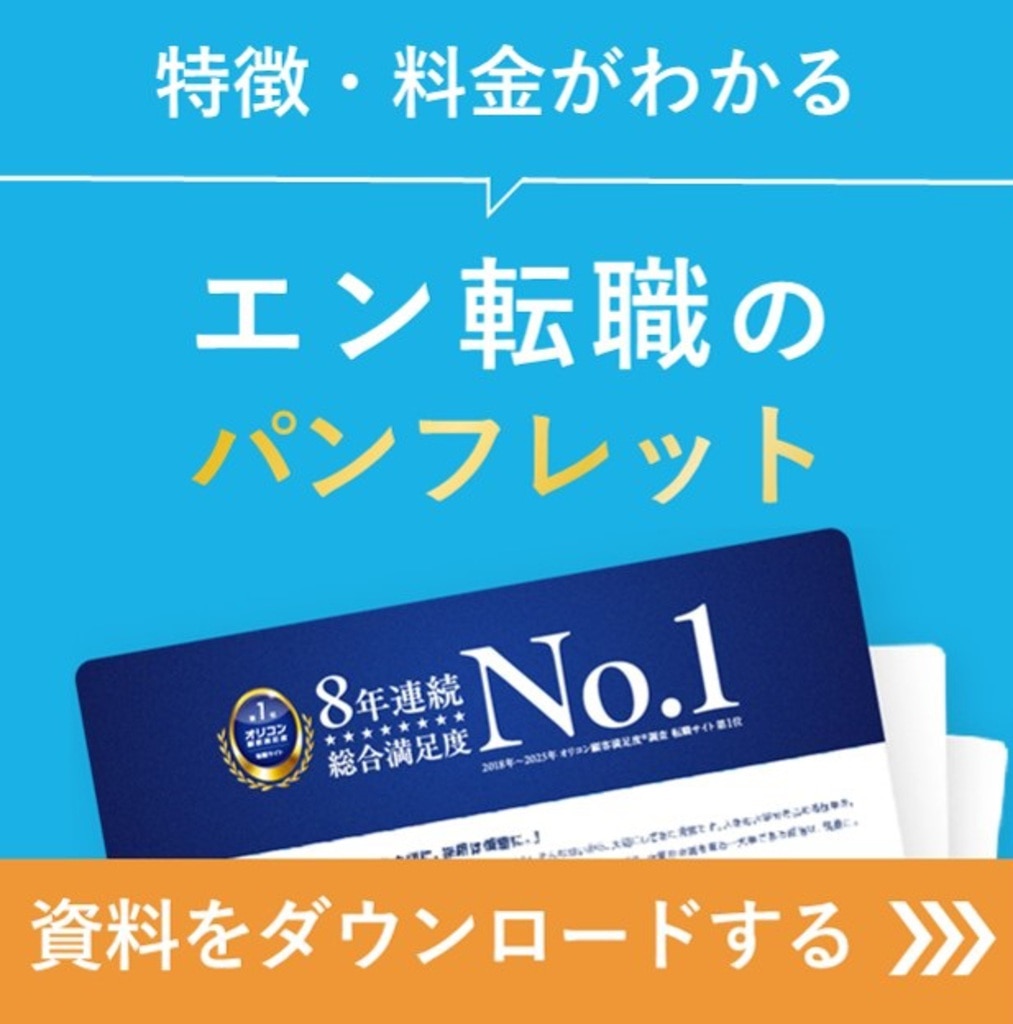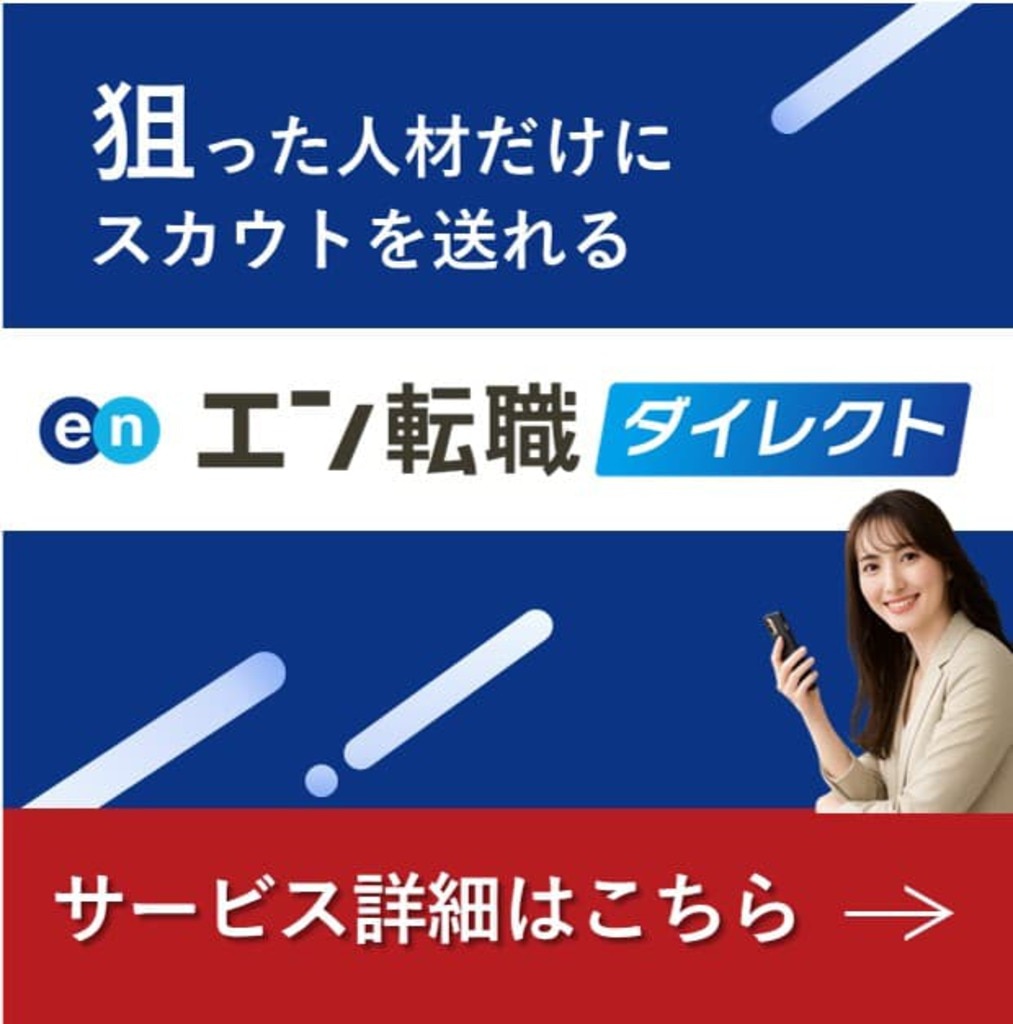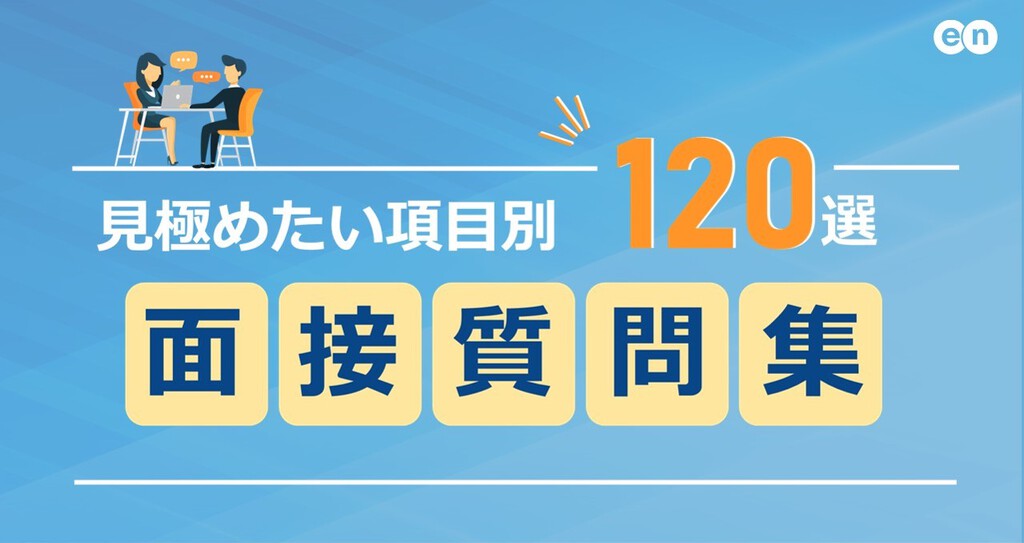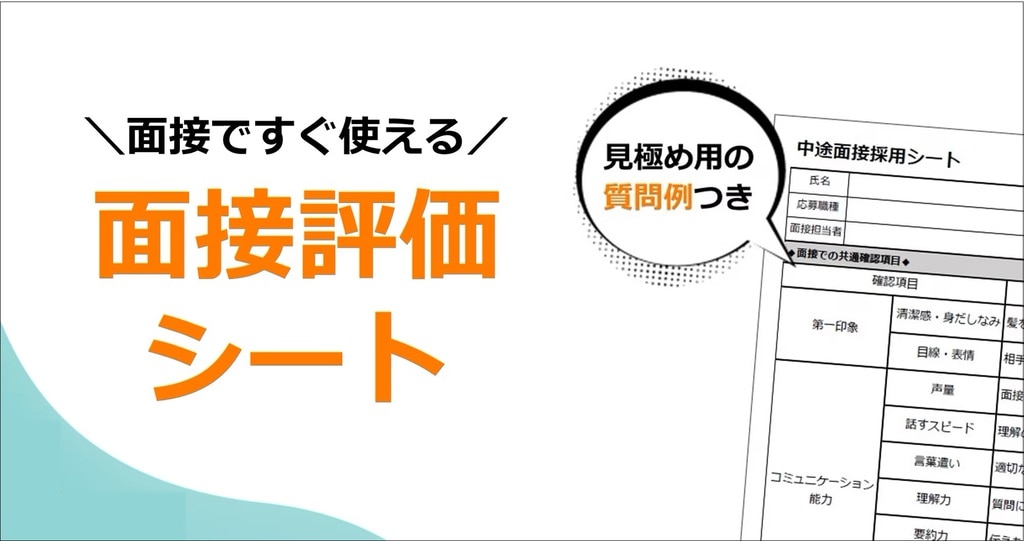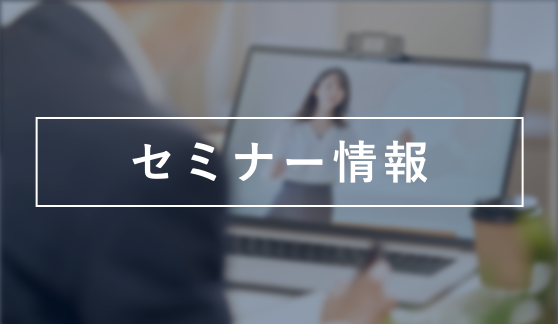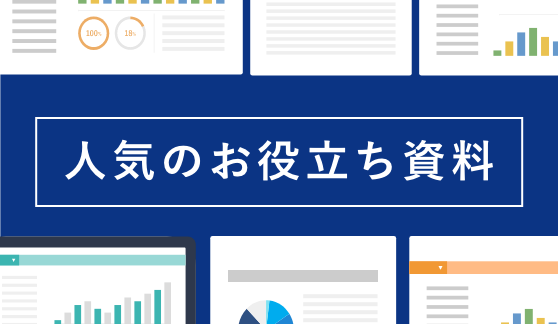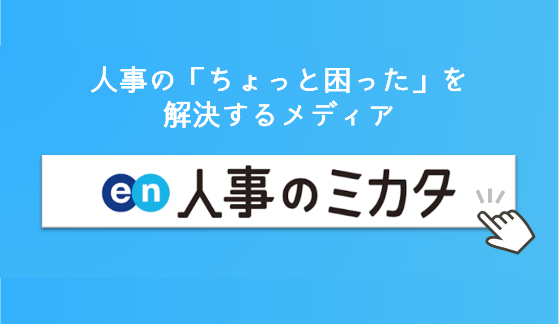人材開発とは? 人材育成との違いや手法、実施時のポイントを解説

人材開発とは、社員一人ひとりの能力を向上させ、パフォーマンスを高める取り組みのことです。人材開発は新入社員・若手社員を主な対象とする人材育成とは異なり、全従業員が対象となります。
人材開発の主な目的は、社員一人ひとりの能力を開発してパフォーマンスを高め、結果的に組織の成果を向上させることです。しかし「具体的に何をすればいいの?」「どう進めていけばいいの?」とお困りの方も多いでしょう。
そこで本記事では、人材開発の具体的な手法や、成功させるためのポイントなどを解説します。「人材開発を行なって社員の能力を向上させたい」とお考えの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.人材開発とは?
- 1.1.人材育成との違い
- 2.人材開発を行なう目的
- 3.人材開発の手法・種類
- 3.1.OJT
- 3.2.Off-JT
- 3.3.自己啓発(SD:Self Development)
- 3.4.タフアサインメント
- 4.人材開発を行なうときのポイント
- 4.1.自社の経営戦略・事業方針に沿わせる
- 4.2.内発的な動機づけを行なう
- 4.3.企業側と社員側で課題や目標を共有する
- 5.まとめ
人材開発とは?
人材開発とは、社員一人ひとりの知識・スキル・能力などを向上させる取り組みのことです。勤続年数に関係なく、全社員が対象となります。
人材開発の主な目的は、社員一人ひとりの能力を開発し、組織全体の成果を高めていくことです。一般的には以下のような内容を実施して、社員のパフォーマンス向上を目指します。
- キャリア開発
- 社内研修・社外研修
- 実習や実務による訓練
- 外部機関によるセミナー
人材育成との違い
人材開発と似ている用語に「人材育成」があります。人材育成も業務に関する知識・スキルなどを社員に習得してもらう点は同じです。
しかし人材育成は、実施するタイミングや対象となる社員の属性などが、人材開発とは少し異なります。下記の表に人材育成と人材開発の違いをまとめましたので、実施するときの参考にしてください。
人材開発 |
人材育成 |
|
主な目的 |
社員一人ひとりの能力開発 個人の能力の最大化 業務知識・スキルの習得 |
業務知識・スキルの習得 |
対象となる社員 |
全社員 |
新入社員や若手社員 |
実施タイミング |
通年で行なわれるケースが多い |
新しい人材が入社したとき |
一般的な実施期間 |
比較的、短期間で実施される |
比較的、長期間で実施される |
なお、人材育成については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
▼人材育成とは? 重要性が高まる背景や基本の進め方を解説
人材開発を行なう目的
人材開発を行なう主な目的には、以下の3点が挙げられます。
- 社員一人ひとりを成長させること
- 企業の経営戦略を実現させること
- 組織としての成長を実現させること
人材開発を実施し、社員一人ひとりが成長すると、組織としてのパフォーマンスも向上します。組織としてパフォーマンスが向上すれば、経営戦略や事業戦略の実現にもつながるため、人材開発は企業の成長に欠かせない取り組みといえるでしょう。
人材開発の手法・種類
ここからは人材開発の具体的な手法や、種類を解説します。人材開発でよく行なわれる手法は、主に以下の4つです。
- OJT
- Off-JT
- 自己開発(SD:Self Development)
- タフアサインメント
それぞれの手法を詳しく見ていきましょう。
OJT
OJTは「On the Job Training」の略称。「実務を通した教育」という意味で使われます。業種・職種・年代を問わず、多くの企業で活用されている教育方法です。
OJTでは実際に業務を遂行するなかで、必要なスキル・ノウハウなどを社員に教育していきます。OJTの対象となる社員の上司や、先輩社員が教育担当となり、あらかじめ計画されたプログラムに沿って進めるケースが多いです。
OJTについては、以下の記事で詳しく解説しています。具体的なメリット・デメリットや、OJTのポイントを知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
▼OJTとは?うまくいくポイントやOJT向きの業務などを徹底解説!
Off-JT
Off-JTは「Off the Job Training」の略称。実務から離れた場で、社員へ行なう教育のことです。OJTでは実務をこなすなかで業務に必要なノウハウなどを実戦形式で学びますが、Off-JTでは研修や講習会などを通して、座学スタイルで知識やスキルなどを学ぶのが一般的です。
Off-JTでは社内研修だけでなく、外部機関から専門家や講師を招いて研修してもらうケースもあります。外部機関に研修を依頼することにより、自社には蓄積されていなかった新しい知識やノウハウを学べるのはメリットです。
自己啓発(SD:Self Development)
自己啓発(SD:Self Development)とは、会社側が用意した教育プログラムにとらわれず、社員が自ら知識の習得や能力向上のために取り組むことです。自己啓発(SD)の例には、主に以下のような取り組みが挙げられます。
- 業務に役立つ資格の取得
- 業務に役立つ検定の受検
- 外部セミナーや通信教育の受講
- 業務に関連するビジネス書籍の購読
自己啓発(SD)はモチベーションの高い社員に適した人材開発手法です。会社側は社員が勉強などの時間をしっかり確保できるようにサポートしましょう。
また、社員が進捗管理をスムーズに行なえるようにするため、定期的に1on1ミーティングを実施してフォローアップするのも効果的です。
タフアサインメント
タフアサインメントとは、あえて能力以上の難しい仕事を任せることにより、社員のスキルアップを図る手法のことです。現状のスキルでは、簡単に達成できない目標を課すことで、対象者の成長を促す効果があります。
具体的には、以下のような取り組みが挙げられます。
- プロジェクトリーダーを任せる
- より大きな部署の管理職に任命する
- 新しいプロジェクトの立ち上げメンバーに抜擢する
タフアサインメントは、社員の成長機会をつくるために有効な手法ですが、過剰な負荷とならないよう注意しなくてはなりません。社員に過剰なプレッシャーや業務負担を与えると、そのストレスが離職の原因となる可能性があるためです。
タフアサインメントを行なうときは、あらかじめ社員の意向を確認し、本人の了承を得たうえで実施しましょう。また、実施中も密にコミュニケーションをとり、対象の社員をこまめにフォローアップするように気を付けましょう。
人材開発を行なうときのポイント
最後に、人材開発を行なうときのポイントを2つ解説します。
自社の経営戦略・事業方針に沿わせる
人材開発の主な目的は、社員一人ひとりの能力を開発して生産性を高め、組織としてのパフォーマンスも向上させることです。
人材開発はあくまでも、経営戦略を実現させるために行なう取り組みなので、実施するときは自社の経営方針に沿った開発計画を立てる必要があります。
やみくもに社員個人のスキルアップを図るだけでは、組織としての力を高めることはできません。自社の戦略や方針に沿った人材開発を行ない、経営における課題を解決できるよう、マネジメント層とも人材開発計画をすり合わせたうえで実施しましょう。
内発的な動機づけを行なう
人材開発において、どのような状態をゴール(目標達成)とするかは、社員によりさまざまです。追いかける目標や目指す姿が、社員一人ひとり違うため、個人の内発的な動機を大切にして人材開発を行なう必要があります。
人材開発を実施するときは、「●●を習得したい」「●●な人材になりたい」「●●のようなキャリアを形成したい」といった社員一人ひとりの内発的な動機を尊重しましょう。
企業側と社員側で課題や目標を共有する
人材開発を実施するときは、以下のような点に注目し、社員側と企業側で課題・目標・行動の仕方などを共有できるように心がけましょう。
- 企業と社員の間にある認識のギャップを把握する
- 企業と社員で改善すべき課題を正確に把握する
- 社員に求める成果と行動の仕方を明確化する
- 自身のキャリア像を社員が振り返る場をつくる
- キャリアの複線化が可能な人事・教育制度をつくる
まとめ
人材開発の意味や具体的な手法、成功させるためのポイントなどを解説しました。人材開発とは、社員一人ひとりの知識・スキル・能力などを向上させ、結果的に組織としてのパフォーマンスを高める取り組みのことです。
人材開発に注力することにより、経営戦略・事業戦略を実現できる可能性が高くなるため、多くの企業で実施されています。
また人材開発には、社員の定着率を高められるメリットもあります。仕事を通して社員一人ひとりの成長を図り、望んだキャリアの実現やスキルアップができるようになれば、自社での活躍率向上も期待できるでしょう。
なお、入社後に定着・活躍する人材を確保したい場合は、採用の時点で自社に適した人材からの応募を集めるのも効果的です。「自社に定着・活躍する人材を採用したい」とお考えの方は、ぜひ『エン転職』をご活用ください。
エン転職は1000万人の会員を保有する、日本最大級の中途採用向け求人サイトです。エン転職では、求人に「仕事の厳しさ」「向いていない人」という項目を設けることで、早期離職の防止や入社後のミスマッチの軽減を行なっています。
早期離職の原因のひとつは、入社後ギャップ。「思ったよりキツイ…」「求人には書いていなかった…」という不満が退職に繋がります。
エン転職では仕事の厳しい側面をあらかじめ求人上で伝え、それでも働きたいと思わせる意欲を醸成。こうした取り組みにより、エン転職経由の入社者の定着率は、格段に高いとご好評いただいております。
採用でお悩みの際は、以下のエン転職お問い合わせ窓口より、お気軽にご相談ください。
▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。
ほかにも『エン転職』には採用を成功に導く様々な特徴があります。『エン転職』の料金表・パンフレットダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますのであわせてご覧ください。
▼エン転職のサービスページ