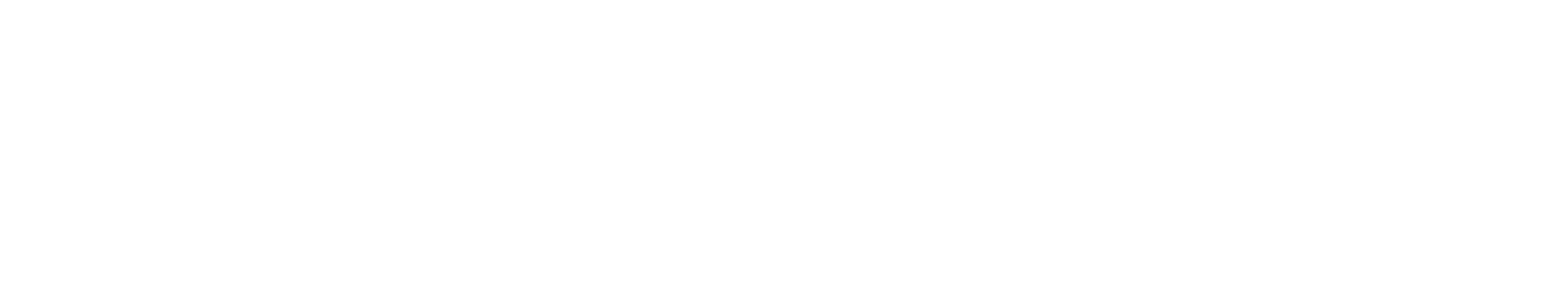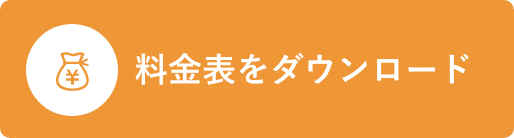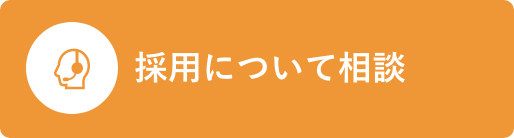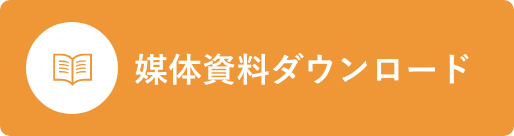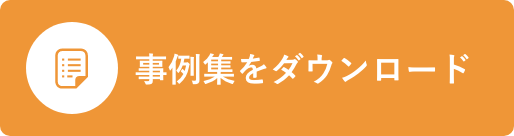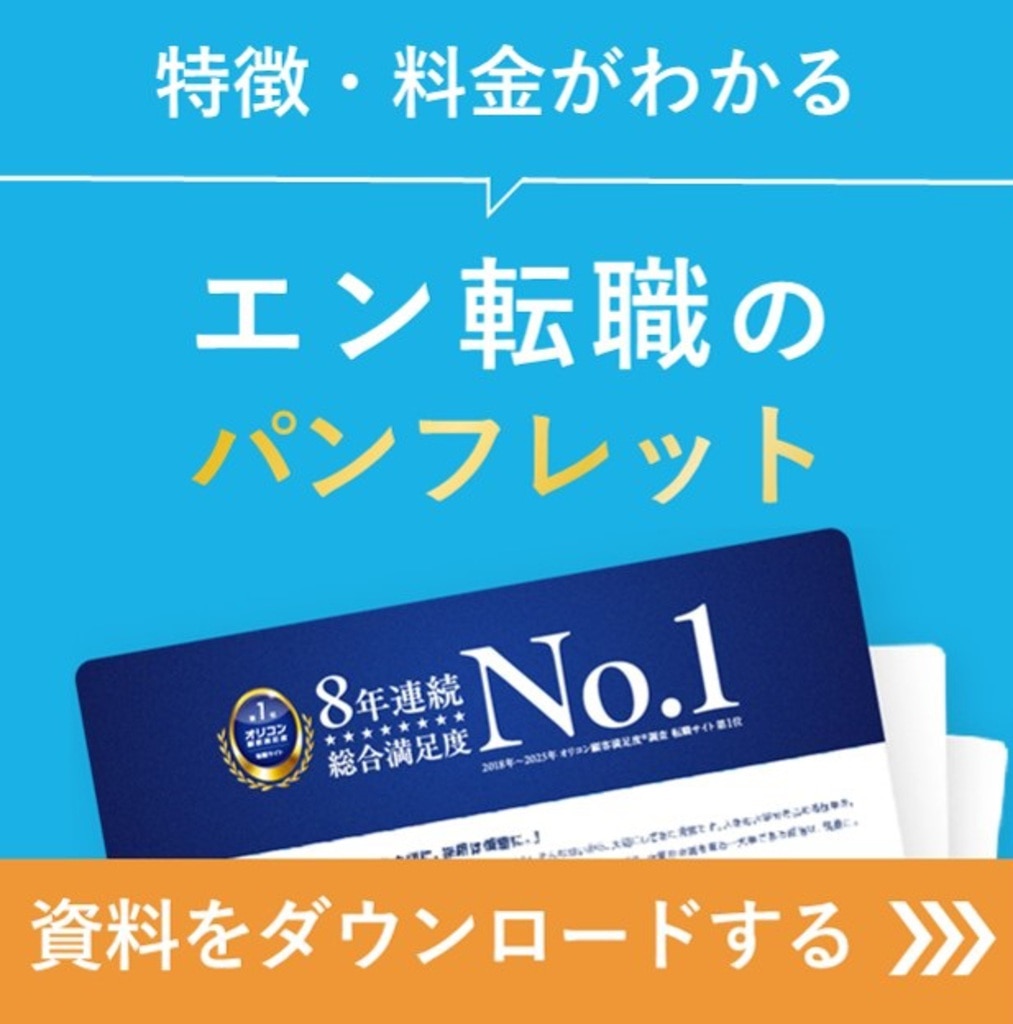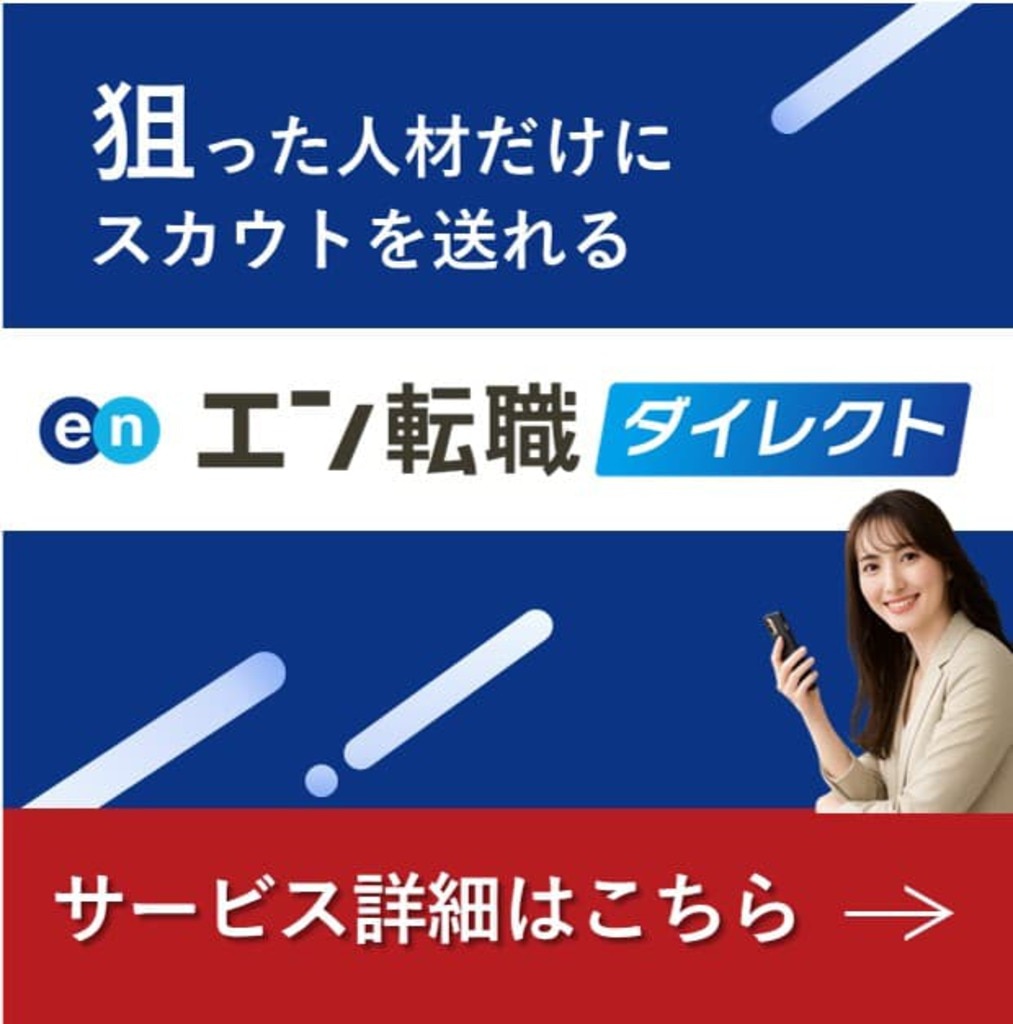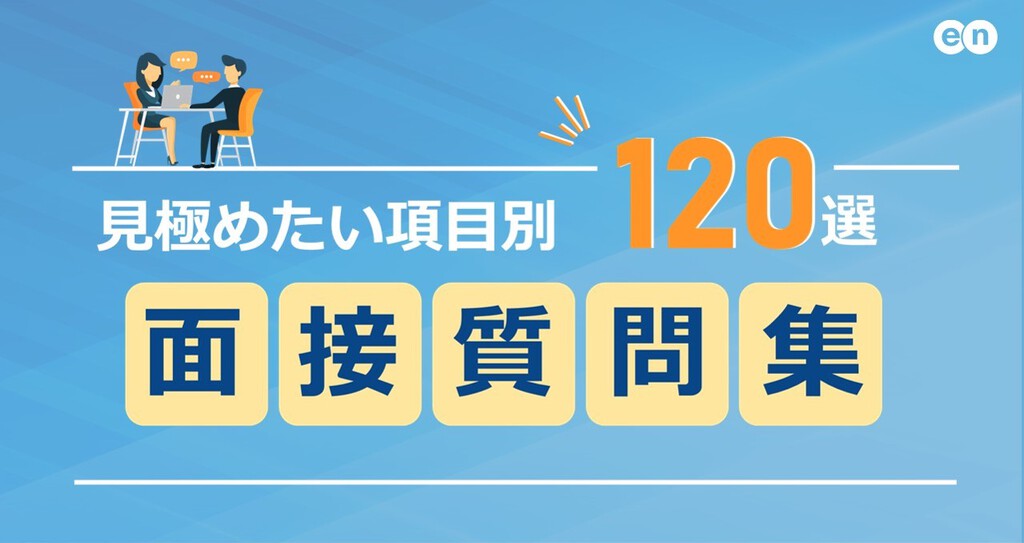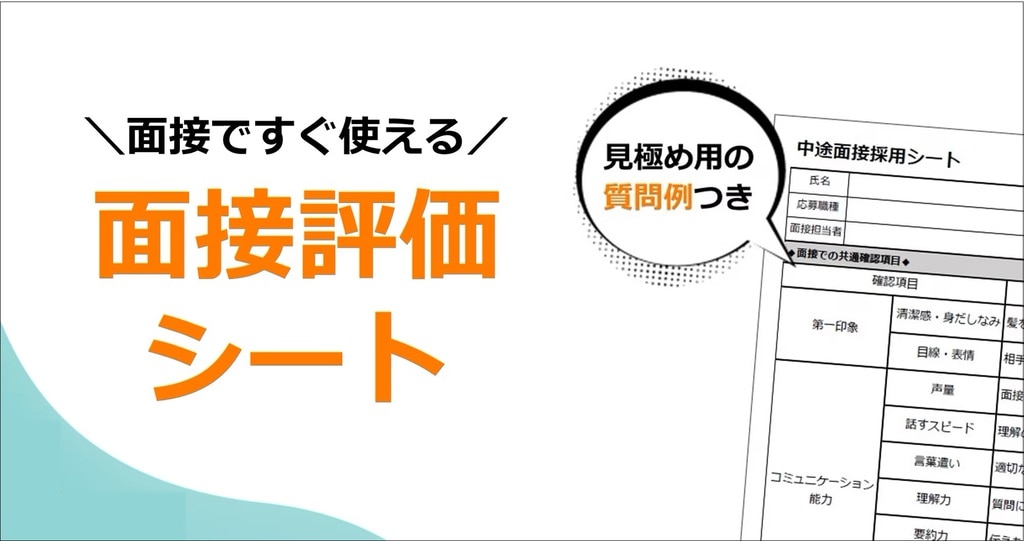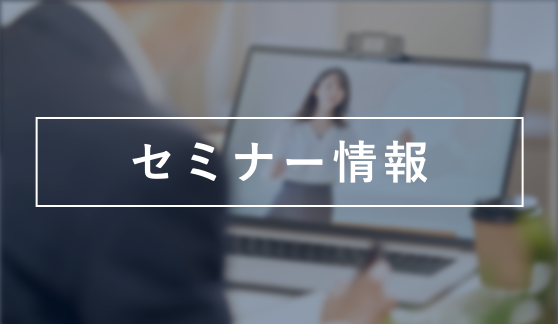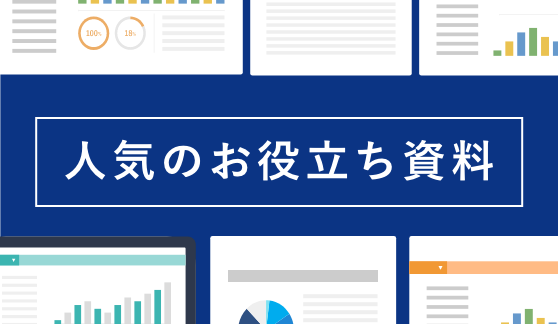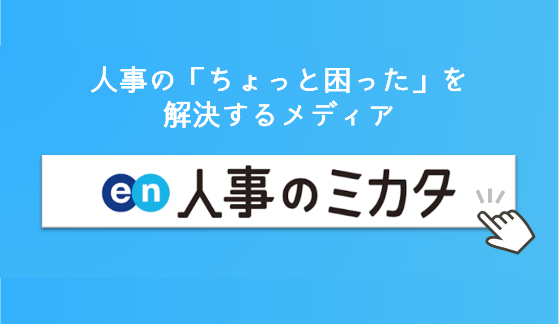人材ポートフォリオとは?重要な理由や作り方、活用方法をわかりやすく解説
企業の競争が激化する現代社会において、優秀な人材の獲得と定着は極めて重要です。そのために注目されているのが「人材ポートフォリオ」です。この記事では、人材ポートフォリオの基本から効果、作成方法、そして採用プロセスでの活用方法までを詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.人材ポートフォリオとは?
- 2.人材ポートフォリオが重視されている理由
- 3.人材ポートフォリオの効果
- 3.1.1. 候補者の専門性を詳細に理解
- 3.2.2. 選考プロセスの効率化と深化
- 3.3.3. 候補者の成果と能力を詳細に検証
- 3.4.4. ターゲット設定とカスタマイズ
- 4.人材ポートフォリオの作り方
- 4.1.作成する目的や方向性を明確化する
- 4.2.自社に必要な人材タイプを分類する
- 4.3.分類したタイプに社内の人材を当てはめる
- 4.4.社内の人材に過不足がないか分析する
- 4.5.余剰/不足しているタイプをどう解消するか考える
- 5.人材ポートフォリオを作成するメリット
- 5.1.適材適所の人材配置が可能になる
- 5.2.社員一人ひとりに適したキャリア支援ができる
- 5.3.人材数や人件費を把握して組織最適化できる
- 6.人材ポートフォリオを作成するときの注意点
- 7.人材ポートフォリオの戦略的な活用方法
- 7.1.1. ポートフォリオの収集と整理
- 7.2.2. 評価と選別のプロセス
- 7.3.3. カスタマイズとターゲティング
- 7.4.4. 選考プロセスへの活用
- 7.5.5. 持続的な更新とフィードバック
- 8.人材ポートフォリオを採用に活かすポイント
- 8.1.1. スキルマッチングの向上
- 8.2.2. 面接や選考の強化
- 8.3.3. 経歴の透明性と信頼性の向上
- 8.4.4. ポジションへの適合度を確認
- 9.まとめ
人材ポートフォリオとは?
人材ポートフォリオとは、企業における人的資本の構成内容を整理し、可視化したものです。人的資本とは、企業に在籍する人材のことを指します。
人材ポートフォリオを作成すると「社内のどこに(部署・支店・役職など)/どのような特性の人材が(能力・スキル・知識レベル・職種など)/どのくらい在籍しているのか(人数・社歴)」が具体的にわかります。
人材ポートフォリオは、自社に在籍している人材の構成内容を可視化できるため、人材配置や人材育成、人材採用などに役立ちます。
自社にどのような人材が在籍しているのか把握し、不足している人材を新たに採用したり、人材の特性に適した部署へ配属したりすることが可能となるため、人材ポートフォリオを活用することで組織最適化につながるでしょう。
人材ポートフォリオが重視されている理由
近年、人材ポートフォリオが重視されている理由には、次の2点が挙げられます。
人材版伊藤レポートによる「人的資本経営」の言及
人材版伊藤レポートとは、2020年に経済産業省が発表した「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~人材版伊藤レポート~」のことです。この報告書には、企業が継続的に経済成長していくための人材戦略について記載されています。
2022年には、同報告書の内容を深掘りした「人材版伊藤レポート2.0」が発表されました。そこで記載された人材戦略のひとつに「人的資本経営」という経営方法があります。
「人的資本経営」とは、企業に在籍する人材を資本と捉えて投資し、企業価値の向上につなげる経営方法のことです。人的資本経営を行なうには、各企業がどのような人材(=資本)を保有しているか明確に可視化する必要があります。
人材ポートフォリオは、この人的資本経営における人材(=資本)可視化に有効であるため、作成する企業が増えているのです。
ISO30414により人的資本の情報開示が義務化
ISO30414とは、国際標準化機構(ISO)によって2018年12月に出版された、人的資本の情報開示を行なうための国際的ガイドラインです。「人的資本の情報開示」とは、企業の人材育成や人材戦略などの取り組みについて、外部へ公表することを指します。
2020年8月、このISO30414の影響を受けて、米国で上場企業を対象に人的資本の情報開示が義務化されました。国際的なガイドラインが制定され、米国で義務化が進んだことにより、日本国内でも人的資本を情報開示する潮流が強まっています。
自社の人的資本を情報開示するためには、保有する人材の情報を洗い出して整理する必要があります。そのため人材ポートフォリオを作成し、人的資本の正確な把握を試みる企業が、増加傾向にあるのです。
人材ポートフォリオの効果
前述の通り、人材ポートフォリオは、企業が採用活動をより戦略的に進めるための重要な要素となります。その効果を最大限に引き出すことで、企業側は優れた人材を発見し、選考プロセスを効率化することができます。以下では、人材ポートフォリオの具体的な効果について詳しく説明します。
1. 候補者の専門性を詳細に理解
人材ポートフォリオは、候補者の専門性やスキルセットを詳細に理解するための貴重なツールです。
履歴書や面接だけでは把握しきれない、個々のスキルや実績、プロジェクト経験などが詳細に示されることで、候補者の専門性を客観的かつ総合的に把握できます。これにより、求めるスキルセットや経験に適合する候補者を正確に選別することが可能です。
2. 選考プロセスの効率化と深化
人材ポートフォリオを活用することで、選考プロセスの効率化と深化が実現します。ポートフォリオに記載された詳細な情報を基に、初期の選別段階から候補者のスキルや実績を評価できるため、無駄な面接や選考を減少させることができます。
また、面接や選考試験の際にポートフォリオの情報を活用することで、より深い洞察を得ながら選考を進めることができます。
3. 候補者の成果と能力を詳細に検証
人材ポートフォリオでは、候補者の実績や成果を定量的なデータとして示すことができます。具体的なプロジェクトでの成果物や数値データ、リーダーシップの発揮などが記載されている場合、企業側はこれを基に候補者の能力や貢献度を詳細に検証できます。
数値データを通じた評価は、より客観的な判断を可能にし、正確な評価・人員配置を行う手助けとなります。
4. ターゲット設定とカスタマイズ
人材ポートフォリオは、企業側が求めるスキルや特性に合致する候補者をターゲットとして絞り込む際に役立ちます。特定のスキルや実績を持つ候補者を見つけることが容易であり、ポジションやプロジェクトに合致する候補者の特定が迅速に行なえます。
さらに、候補者のポートフォリオをカスタマイズして企業のニーズに合わせた情報を強調することで、ターゲット設定をさらに精緻化することが可能です。
人材ポートフォリオの効果を最大限に引き出すことで、企業はより優秀な候補者を発見し、選考プロセスをより効果的に進めることができます。
候補者の専門性を詳細に理解し、選考プロセスの効率化と深化、能力と成果の詳細な検証、ターゲット設定の精緻化を通じて、企業側の採用活動を戦略的に強化できるでしょう。
人材ポートフォリオの作り方
ここからは、人材ポートフォリオの作り方を5つのステップで解説します。初めて人材ポートフォリオを作るという方は、以下の基本的な手順に沿って 作成を進めるとよいでしょう。
作成する目的や方向性を明確化する
まずは、自社で人材ポートフォリオを作成する目的と、要件を明確化しましょう。
- 何のために人材ポートフォリオを作成するのか?
- 人材ポートフォリオを何に活用したいのか?
上記のような観点から、自社の目的を明確化させ、人材ポートフォリオを作成するときの方向性を定めましょう。
なお、人材ポートフォリオを作成するときは、自社の事業計画や経営ビジョンと照らし合わせながら、目的を決めることが重要です。そのため、現場の管理職だけでなく、経営層とも話し合って作成を進めるのが望ましいといえます。
自社に必要な人材タイプを分類する
人材ポートフォリオを作成する目的が定まったら、人材をタイプ別に分類します。事業計画や経営ビジョンと照らし合わせながら、「自社にはどのような人材タイプが必要で、現状はその人材タイプがどのくらい不足/余剰しているのか」を明確化させましょう。
人材タイプの分類方法には、いくつかやり方がありますが、縦軸と横軸で人材を4パーンに分けるフレームワーク(四象限マトリクス)を利用するのが一般的です。
たとえば、事業を行なううえで必要な仕事に「個人で進める仕事/チームで進める仕事」と「クリエイティブ/ルーティンワーク」がある場合は、縦軸・横軸を以下のように設定して、必要な人材タイプを分析します。
- 縦軸:個人で進める仕事/チームで進める仕事
- 横軸:クリエイティブ(新しい物事を創造する仕事)/ルーティンワーク(既存の仕組みを運用する定型業務)
自社に「個人で進める仕事×クリエイティブ」に当てはまる業務がある場合は、クリエイティブな業務をひとりで粛々と進められるような、「発想力があり自走できるタイプの人材」を確保しなくてはいけません。
また、「個人で進める仕事×ルーティンワーク」に当てはまる業務がある場合は、決められたルールに従って「ひとりで正確に作業できる人材」を確保する必要があるでしょう。
なお人材のタイプ分けは、上記のように業務内容で分類する方法のほか、人材の志向性によって分類する方法もあります。たとえば以下のようなフレームの分け方です。
- 縦軸:組織志向/個人志向
- 横軸:クリエイティブ/ルーティンワーク
「組織志向×クリエイティブ」には組織を新たに創造できる人材、つまり「組織のマネジメントができる人材」が当てはまるでしょう。
その逆に「個人志向×クリエイティブ」には、「専門性の高いエキスパート人材」が当てはまります。どのような分類方法が適しているかは、企業の事業内容や経営方針などにより異なるので、自社にどのような人材が必要なのかを考え、適した分類方法で人材をタイプ分けしましょう。
分類したタイプに社内の人材を当てはめる
自社に必要な人材タイプを分類したら、社内に在籍している人材を当てはめていきます。この時、なるべく客観的な根拠に基づく判断で、各タイプへ当てはめていくことが大切です。評価者の主観だけで社内の人材をタイプ分けしないよう気を付けましょう。
自社の従業員を人材タイプに当てはめるときは、適性検査や360度評価(多面評価)などのアセスメントをきちんと行なって、客観的な分析のもとタイプ分けするのがオススメです。客観的な根拠をもとにタイプ分けしたほうが、従業員の納得感も高まります。
なお、アセスメントについては、以下の記事で詳しく解説しています。人材の客観的な評価方法などを知りたい方は、ぜひあわせてご覧ください。
▼アセスメントとは? 意味や使い方、導入手順などをわかりやすく解説
社内の人材に過不足がないか分析する
社内の人材を各タイプへ当てはめていくと、自社の人材構成における過不足が見えてきます。
たとえば「ルーティンワークが得意な人材は多いが、クリエイティブな業務が得意な人材は少ない」というように、自社が抱えている人材のうち、人数が不足しているタイプまたは多すぎるタイプがわかってくるのです。
自社に必要な人材タイプのうち、どのようなタイプが不足しているのか/多すぎるのかを具体的に洗い出しましょう。
余剰/不足しているタイプをどう解消するか考える
自社が抱えている人材タイプのうち、不足しているタイプ/余剰しているタイプなどが判明したら、それらに対する解消策を考えていきます。たとえば、以下のような方法が挙げられるでしょう。
問題点 |
解消方法 |
|
不足している人材タイプがある |
●人材採用 |
●人材育成 | |
|
余剰している人材タイプがある |
●退出や解雇 |
●人事異動 |
ただし「解雇・遠方への異動」などの極端なやり方を強行しないように注意しましょう。無理な解雇や異動を行なうと、従業員から反発を招く可能性があります。
人材ポートフォリオを作成する目的は、あくまでも社内の人的資本を正確に把握し、組織の最適化を図ることです。
「適材適所で働ける人材を増やすために作成する。組織改善のために異動を実施するときは、従業員に適切なスキルアップを目指してもらう」という意識をもち、従業員一人ひとりがポテンシャルを発揮できることを重視して取り組みましょう。
人材ポートフォリオを作成するメリット
続いて、人材ポートフォリオを作成するメリットについて解説します
適材適所の人材配置が可能になる
人材ポートフォリオを作成することにより、自社に在籍している人材の特性や、自社の人材構成を詳しく把握できるようになります。
従業員一人ひとりの得意/不得意分野や志向性などを理解したうえで、どのような人材をどこへ配属すべきか考えやすくなるため、適材適所の人材配置が可能となります。
社員一人ひとりに適したキャリア支援ができる
社員一人ひとりに適したキャリア支援ができることも、人材ポートフォリオを作成するメリットです。人材ポートフォリオを作ることにより、「社員の得意/不得意分野・キャリア形成への価値観」などを企業側が把握できるようになります。
その結果「社員のキャリア形成の希望に適した教育機会を与えやすくなる」「社員の適性に沿った業務を割り振りやすくなる」などの効果が得られます。一人ひとりに適したキャリア支援を実施できることにより、社員のエンゲージメントも高まるでしょう。
人材数や人件費を把握して組織最適化できる
人材ポートフォリオを作成するメリットには、自社の人材数や人件費を把握しやすくなる点も挙げられます。人材数や人件費を正確に把握できれば、「どのポジションの人件費が多すぎるのか」「どの業務に人材が足りていないのか」といった人材の過不足がわかりやすくなるからです。過不足に応じて人員を調整すれば、組織を最適化させられるでしょう。
人材ポートフォリオを作成するときの注意点
人材ポートフォリオは、作成して終わりではありません。作成後、常に最新の情報を反映させることで、その価値を最大限に引き出すことができます。ここからは、人材ポートフォリオを作成・運用するにあたり注意すべきポイントを解説します。
1. 最新の実績やスキルを反映させる
人材ポートフォリオは、個人の成長や新たな実績に合わせて定期的に更新することが重要です。新しいプロジェクト経験やスキル習得、資格取得などがある場合には、それを追加してポートフォリオをアップデートしましょう。
これにより、最新の情報を提供し、従業員のが何を経験し、何を能力として身に着けているのかを常に把握することができます。
2. パフォーマンスマネジメントを実施する
パフォーマンスマネジメントとは、直属の上司や人事担当者が、自社社員のパフォーマンスを上げるために実施するマネジメントのことです。直属の上司や人事担当者が、マネジメント対象の社員と共に業務目標を設定し、実績を振り返りながらフィードバックを行ないます。
人材ポートフォリオは、作成して終わりとするのではなく、このパフォーマンスマネジメントに活かすことが重要です。人材ポートフォリオをもとに、社員の特性へ理解を深め、成長点や課題点などをフィードバックし、社員のパフォーマンスを最大化させましょう。
3.従業員本人の声や現場の声も考慮する
人材ポートフォリオは、人員配置や人材育成に役立ちます。しかし会社側がデータだけを頼りに、従業員本人や業務現場の声を無視して、一方的に人員配置・人材育成をするのは控えましょう。
データに基づいているからといって、従業員本人や現場の声を無視して人員配置・人材育成を行ななう、モチベーションの低下につながる恐れがあります。意見や希望が反映されない状態が続くと、従業員が離職する可能性もあるため、ある程度は従業員本人や現場の声を考慮しましょう。
人材ポートフォリオの戦略的な活用方法
人材ポートフォリオを有効に活用するためには、適切な運用フローを策定し、戦略的に活動することが重要です。以下では、企業が人材ポートフォリオを活用する際の運用フローについて解説します。
1. ポートフォリオの収集と整理
運用フローの第一歩は、従業員から人材ポートフォリオを収集し、適切に整理することです。従業員に対してポートフォリオの提出を促し、提供された情報をカテゴリ別に整理します。
スキル、実績、プロジェクトなどを詳細に整理することで、企業がポートフォリオの内容を簡単に把握できるようにします。
2. 評価と選別のプロセス
整理されたポートフォリオを基に、評価と選別のプロセスを実施します。求めるスキルや要件に適合するポートフォリオを評価し、最適な候補者を選別します。実績の詳細や数値データなどを活用して客観的な判断を行い、選考プロセスを効率化します。
3. カスタマイズとターゲティング
選択されたポートフォリオは、応募するポジションやプロジェクトに合わせてカスタマイズされます。特定のスキルや実績を強調したり、企業のニーズに合わせた情報を加えたりすることで、個々の情報に最適化されたポートフォリオを作成します。これにより、要件に合致した候補者をより具体的に評価できます。
4. 選考プロセスへの活用
ポートフォリオは、選考プロセスの一環としても活用できます。面接や選考試験の際に、ポートフォリオを通じて候補者のスキルや実績を把握し、深い理解を得ることができます。ポートフォリオを活用した選考プロセスは、候補者の適性評価を豊富な情報を基に行う手助けとなります。
5. 持続的な更新とフィードバック
運用上では、候補者がポートフォリオを定期的に更新することが奨励されます。新たなスキルや実績の追加、成長のアップデートなどを継続的に行うことで、常に最新の情報を提供できる状態を維持します。
また、選考プロセスや採用後の成果に基づいたフィードバックを通じて、ポートフォリオの質を向上させる努力を促進します。
運用フローを通じて人材ポートフォリオを戦略的に活用することで、企業は選考プロセスを効果的に強化し、最適な候補者の発見や成長を支援できます。持続的な更新と絶え間ない改善を通じて、人材ポートフォリオの運用を最大限に活かすことが重要です。
人材ポートフォリオを採用に活かすポイント
人材ポートフォリオは、企業側が新たな才能を発見し、採用プロセスを効果的に強化するための有力なツールとなり得ます。以下では、人材ポートフォリオを採用に活かすための方法と具体的なアプローチについて解説します。
1. スキルマッチングの向上
人材ポートフォリオに記載されたスキルや実績を通じて、候補者の能力や専門性をより詳細に把握することができます。企業側は求めるスキルや要件に合致する候補者を見つける際に、ポートフォリオの情報を活用できます。特に、具体的なプロジェクトの経験や成果を数値や事例と共に示すことで、候補者のスキルマッチングをより精度高く行うことが可能です。
2. 面接や選考の強化
人材ポートフォリオは、面接や選考試験の際に有益な補完情報となります。面接官や選考担当者は、ポートフォリオを通じて候補者の経歴や実績にアクセスし、質問や評価基準をより具体的に設定することができます。これにより、選考プロセスの質と深さを向上させ、候補者の適性を総合的に評価する手助けとなります。
3. 経歴の透明性と信頼性の向上
人材ポートフォリオは、候補者の経歴や実績を透明かつ信頼性の高い形で提供する手段として機能します。正確な情報提供を通じて、企業側は候補者の経歴やスキルに対する信頼を築き上げることができます。これにより、選考プロセスの透明性を向上させ、より有望な候補者を選定する基準として活用できます。
4. ポジションへの適合度を確認
人材ポートフォリオは、候補者が応募するポジションへの適合度を確認する際にも役立ちます。
ポートフォリオの情報を通じて、候補者の過去のプロジェクト経験や成果を評価し、ポジションに求められる役割やスキルとのマッチング度を判断することができます。これにより、企業はポジションへの適切な候補者をより的確に選択することができます。
総括すると、人材ポートフォリオは採用プロセスにおいて有益なツールとなり得ます。スキルマッチングの向上や面接強化、透明性の向上など、ポートフォリオの情報を活用することで、企業はより質の高い選考プロセスを実現し、最適な候補者の発見をサポートできるでしょう。
まとめ
以上で、人材ポートフォリオの基本的な理解から、効果、作成方法、そして採用プロセスでの活用方法までをご紹介しました。
採用活動においては人材ポートフォリオを活用できますが、作成した人材ポートフォリオの内容が適切に伝わり、候補者が入社後に活躍していただけなければ目的は果たせません。
入社後に活躍・定着する人材を採用したいとお考えであれば、ぜひ『エン転職』をご活用ください。『エン転職』は日本最大級となる1000万人の会員を保有する、中途採用向け求人サイトです。
『エン転職』では、求人に「仕事の厳しさ」「向いていない人」という項目を設けることで早期離職の防止や入社後のミスマッチの軽減を行なっています。
早期離職の原因のひとつは、入社後ギャップ。「思ったよりキツイ…」「求人には書いていなかった…」という不満が退職に繋がります。
あらかじめ仕事の厳しい側面を求人上で伝え、それでも働きたいと思わせる意欲を醸成。こうした取り組みにより、エン転職経由の入社者の定着率は格段に高いとご好評いただいております。
採用でお悩みの際は、以下のエン転職お問い合わせ窓口よりお気軽にご相談ください。
他にも『エン転職』には入社後の活躍・定着を促進する機能が多数。詳細はこちらの記事で解説しています。
▼エン転職の特徴を分かりやすく整理|採用成功できるヒミツを大公開