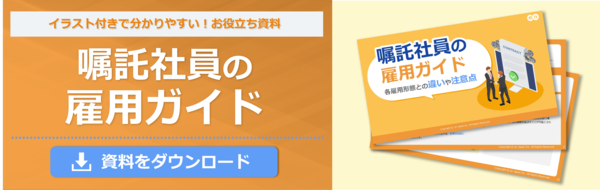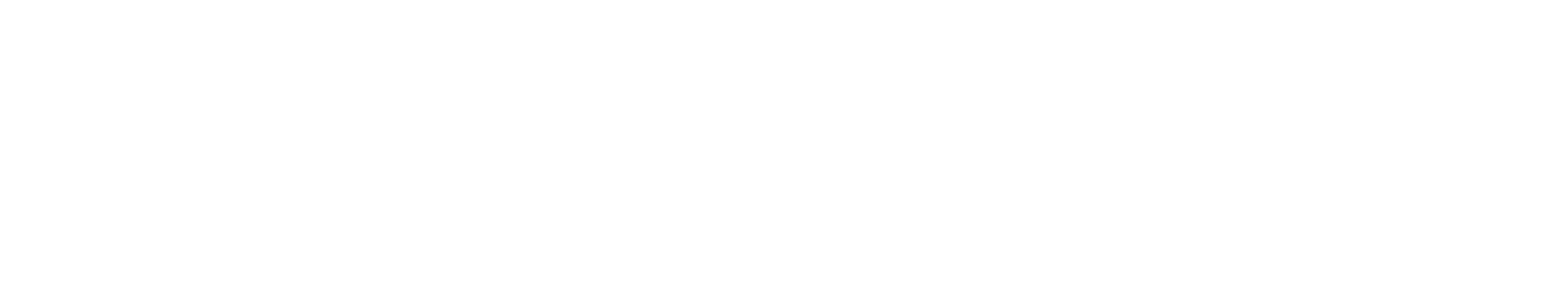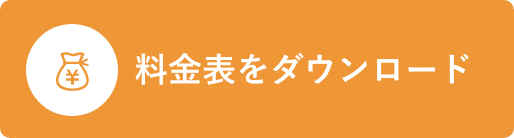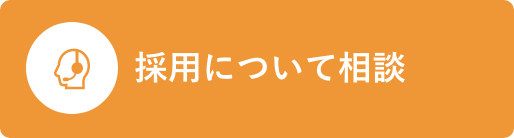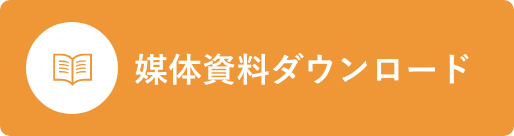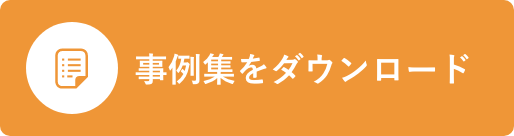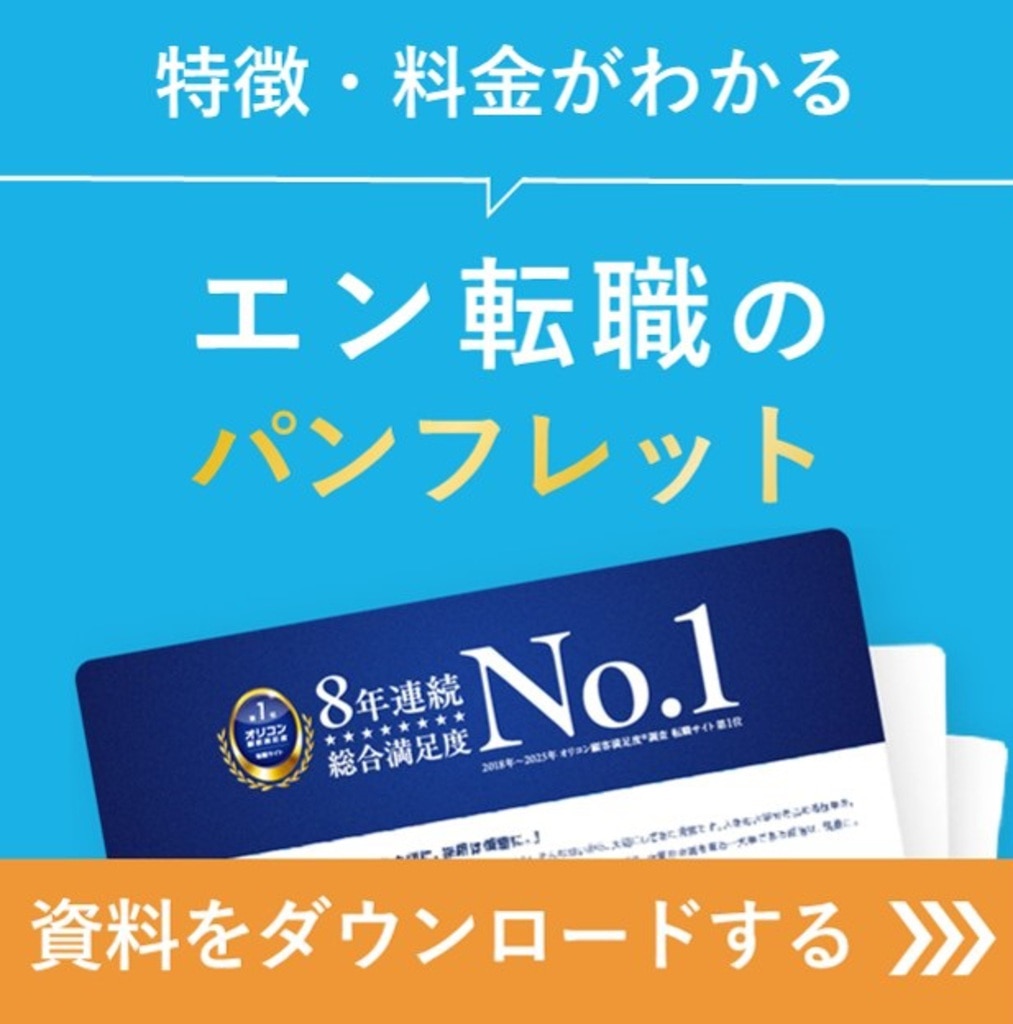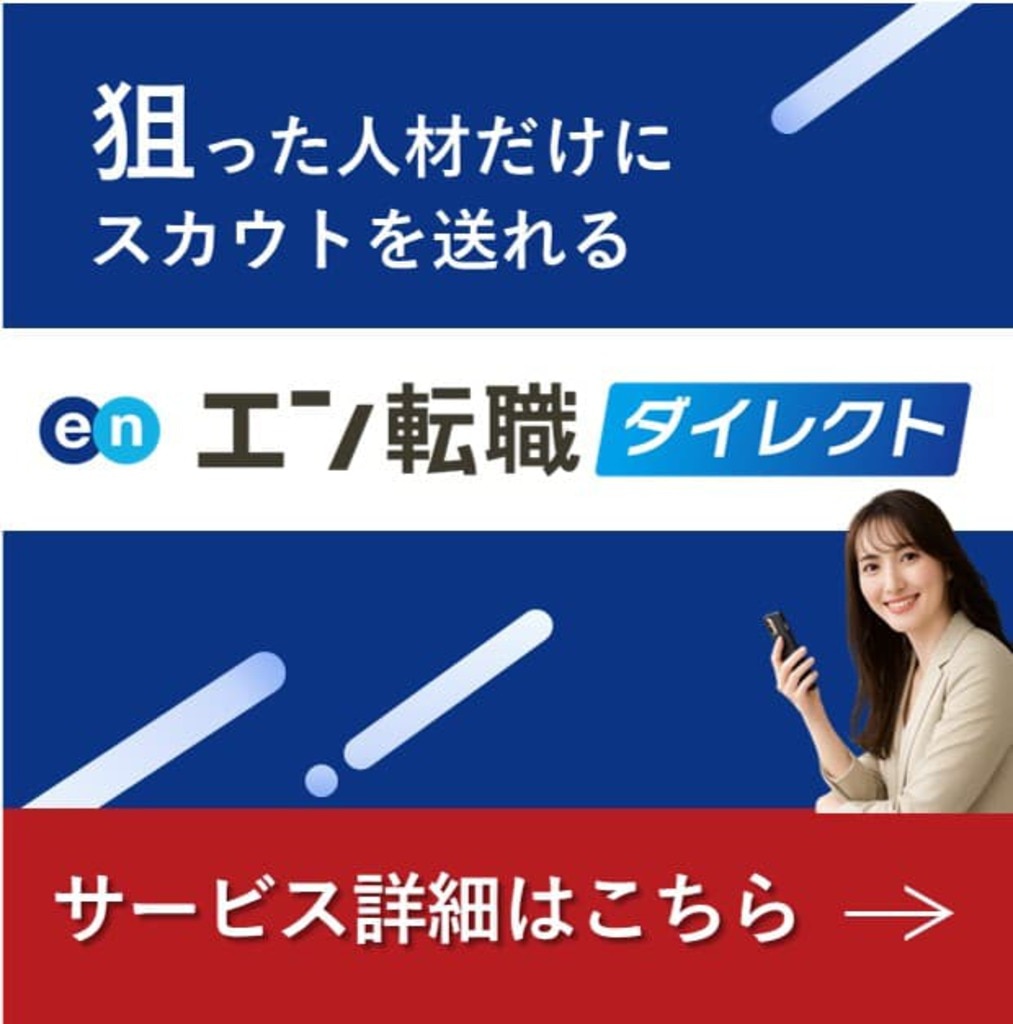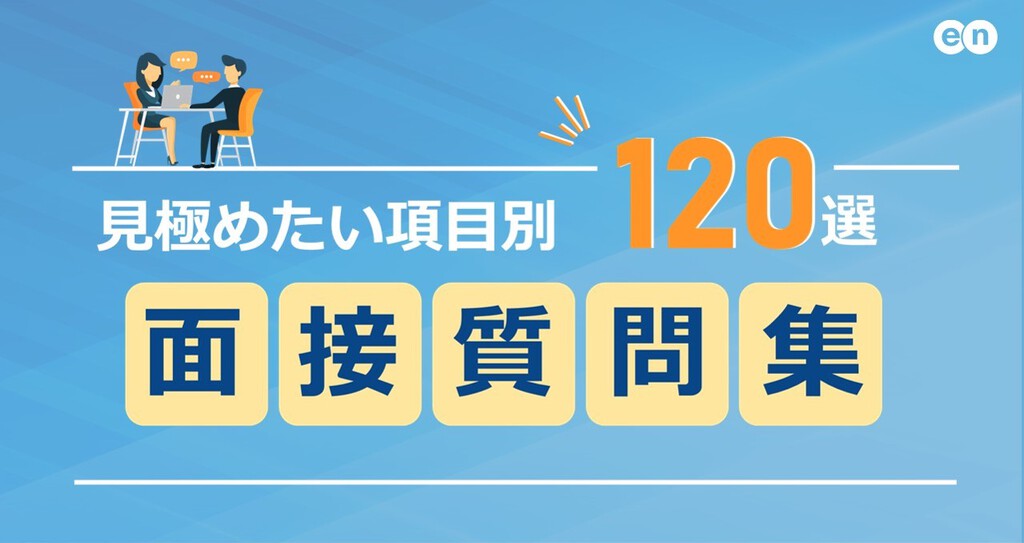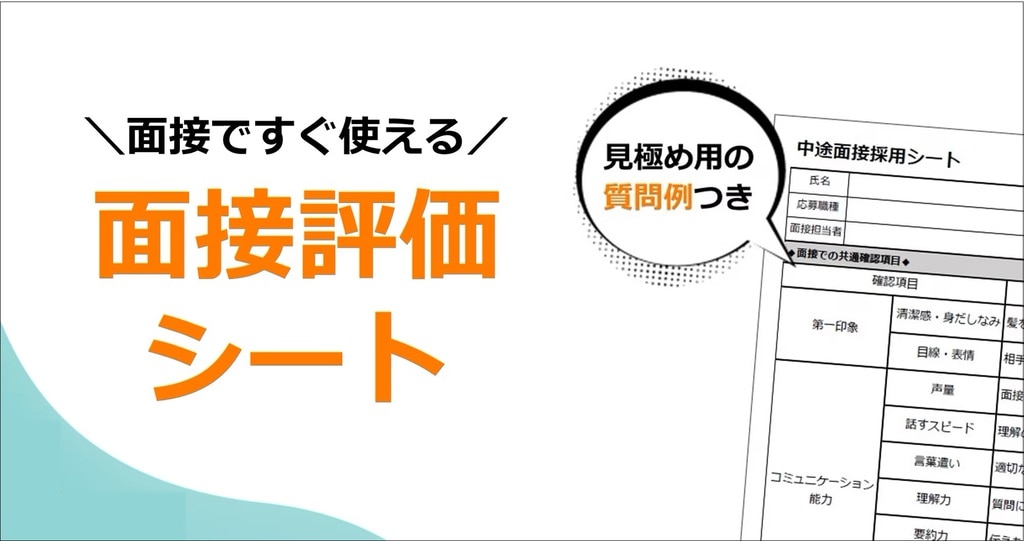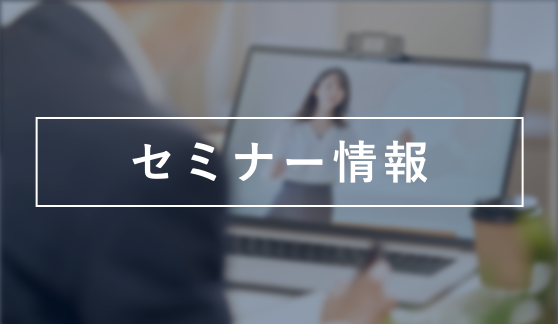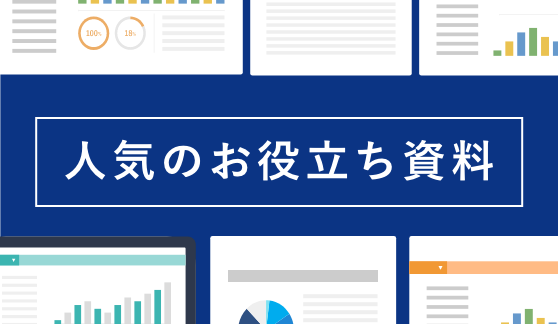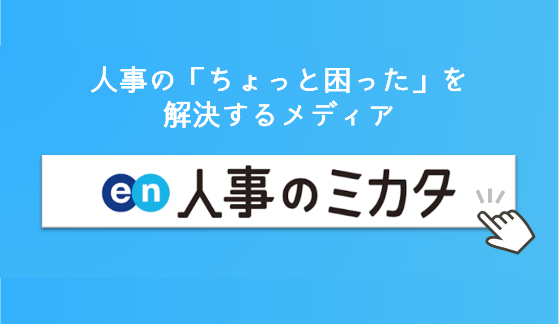嘱託とは? 労働条件や各雇用形態との違い、雇用する際の注意点

雇用形態は大きく分けて、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の2つに分類できます。なかでも非正規雇用労働者は、契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなど種類が多様なので、各企業が必要な労働力などに応じて、雇用の仕方を分けている状況です。
非正規雇用労働者に「嘱託(しょくたく)」という働き方があります。嘱託社員には「正規雇用労働者よりも人件費を抑えられる」「契約期間が満了した場合に原則として雇い止めが認められる」などの特徴があり、近年注目が集まっています。
本記事では嘱託社員について、主な労働条件やほかの雇用形態との違い、雇用するメリット、雇用するときの注意点などを解説します。雇用を検討している方は、本記事をもとに嘱託社員への理解を深めましょう。
▼本記事をより分かりやすく解説した「嘱託社員の雇用ガイド| 各雇用形態との違いや注意点」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼
目次[非表示]
- 1.嘱託(しょくたく)・嘱託社員とは?
- 1.1.定年後に再雇用されるケース
- 1.2.再雇用以外で嘱託社員になるケース
- 2.嘱託社員の労働条件
- 3.嘱託社員とほかの雇用形態の違い
- 3.1.正社員との違い
- 3.2.契約社員との違い
- 3.3.パート・アルバイトとの違い
- 3.4.業務委託との違い
- 4.嘱託社員を雇用するメリット
- 5.嘱託社員を雇用するデメリット
- 6.嘱託社員を雇用するときの注意点
- 6.1.不合理な労働条件は禁止
- 6.2.雇い止めに関する法律を遵守する
- 7.まとめ
嘱託(しょくたく)・嘱託社員とは?
嘱託(しょくたく)は「ある業務を頼んで任せる」という意味がある言葉です。嘱託社員という働き方に法律上の定義はありませんが、非正規雇用労働者の一種で、ある特定の業務の知識・経験が豊富な人材を有期雇用する際に使われるケースが多くあります。
法律上の定義がないため、企業によっては嘱託社員を準社員のように扱っているパターンもあります。つまり、嘱託社員をどのような位置づけで雇用するかは、企業の裁量にある程度任せられているのです。
また、嘱託社員の契約期間は、労働基準法第十四条によって、最長3年と定められています。しかし「定年後に再雇用する場合」「専門知識が必要な業務を担う場合」などにおいては、最長5年まで契約期間を延ばすことが可能とされています。
定年後に再雇用されるケース
昨今では定年退職した社員を再雇用する際に、嘱託社員として雇用するケースが多くあります。定年退職後に嘱託社員として再雇用するケースには、以下のパターンが挙げられます。
- 自社に定年まで在籍していた社員を、定年後に嘱託社員として再雇用する
- 定年まで他社に在籍していた人材を、新たに嘱託社員として自社へ迎え入れる
近年は少子高齢化の影響で、高齢者に雇用機会をつくる必要性が高まっています。高年齢者雇用安定法により、65歳まで雇用機会を与えるよう義務づけられているため、定年後の再雇用制度として、嘱託という働き方を活用している企業が多くなっているのです。
再雇用以外で嘱託社員になるケース
定年退職後の再雇用以外で、人材を嘱託社員として雇用するケースには、以下のようなパターンがあります。
- 専門性の高い業務を任せるため、期間限定で雇用する
- 特定のプロジェクトを遂行するため、プロジェクト期間中のみ雇用する
嘱託社員の労働条件
前述したように、嘱託社員には法律上の定義がないため、嘱託社員の労働条件も「嘱託社員だけの条件」は特に明確化されていない状況です。そのため一般的に、嘱託社員の労働条件は「パートタイム・有期雇用労働法」などの法律をもとに定められています。
嘱託社員の賃金
パートタイム・有期雇用労働法が改正され、「同一労働同一賃金」が定められました。これは正規雇用労働者と、非正規雇用労働者の不合理な待遇差を解消するためのものです。
企業は業務内容や責任範囲などが同一の場合、各労働者に同じ賃金を支払わなくてはなりません。嘱託社員にも「同一労働同一労働」に則った賃金が支払われます。
ただし定年後に再雇用している場合は、責任範囲が正規雇用労働者だった頃よりも狭くなったり、業務内容が少なくなったりすることがほとんどです。そのため、正規雇用労働者として働いていた頃よりも、賃金が低くなるケースが多くあります。
嘱託社員の社会保険
嘱託社員も条件を満たす場合は、社会保険への加入義務があります。社会保険の加入条件は以下の通りです。(2024年2月現在)
- 厚生年金保険の適用対象者が101人以上の企業
(2024年10月以降は51人以上に法改正予定) - 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内労働時間内の賃金が月額88,000円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
出典:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険加入対象により手厚い保障が受けられます」
加えて、以下の条件を満たす場合は、雇用保険への加入義務があります。
- 31日以上の雇用期間が見込まれる
- 週の所定労働時間が20時間以上
出典:厚生労働省「雇用保険の加入手続きはきちんとなされていますか」
また、労働基準法上の労働者に該当する場合、全従業員が加入対象となる労災保険(労働者災害補償保険)にも加入する必要があります。各保険へ適切に加入をしないと、罰則の対象となるので注意しましょう。
嘱託社員の有給休暇
労働基準法により、嘱託社員にも有給休暇を付与するよう定められています。有給休暇を付与する条件は以下の2つです。
- 雇い入れの日から6ヶ月以上経過していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
上記の条件を満たしている嘱託社員には、10労働日の有給休暇を付与する必要があります。勤続期間に応じた有給休暇の日数は、以下の通りです。
勤続期間 |
付与すべき有給休暇の日数 |
6ヶ月 |
10労働日 |
1年6ヶ月 |
11労働日 |
2年6ヶ月 |
12労働日 |
3年6ヶ月 |
14労働日 |
4年6ヶ月 |
16労働日 |
5年6ヶ月 |
18労働日 |
出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
嘱託社員とほかの雇用形態の違い
嘱託社員とほかの雇用形態の違いを詳しく見ていきましょう。正社員・契約社員・パート・アルバイト・業務委託との違いを解説します。
正社員との違い
正社員と嘱託社員のもっとも大きな違いは、雇用期間です。正社員は期間に定めのない雇用形態なので、労働契約の更新が必要ありません。
対して、嘱託社員は期間に定めのある雇用形態なので、契約期間が満了したあとも働き続ける場合は、労働契約を更新する必要があります。
また一般的に、同じような業務内容であっても、正社員の責任範囲の方が、広い場合が多いでしょう。そのため正社員と嘱託社員で比べると、賃金・福利厚生・退職金の有無などの待遇面は、正社員の方が手厚い傾向にあります。
契約社員との違い
契約社員は非正規雇用労働者の一種で、期間に定めのある雇用形態です。法律上、契約社員と嘱託社員の明確な区分はありませんが、以下のように分けられている場合が多いようです。
契約社員 |
|
嘱託社員 |
|
上記の分け方は、あくまでも一般的な例です。契約社員と嘱託社員をどのように区分するかは、企業によって異なります。
パート・アルバイトとの違い
パート・アルバイトも非正規雇用労働者で、期間に定めのある雇用形態の一種です。契約社員と同様に、パート・アルバイトと嘱託社員にも、法律上の明確な区分はありません。
それぞれをどのように位置づけるかは、企業により異なりますが、以下のように分けられているケースが多く見られます。
パート |
|
アルバイト |
|
嘱託社員 |
|
労働時間がフルタイム勤務よりも短く、シフト制で働く労働者を「パート」と呼び、学生やフリーターなどの労働者を「アルバイト」と呼ぶ傾向があります。
また、パート・アルバイトが基本的に時給制であるのに対し、嘱託社員は月給制で働いている場合が多いなどの違いもあります。
業務委託との違い
業務委託とは、企業が雇用契約を結んでいない個人や、外部業者へ業務を依頼すること。業務を依頼した企業は、「成果物が納品されたとき」「依頼した役務が完遂されたとき」など、依頼内容が問題なく実施されたときに、依頼先へ報酬を支払います。
業務委託と嘱託社員のもっとも大きな違いは、雇用契約の有無です。業務委託は企業と雇用契約を結ばないのに対し、嘱託社員は企業と有期雇用契約を結びます。
業務委託に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。業務委託契約の種類やメリットなどを解説していますので、気になる方はこちらもご覧ください。
▼業務委託とは? 契約の種類やメリット、契約締結時の注意点などを解説
嘱託社員を雇用するメリット
企業が嘱託社員を雇用する主なメリットは、以下の通りです。
- 人件費を抑えられる
- 雇用のミスマッチを防げる
- 即戦力になれる人材を雇用できる
嘱託社員を雇用するときは、担当業務に必要な知識・経験がすでにある人材を雇うケースがほとんどです。そのため、業務の即戦力になれる可能性が高いほか、新人教育にかける育成コストの削減にもつながります。
加えて、企業が労働者へ求めているスキルと、嘱託社員が有しているスキルがマッチする場合が多いことから、雇用のミスマッチを防止しやすいメリットもあります。
嘱託社員を雇用するデメリット
企業が嘱託社員を雇用する主なデメリットは、以下の通りです。
- 契約期間が満了するたびに更新の手間がかかる
- 環境や立場の変化により、モチベーションを保てなくなる嘱託社員もいる
嘱託社員は、企業と有期雇用契約を結んで仕事をする働き方です。契約期間が満了したあとも働き続けてもらう場合は、更新の手続きを行なう必要があります。
また、定年退職後の人材を嘱託社員として再雇用する場合、以下のような状況が生じる可能性があるでしょう。
「今まで自分の部下だった人が再雇用後は上司になった」
「業務内容は今までとほぼ同じだが、責任範囲が減ったため給与も低くなった」
こういった環境や立場の変化により、仕事へのモチベーションを保てなくなってしまう人もいます。嘱託社員も自社の従業員であることには変わりないので、定期的に個人面談を実施するなどして適宜フォローしましょう。
嘱託社員を雇用するときの注意点
最後に嘱託社員を雇用するとき、特に注意しておきたいポイントを2つ解説します。法令を遵守し、従業員が働き方や立場を問わず、心地よく働ける職場づくりを心がけましょう。
不合理な労働条件は禁止
パートタイム・有期雇用労働法で定められた「同一労働同一賃金」により、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間に、不合理な待遇差をつけるのは禁止されています。
企業側は、業務内容や責任範囲などが同一の場合、雇用形態に関係なく各労働者に同じ給与を支払わなくてはなりません。
たとえば正社員と嘱託社員で「業務量・責任範囲が大きく異なっている」「嘱託社員の方が、労働時間が短い」などの場合は、待遇差があっても合理的であると判断されます。
しかし、業務量や責任範囲が変わらないにもかかわらず、「非正規雇用労働者だから」などの理由で一方的に待遇を悪くするのは、不合理な待遇差とみなされるので注意しましょう。
雇い止めに関する法律を遵守する
「雇い止め」とは、企業側が嘱託社員との雇用契約を更新しないと決めることです。嘱託社員は基本的に有期雇用契約であるため、契約期間が満了すれば、企業側は契約更新を拒絶できます。
ただし「無期転換ルール」が定められているため、一定の条件を満たす場合は、更新時に雇用期間を無期へと転換しなくてはなりません。無期転換ルールとは、以下のようなルールです。
無期雇用ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
有期契約労働者が、使用者に対して無期転換の申し込みをした場合、無期労働契約が成立します。使用者は断ることができません。
引用:厚生労働省「無期転換ルールについて」
無期転換ルールが適用される条件は、以下の通りです。すべての条件を満たす場合、無期転換ルールの対象となります。
- 有期労働契約の通算期間が5年を超えている
- 契約の更新回数が1回以上
- 現時点で同一の使用者との間で契約している
出典:厚生労働省「無期転換ルールハンドブック ~無期転換ルールの円滑な運用のために~」
まとめ
嘱託社員の労働条件や、ほかの雇用形態との違い、雇用するメリット・デメリット、雇用するときの注意点などを解説しました。
嘱託社員には、法律上の定義がありません。嘱託社員をどのような位置づけで雇用するかは、企業の裁量にある程度任せられています。
一般的には、「定年退職した人材を再雇用するとき」「専門性の高い業務を期間限定で依頼したいとき」などに、嘱託社員として人材を雇うケースが多くあります。業務の知識・経験が豊富な人材を嘱託社員として雇用すれば、教育コスト削減や雇用ミスマッチの防止につながるでしょう。
現代の日本社会は、少子高齢化による労働力人口の減少が進み、人材が希少化しています。企業の採用難易度が上がっているので、嘱託社員なども活用し、人材が長く活躍できる環境を整えることが大切です。
しかし一方で、難易度が上がっているとはいえ、新たな人材を採用しなければ、企業の成長が鈍化してしまうでしょう。少しでも成功率の高い方法で、新たな人材を採用したいとお考えの方は、ぜひ『エン転職』にご相談ください。
『エン転職』は日本最大級となる1100万人の会員を保有する、中途採用向け求人サイトです。オリコンヒットチャートでお馴染み、「オリコン顧客満足度調査」の「転職サイト部門」において、『エン転職』は8年連続 総合満足度第1位を獲得しています(2025年時点)。
今、一番求職者から選ばれている求人メディアだからこそ、難易度が高い採用にもオススメです。採用でお悩みの際は、以下のエン転職お問い合わせ窓口よりお気軽にご相談ください。
ほかにもエン転職には採用を成功に導くさまざまな特徴があります。エン転職の料金表・パンフレットのダウンロードやサービスの詳細については、こちらからご確認ください。
▼本記事をより分かりやすく解説した「嘱託社員の雇用ガイド| 各雇用形態との違いや注意点」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼