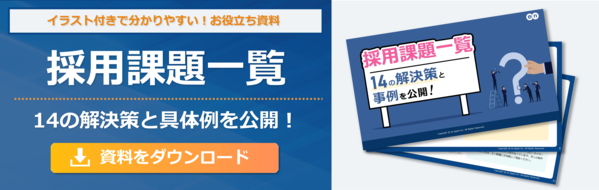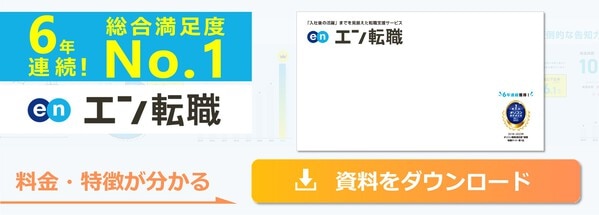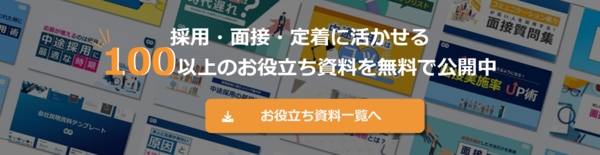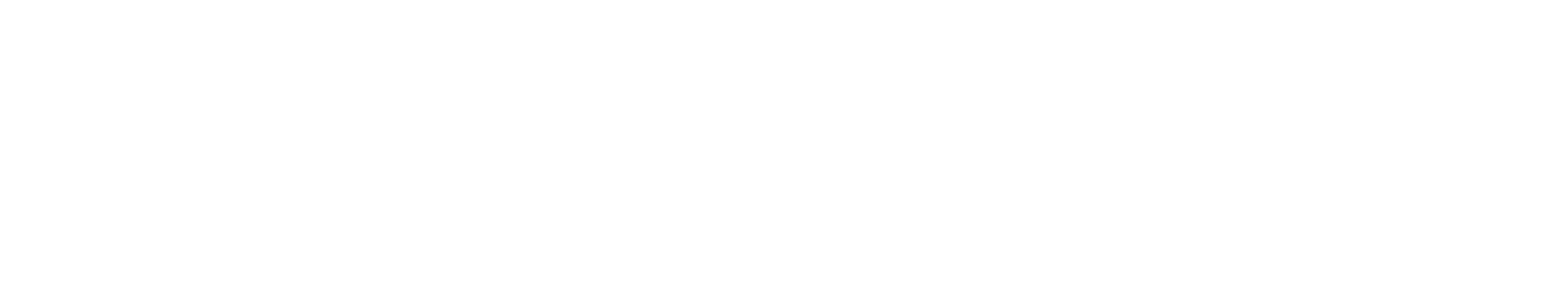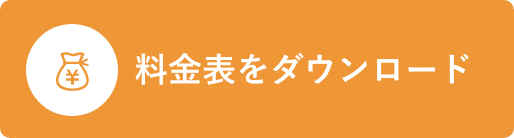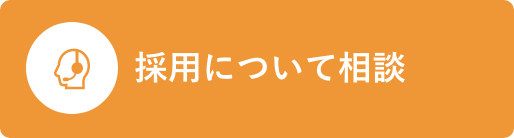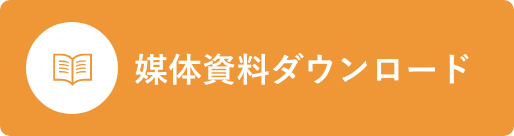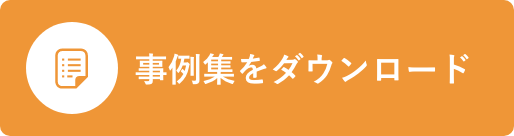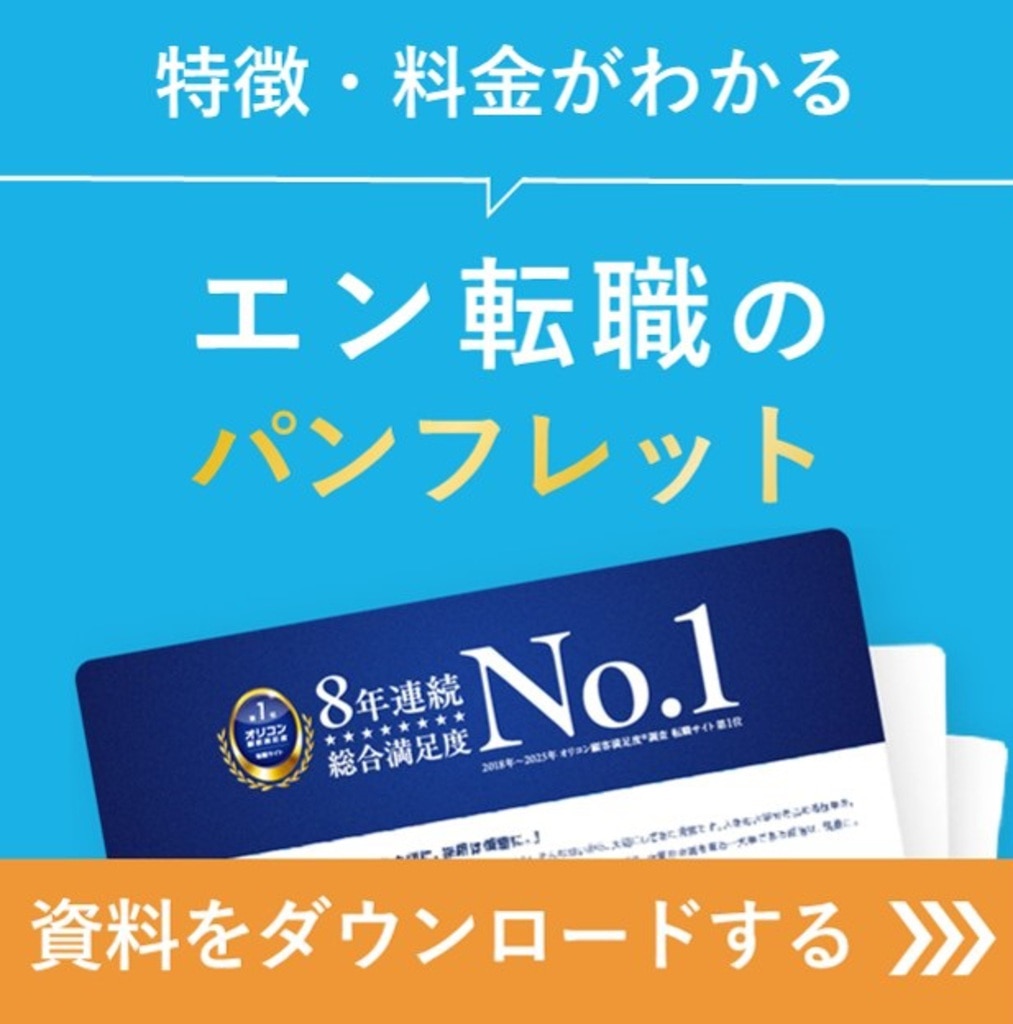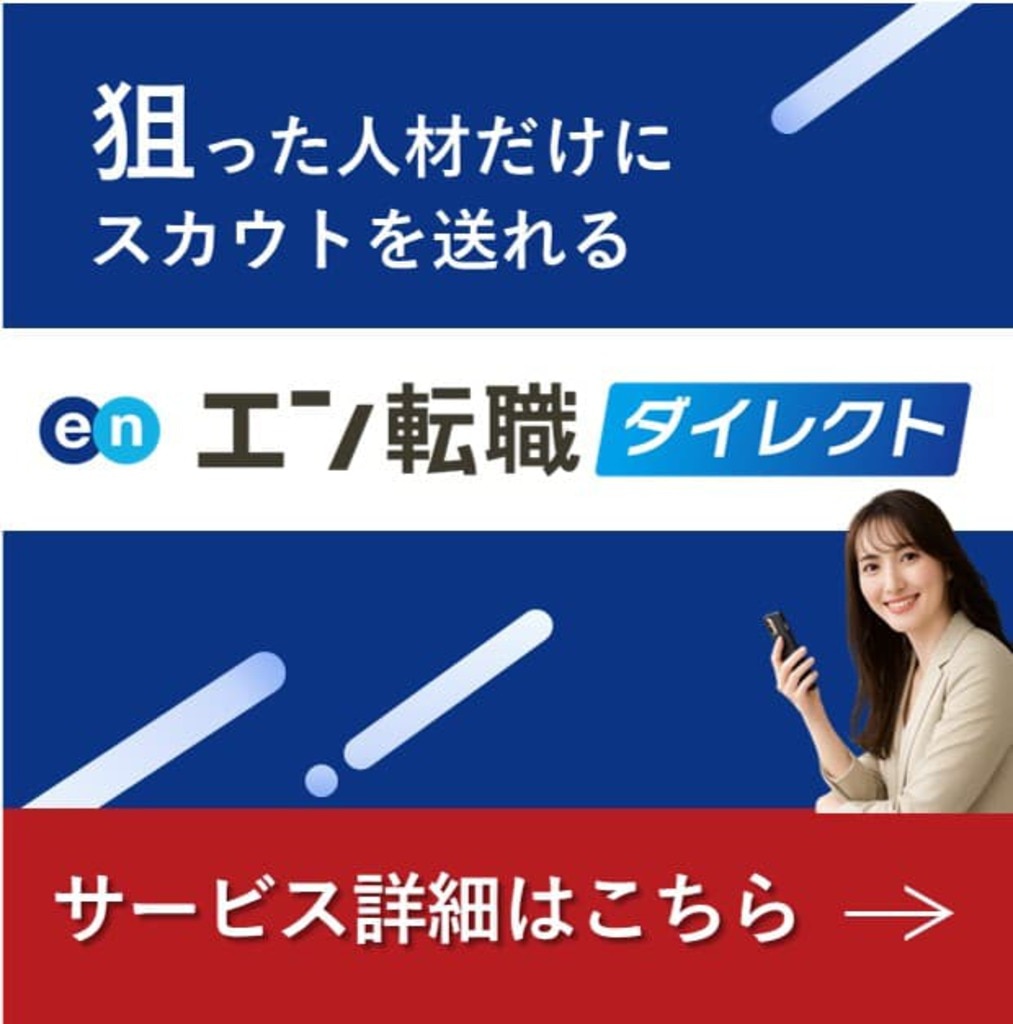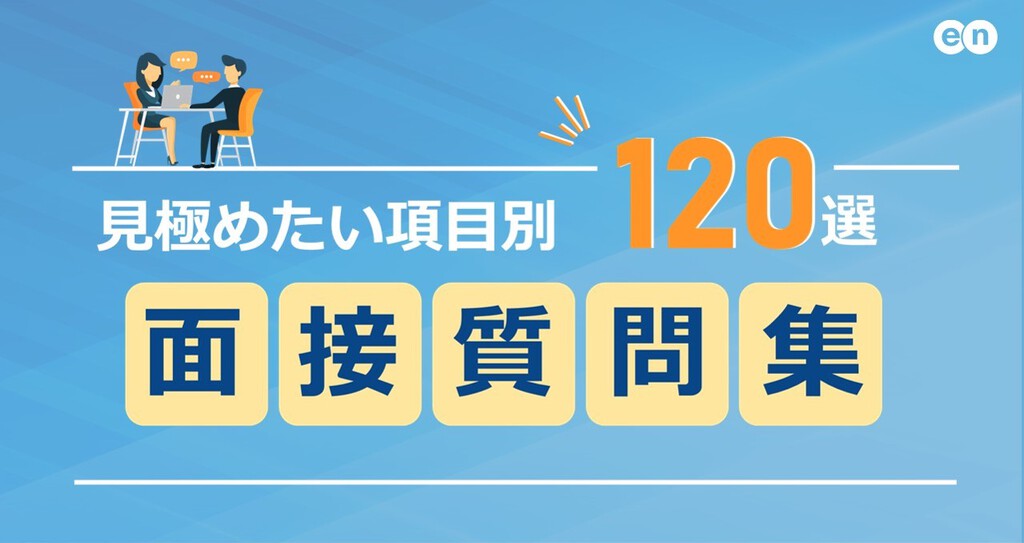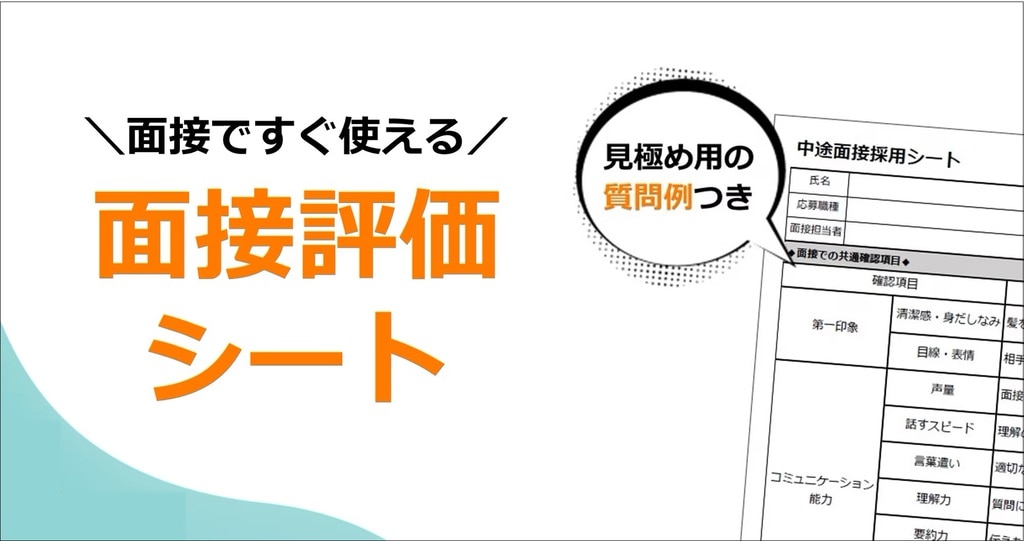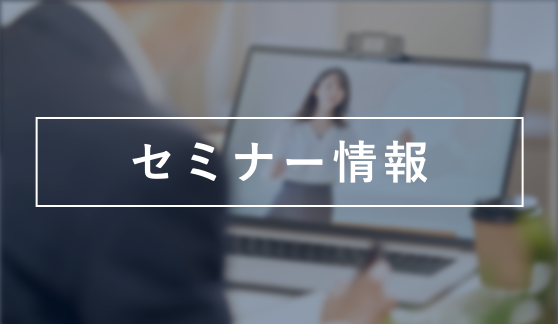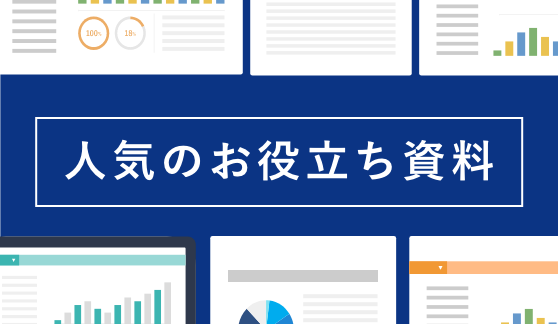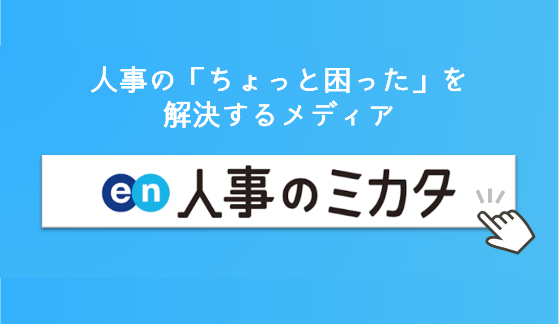採用課題一覧|主要な7パターンの解決策と具体的な企業事例を公開

企業の経営者、人事担当者・採用担当者の皆さま。本記事にたどり着いたということは、何かしらの「採用課題」を抱え、採用が上手くいかずに悩んでいらっしゃると思います。
「採用課題」と一言でまとめても、その種類は様々であり、課題に応じて解決策は異なります。
そこで本記事では、採用課題の一覧から、特に多い7つの採用課題の解決策と解決事例、採用課題の特定法までまとめました。
「なぜ採用が上手くいかないのか分からない…」「自社の採用課題は分かっているが、どうすれば課題を解消できるか分からない…」、どちらのお悩みを解消できるノウハウをまとめておりますので、ぜひご活用ください。
▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「採用課題一覧|14の解決策と事例を公開!」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼
目次[非表示]
- 1.採用課題とは?
- 2.採用課題一覧
- 2.1.特に応募の数や質に影響する採用課題
- 2.2.特に面接辞退・内定辞退に影響する採用課題
- 2.3.特に入社後の定着率に影響する採用課題
- 3.主要な6つの採用課題と解決策
- 3.1.応募が集まらない(母集団形成)
- 3.1.1.解決策1:適切な採用手法・採用媒体を選ぶ
- 3.1.2.解決策2:求人の情報量を増やす
- 3.1.3.解決策3:求人で画像・動画を活用する
- 3.1.4.解決策4:求人で他社と差別化を図る
- 3.2.求める人材がいない(応募者の質)
- 3.2.1.解決策①:向いている人・向いていない人を求人で伝える
- 3.2.2.解決策②:求める人材にとって魅力的に見える求人にする
- 3.2.3.解決策③:スカウトメールやダイレクトリクルーティングを活用する
- 3.3.面接辞退が多い
- 3.3.1.解決策①:選考回数を減らす
- 3.3.2.解決策②:面接の連絡スピードを速める
- 3.4.内定辞退が多い
- 3.4.1.解決策①:面接で魅力づけをする
- 3.4.2.解決策②:クチコミを活用する・払しょくする
- 3.5.入社後の定着率が悪い
- 3.5.1.解決策①:求人に記載する情報量を増やす
- 3.5.2.解決策②:求人で仕事の厳しい側面まで伝える
- 3.6.採用に工数をかけられない
- 3.6.1.解決策①:採用計画・採用戦略から採用支援会社に任せる
- 3.6.2.解決策②:採用工程の代行サービスを利用する
- 4.採用課題を解決した企業事例
- 5.自社の採用課題の見つけ方
- 6.採用課題が生じる背景
- 7.まとめ
採用課題とは?
採用課題とは、人材を獲得する効率を低下させる障害や困難のことを指します。ポイントは「成功率」を低下させる要因だけでなく、「効率」を低下させる要因も含めて採用課題ということです。
例えば、「応募が集まらず採用が決まらない」は採用課題ですが、「採用できても入社後に早期離職してしまう」というのも結果的に、再び採用活動を行なう必要が生じて効率を低下させる採用課題と言えます。
「採用課題」が生じる原因は、社内にあるとは限りません。経済の変化、業界の成長や衰退、中途採用市況の変化なども、採用課題に影響を与えます。今月採用を行なった時と、来月採用を行なう時では、「採用課題」が異なるケースも少なくありません。
例えば、同時期に掲載される求人の待遇・打ち出しによっても採用の成否は左右されます。今月の採用で「月給24万円」が同じエリア・同じ職種で高水準だったとしても、来月は平均~平均を下回っている可能性もあります。つまり、「採用課題」は採用活動ごとに見極め、適切な打ち手を都度考えていくことが重要です。
採用課題一覧
採用課題は多岐にわたります。ここでは【応募の数や質に影響する採用課題】、【特に面接辞退・内定辞退に影響する採用課題】、【特に入社後の定着率に影響する採用課題】の3つに分類してご紹介します。
特に応募の数や質に影響する採用課題
- 採用活動に時間をさけない
- 採用担当者が採用に不慣れ
- 採用手法が合っていない
- 採用媒体内に求める人材が少ない
- 求人の露出量が少ない
- 求人の情報量が少ない
- 求人の書き方が悪い
- 求人で狙うターゲットを明確にできていない
- 求人で狙うターゲットに届いていない
- 待遇が相場より悪い
- 実態の待遇を求人に書ききれていない
- 求人に画像がない
- 求人で画像を効果的に活用できていない
- 求人に動画がない
- スカウトメールを送れていない
- スカウトメールの文面が悪い
- スカウトメールを送る対象が悪い
- 採用ページがない、あるいは古い
- 企業クチコミサイトに自社のクチコミがない
- 企業クチコミサイトにネガティブなクチコミが多い
特に面接辞退・内定辞退に影響する採用課題
- 選考回数が多い
- 紙の履歴書が必須
- 面接時の提出物が多い
- 書類選考の合否連絡が遅い
- 面接日程調整の連絡が遅い
- 内定通知の連絡が遅い
- 面接会場が遠い
- 面接で充分に魅力づけできていない
- 求人で充分に魅力づけできず面接優先度が低い
- 面接ノウハウが社内にない
特に入社後の定着率に影響する採用課題
- 求人と仕事・待遇の実態に乖離がある
- 求人・面接で仕事を充分に理解させられていない
- 求人・面接で風土を充分に理解させられていない
- 採用要件(応募資格)の要素が足りていない
- 面接で充分に見極め出来ていない
主要な6つの採用課題と解決策
採用課題一覧の中でも特に頻出する6つの課題について、詳細と解決策の一例をご紹介します。
応募が集まらない(母集団形成)
求人を掲載しても応募が集まらないことを、母集団の形成に課題があると言います。応募が集まらないことには、その先を改善しようがありません。まずは応募を集めることが第一目標となります。応募を集めるためには、そもそも「手法に問題があるのか」「活動の中身に問題があるのか」に分けて考える必要があります。
解決策1:適切な採用手法・採用媒体を選ぶ
人材紹介、求人広告、地方求人誌、ハローワーク等。採用手法にはそれぞれ得意分野・苦手分野があります。
例えば、人材紹介は登録人材の経験・知識・スキルが豊富な反面、採用コストが高く、大量応募獲得には向いていません。紹介会社のエージェントからの紹介を待つしかなく、採用が決まるまでに時間がかかるケースもあります。求人広告は工夫次第で大量応募を集めることができますが、求人の質などにも応募効果が大きく影響されます。
同様に、採用媒体にも登録会員に特色があります。若手人材が良く利用している媒体、主婦層が良く利用している媒体、特定の職種経験者採用に特化している媒体など。自社が求める人材に応じて、最適な採用手法・採用媒体を選ぶことが、採用成功の第一歩です。
自社に合った最適な採用手法の選び方については以下の記事で解説しておりますので、ご参考ください。
▼10の中途採用手法を比較|自社に合った採用手法の選び方▼
解決策2:求人の情報量を増やす
転職は人生において重要な決断。求職者からすると企業理解を深めるためにも、求人の情報量は多いに越したことはありません。求人の文字スペースは最大限活用しましょう。それでも足りない場合は、求人情報量が多いプランを活用するのも選択肢になります。
解決策3:求人で画像・動画を活用する
求人で画像・動画を活用するのも、情報量を増やす手段として有効です。画像は文字の7倍、動画は文字の5000倍の情報を伝えられると言われています。特に文字情報では伝えにくい、会社の雰囲気・風土を伝えるのに、画像・動画は最適です。
解決策4:求人で他社と差別化を図る
貴社が求人を掲載するのと同じ時期に、同じエリアで、同じ職種を募集する他社は、「採用上の競合(=ライバル)」と言えます。ライバルの待遇と打ち出しと比較して、何を打ち出せば勝ち目があるかを検討して、差別化した求人を掲載することは採用の成功率を大幅にアップさせます。
ただし、自社だけでこうした求人の工夫は難しいため、採用支援会社に相談すると良いでしょう。『エン転職』は自社で求人専門のディレクター・コピーライターを雇用し、求人制作のアドバイスを行なっています。求人の制作で悩んだときは、エン転職にお気軽にご相談ください。
▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「採用課題一覧|14の解決策と事例を公開!」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼
求める人材がいない(応募者の質)
応募者が求める人材の条件(採用要件・応募資格)と合致しない場合も、応募数と同様、「手法に問題があるのか」「活動の中身に問題があるのか」に分けて考えるのがオススメです。
採用媒体内に求める人材が少ないなら、利用する媒体そのものを見直す必要があります。活動の中身に改善を加えるのは、その後です。
解決策①:向いている人・向いていない人を求人で伝える
求人内で率直に「この仕事に向いている人・向いていない人」を伝えるというのも、有効応募率を高める手段です。求職者としても、企業がどのような人材を必要としているのか、逆にどのような人材はマッチしづらいのかを判断しやすくなります。
解決策②:求める人材にとって魅力的に見える求人にする
例えば、「目標達成にこだわれる人」が欲しいとします。目標達成をあきらめない人なら、欲しがる企業は山ほどいるはずです。そのため、一方的に条件を提示するのではなく、「目標達成にこだわれる人なら、歩合給で高年収を得やすい」など、求職者にとっての魅力に落とし込んで求職者に求人で紹介すると応募を集めやすくなります。
解決策③:スカウトメールやダイレクトリクルーティングを活用する
求人広告や人材紹介は、応募を「待つ」のが基本です。しかし、求人サイトの中「スカウトメール機能」を活用したり、スカウトに特化した採用サービスである「ダイレクトリクルーティング」を利用したりすることで、求める人材に対して直接求人を届け、応募を獲得しやすくなります。
スカウトメールとダイレクトリクルーティングの違いは、以下の記事で解説しておりますのでご参考ください。
▼ダイレクトリクルーティングサービスとスカウトサービスの違いとは?▼
面接辞退が多い
面接辞退が多い場合は、「面接前」に辞退が多いのか、「面接後」に辞退が多いのかによって対策が少し異なります。例えば、面接前の辞退が多いのであれば、応募者の中で「選考の優先度が低かった」ことも原因の1つとして考えられます。これはつまり、求人での魅力づけが不十分だったということが考えられます。応募の数や質同様、求人の工夫で採用課題を解決する必要があります。
この他にも、面接辞退には以下のような解決策があります。
解決策①:選考回数を減らす
応募から内定までは、「平均2週間以内」というデータがあります。面接回数が多くなるほど選考期間が長くなり、他社で先に内定が決まってしまう危険性が高まります。また、求職者にとっても面接のために複数回来社したり、そのために準備したりするのは負担になります。
現場・人事・役員で3回面接があるなら、全員が同席して1回の面接にするなど、選考回数を減らすことを検討しましょう。
解決策②:面接の連絡スピードを速める
前述のとおり、選考が長引くほど他社で内定が決まる可能性があります。貴社が欲しい人材は、他社も欲しいという前提を踏まえ、可能な限り、面接までの連絡を早めましょう。面接前日にはリマインドでメールを送るのも有効です。
内定辞退が多い
面接まで来てくれているのに、内定を辞退されてしまうということは面接で入社意欲を高め切れていない可能性があります。選考スピードを上げることも重要ですが、この点を改善しないと、内定承諾率を高めることはできません。
解決策①:面接で魅力づけをする
面接の役目は、「見極め」と「魅力づけ」の2点です。求職者は複数社に応募しているケースが多く、他社からも内定をもらう可能性があります。そのため、面接では候補者を見極めるだけでなく、自社を選んでもらえるように魅力づけする必要があります。
求職者の転職軸を確認して、自社に入社することで希望が叶うことをアピールしたり、現場社員に面接に同席してもらって疑問や不安を解消したりといった工夫が考えらえます。
解決策②:クチコミを活用する・払しょくする
面接辞退・内定辞退が起きるケースの中には、企業クチコミサイトに応募企業のクチコミがなくて実態が分からなかった、応募後に企業のネガティブナクチコミを見て思いとどまった…というケースが意外なほど多くあります。現在の就職活動・転職活動では、応募企業のクチコミを調べることが当たり前になっています。
クチコミがないと応募してもらえないケースがあるので、企業クチコミサイトに自社のクチコミがない場合は、まず従業員に協力してもらってクチコミを投稿しましょう。ネガティブナクチコミがあった場合は、受け止めたうえで、どのように改善しているのかを応募者に伝えられるようにしましょう。
クチコミは見られているという前提で、会社の課題も正直に伝え、改善に向けた取り組みを行なっていることが分かると、誠実さが伝わり、求職者も安心できます。
入社後の定着率が悪い
入社後の定着率が悪い場合は、採用段階に問題があるのか、受け入れ後に問題があるのか原因を特定することが重要です。退職相談をされた場合は、相手の本音を引き出し、何が退職の原因かを見極めましょう。
業務負荷の大きさ、上司・同僚などとの人間関係、評価制度や教育制度への不満などが、退職原因となる場合は、受け入れ部署や会社制度自体を見直していかなければなりません。今回はそれ以外の「採用段階でミスマッチが起きている場合の解決策」をご紹介します。
解決策①:求人に記載する情報量を増やす
よくある早期離職の原因の1つに「入社前に抱いていた仕事・会社に対するイメージとのギャップ」があります。こうしたギャップが生まれてしまう背景には、求人の情報不足があります。求人で仕事の概要しか伝えていない、求人の情報が少なく文字数上限には余裕がある。このように求人の情報量が不足しているケースは少なくありません。心当たりが多い方は多いのではないでしょうか?
採用を決める前に、仕事・会社に対するイメージを深められるように情報は可能な限り多く、求人で伝えるのがオススメです。特に仕事内容・一緒に働く社員・入社直後と将来的な年収例などは知りたい情報です。
解決策②:求人で仕事の厳しい側面まで伝える
仕事の楽しい側面だけでなく、仕事の厳しい側面も、求人で事前に伝えるのがオススメです。あえて仕事の厳しい側面を事前に伝えることで、仕事の厳しさを知ったうえで、それでも「この仕事をやってみたい!」と覚悟ある方から応募が集まりやすくなります。
これは「RJP理論」と呼ばれ、実際に、仕事の厳しい側面を事前に伝えることで、面接通過率・内定率・定着率が上がったという事例が多数あります。RJPとは「Realistic Job Preview」の略。「現実的な仕事情報の事前開示」を意味します。会社の良い点だけでなく、自社の課題や仕事の厳しさといったネガティブな情報の開示を入社前に行なうことで「入社後のミスマッチを減らす」取り組みです。
採用に工数をかけられない
経営者が採用業務を行なっている。専任の人事担当がいるわけではなく、本業と兼務で採用担当を行なっている。こうしたケースだと、採用ばかりに時間をさけないと思います。採用に工数をかけられないことも、深刻な採用課題です。以下に採用にかかる負担を減らすのかが求められます。
解決策①:採用計画・採用戦略から採用支援会社に任せる
どんな目的で、どんな人を、いつまでに、何名採用するのか(採用計画)
採用上の競合他社が多い中、狙った人材をどうやって採用するのか(採用戦略)
こうした採用計画・採用戦略を忙しい中で、経営者・採用担当者ご自身で考えるのは大変です。そこで、こうした採用計画・採用戦略から一緒に考えてくれる採用支援会社を利用することで、採用にかける時間を抑えることができます。
エン転職は、ただ貴社の求人を掲載するだけでなく、こうした採用計画・採用戦略を練るところからお手伝いができます。採用でほしい人物像などが明確に定まっていなくても、言語化するところからご支援します。まずは、お気軽にご相談ください。
解決策②:採用工程の代行サービスを利用する
採用支援会社の中には、「書類選考」や「スカウトの送信」など、採用の工程を代行するオプションサービスを備えているところもあります。他の業務が忙しい場合は、こうした代行サービスを活用して業務を切り出すと、負担を大きく軽減できます。
▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「採用課題一覧|14の解決策と事例を公開!」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼
採用課題を解決した企業事例
以下で採用活動中の工夫により、「応募の数を改善した事例」、「応募の質を改善した事例」「選考中の辞退を防止した事例」「入社後の定着率が向上した事例」「採用工数を削減した事例」をまとめています。
実際に掲載された求人広告とその応募数や面接数、内定数、入社数も公開しておりますので、参考になる事例が必ずあるはずです。ぜひご覧ください。
▼応募の数を改善した企業事例▼
▼応募の質を改善した企業事例▼
▼選考中の辞退を防止した企業事例▼
▼入社後の定着率が向上した企業事例▼
▼採用工数を削減した企業事例▼
自社の採用課題の見つけ方
自社の採用課題を見つける際は、以下の図のような「求人広告のマーケティングファネル」を活用するのが有効です。露出・閲覧・応募・選考・入社の各ファネルのどこが低いかで、採用課題を特定できます。求人サイトなどを利用している場合は、こうしたデータがあるはずなので、サービス提供会社に、ぜひ見せてもらってください。

この中で、応募が集まらない原因が求人広告にあるものは以下があげられます。
応募が集まらない原因が求人広告にある場合 | |
CTR(Click Through Rate )」が低い |
求人が表示されているのに開いてもらえていない。
=求人の検索結果画面で興味喚起できていない。
|
CVR(Conversion Rate)が低い
|
求人は読んでもらえているが応募につながらない。
=求人広告で興味喚起できていない。
|
書類選考通過率が低い |
求人に応募してもらえているがターゲット外。
=求人でターゲット人材に興味喚起できていない。
|
応募が集まらない原因が求人広告「以外」にあるものは以下があげられます。
応募が集まらない原因が求人広告以外にある場合 | |
露出(impression)が低い |
求人の表示回数がそもそも少ない。
=求人が埋もれてしまって見てもらえていない。
|
面接実施率が低い |
ターゲットから応募があるものの面接を実施できない。
=面接スピードや連絡対応などに課題がある可能性がある。
|
内定承諾率が低い |
欲しい人材と面接までできているが内定を辞退される。
=面接等で十分に魅力づけできていない。
|
このように、求人広告で効果を出すためには、まず原因を見極めることが肝心です。
採用課題が生じる背景
採用課題が生じる背景には、多くの要因が関与しています。経済の変動や労働市場の変化、企業の成長段階や業界特性などが、採用における課題の発生を促す要因となることがあります。
特に大きな要因となるのが、「少子高齢化・労働人口の減少」と「働く人の価値観の変化」の2点です。
■少子高齢化・労働人口の減少
世界中で少子高齢化が進んでいます。日本は特に少子高齢化の傾向が著しく、それに伴って労働人口が減り続けています。これはつまり、「人材の希少化」が進んでいるということです。働き手が希少になり、人材不足に悩む企業が増えています。
■働く人の価値観の変化
人材の希少化が進むということは、「求職者」にとっては有利なことです。厚生労働省が発表している有効求人倍率の推移をご覧ください。

この値が「1.0倍」を超えると、求職者に有利な売り手市場と言われています。長年、有効求人倍率は1倍以上を推移しています。コロナ禍で求人が減った時期でも、1倍を割ることはありませんでした。
求職者の数より、人材募集をしている企業が多いということは、1人の求職者が複数社から内定をもらいやすくなっているということです。求職者に有利な市況が続いたため、転職を考える人が珍しくない時代になりました。
転職を以前より前向きに考える人が増え、採用も難しくなっているため、企業は以前より応募の数・応募の質・面接辞退・内定辞退・入社後の定着で悩むことが増えています。
まとめ
日本の少子高齢化・労働人口の減少は、今後も改善する目途がありません。むしろこの傾向は年々顕著になっています。これはつまり、採用課題で悩む企業は、今後ますます増えていくということです。
採用課題によって解決策は1つではありません。企業ごとに課題は異なるため、よく原因を分析して最適な解決策を選択する必要があります。
本記事でご紹介した採用課題以外にも、採用でお悩みであれば、ぜひ『エン転職』にご相談ください。『エン転職』は日本最大級となる1000万人の会員を保有する、中途採用向け求人サイトです。
エン転職は、ただ応募を集めるだけでなく、他社と差別化する方法や、貴社で活躍・定着する可能性が高い方からの応募を集める方法をご提案いたします。
エン転職を利用するかどうかは、採用戦略を考えてからご判断いただければと思います。まずはお気軽にご相談ください。
▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。
▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「採用課題一覧|14の解決策と事例を公開!」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼